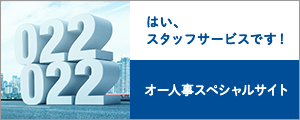協定対象派遣労働者とは?派遣労働者との違い・企業側のメリットを解説

2020年4月1日に改正された「労働者派遣法」では「協定対象派遣労働者」という言葉が多く使われています。派遣に慣れていない人にとっては聞き慣れない言葉ですが、どのような派遣労働者を指しているのでしょうか。
この記事では、協定対象派遣労働者の概要や企業が受け入れるメリット、受入時に必要となる対応について解説します。
目次
協定対象派遣労働者とは

協定対象派遣労働者とは、派遣元企業(以下、派遣会社とする)と労使協定を締結している派遣労働者のことです。2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法では、「同一労働・同一賃金」のもと雇用形態にかかわらず公正な待遇が確保されることを定めています。
派遣労働者はこれまで「正社員と同じ仕事をしているのに給与が低い」といった不合理な待遇の差が生じることもありました。
そこで改正労働者派遣法では、不合理な待遇差をなくすためにさまざまな規定が整備されています。その中のひとつとして挙げられるのが、派遣社員の待遇を決める方式についてです。
派遣社員の待遇を決定するときは「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」の2種類があります。このうち、労使協定方式によって待遇を決定している派遣労働者を「協定対象派遣労働者」と呼びます。
労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の違い
前述の通り、派遣労働者の待遇を決定する方法には「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」の2種類があります。
まず労使協定方式は、派遣元企業との間で締結した労使協定に基づいて派遣労働者の待遇が決定される方式です。派遣元企業は労働組合や労働者の代表者と労使協定を締結し、その内容に基づいて派遣労働者の待遇を決定します。
一方、派遣先均等・均衡方式は、派遣先企業で働く通常の労働者と比較して、同等以上の待遇を図る方式です。派遣先均等・均衡方式では、同じ職務に就く人や配置の変更範囲が同じ人など、派遣社員と待遇を比較しやすい人を「比較対象労働者」として選定します。
派遣先の企業はその比較対象労働者の待遇に関する情報を派遣元企業へ共有し、派遣元企業は受け取った情報をもとに派遣労働者の待遇を決定する仕組みです。
協定対象派遣労働者になれる人
協定対象派遣労働者とは、下記の条件を満たす人を指します。
・派遣元企業と労使協定を締結している
・労使協定に基づいて待遇が決定されている
なお、労使協定は記載すべき事項が定められており、その一例として下記のような点が挙げられます。
・労働者の過半数で構成される労働組合もしくは過半数代表者との間で締結されている
・「派遣元事業主単位」もしくは「労働者派遣事業をおこなう事業所単位」で締結している
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載している
・労使協定の有効期間を記載している
・派遣労働者の賃金を同業種の一般労働者の平均的な賃金額と同等以上にしている など
もし労使協定が要件を満たさないと判断された場合、労使協定方式は適用されません。厚生労働省では労使協定における自主点検表を提供していますので、適切な労使協定となるよう活用してみましょう。
協定対象派遣労働者の現状

厚生労働省では、毎年派遣元事業主から送られる「労働者派遣事業報告書」の結果を公表しています。ここでは、報告書から見る派遣労働者の現状について紐解いていきましょう。
派遣労働者は大半が協定対象派遣労働者
2023年6月1日現在、派遣労働者の人数は全国で約192万人にのぼり、前年対比で3.4%増えている状況です。
派遣労働者には「無期雇用」と「有期雇用」の2種類がありますが、それぞれ内訳は下記の通りとなっています。
|
人数 |
うち協定対象派遣労働者の人数(割合) |
|
|
無期雇用派遣労働者 |
79万1,293人 |
75万8,657人(95.9%) |
|
有期雇用派遣労働者 |
113万3,162人 |
105万6,870人(93.3%) |
|
合計 |
192万4,455人 |
181万5,527人(94.3%) |
出典:厚生労働省「労働者派遣事業の令和5年6月1日現在の状況(速報)」
上記結果を見ると、無期雇用・有期雇用にかかわらず現在は協定対象派遣労働者が大多数を占めていることが分かります。
無期雇用派遣労働者には3年ルールが適用されない
派遣労働者にはいわゆる「3年ルール」があり、1人の派遣労働者が同じ課で3年を超えて働くことはできません。そのため「長期的な人材確保が難しい」と感じている企業もあるかもしれません。
しかし、派遣労働者には「無期雇用」としての働き方もあり、この場合は3年ルールが適用されない仕組みとなっています。
前述の報告書を見ると、無期雇用派遣労働者は全体の約40%となっていますので、長期的な人材を確保したい場合は無期雇用の派遣労働者を受け入れるのもひとつの方法です。
協定対象派遣労働者を受け入れるメリット・デメリット

企業が協定対象派遣労働者を受け入れる際は、メリット・デメリットのどちらも理解しておく必要があります。それぞれくわしく紹介していきましょう。
メリット
協定対象派遣労働者を受け入れるメリットとして、主に下記のような点が挙げられます。
|
・即戦力となる人材を確保できる |
派遣元企業では専門性の高い人材を幅広く確保しており、企業の要望に合わせて適切な人材を派遣する体制を整えています。そのため、即戦力となる人材を確保することができ、スムーズに業務を遂行することができます。
また、派遣先企業は自社で人材を採用したり、育成したりする必要がなく、採用や教育にかかるコストを削減できる点も大きなメリットです。事業をおこなううえで最も負担の大きいコストとなりやすい人件費を抑えられるのは、経営戦略としても効果的といえます。
さらに、派遣労働者の受け入れは柔軟な人員調整にもつながります。派遣労働者は派遣期間を調整することができ、「人手が足りない繁忙期のみ受け入れる」という選択も可能です。
デメリット
一方、協定対象派遣労働者を受け入れることには、下記のようなデメリットも存在します。
|
・派遣労働者の受入体制を整える必要がある |
派遣労働者は即戦力となりやすいとはいえ、業務に必要なスキルを学ぶ研修などは他の従業員と同様に実施しなければなりません。これは労働者派遣法でも定められていることで、同じ業務に就く他の従業員に対して教育訓練を実施している場合は、派遣労働者に対しても同様の教育訓練を実施する必要があります。
そのため、派遣労働者を受け入れる際は、必要に応じて研修や教育体制を用意しておくようにしましょう。
また、協定対象派遣労働者では、派遣元企業と締結した労使協定に基づいた給与が支払われます。派遣先均等・均衡方式と違って、派遣先企業の従業員の給与水準などは考慮されないため、かえってプロパーの従業員を雇用する場合よりも人件費が高くなることもあります。
派遣先企業に求められる対応

派遣先企業は、協定対象派遣労働者を受け入れる際にいくつかおこなうべき対応があります。それぞれくわしく確認していきましょう。
待遇等に関する情報提供
協定対象派遣労働者に適用される労使協定方式では、派遣先企業から派遣会社(派遣元企業)へ下記の情報を提供しなければなりません。
・業務に必要なスキルを身につけるための教育訓練
・食堂、休憩室、更衣室など福利厚生施設の利用
これらの情報を提供するのは、派遣労働者と他の労働者との間に不合理な待遇差を生じさせないためです。たとえば、「正社員は食堂や休憩室を利用できるのに、派遣社員には理由なく利用が禁じられている」という場合、労働者派遣法に違反していると見なされる可能性があります。
協定対象派遣労働者を受け入れる際は、他の従業員との間に教育体制や福利厚生施設の利用で不合理な差が生じないように配慮しましょう。
なお、派遣先均等・均衡方式では比較対象労働者の職務内容や雇用形態、待遇内容などの情報を派遣会社(派遣元企業)へ提供する必要があります。
教育訓練の機会、福利厚生施設の提供
派遣先企業は、派遣会社(派遣元企業)へ提供した情報に基づき、派遣労働者へ教育訓練の機会や福利厚生施設の利用環境を提供します。このとき、他の従業員との間に不合理な差が生じることは認められず、他の従業員に提供されているものは同じように派遣労働者にも提供しなければなりません。
なお、派遣労働者は労使協定のもと待遇が決定されますが、労使協定の協定書作成や周知は派遣会社(派遣元企業)がおこないます。
協定対象派遣労働者を受け入れるには
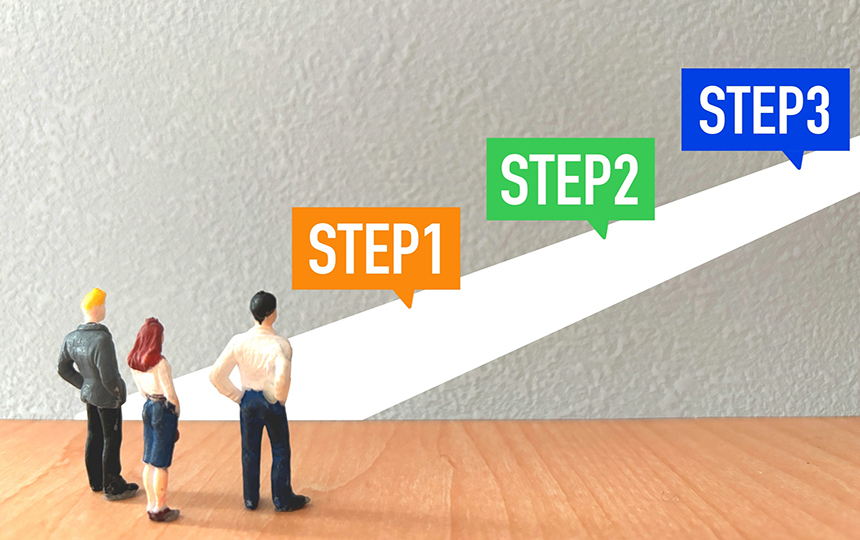
派遣先企業が協定派遣労働者を受け入れる際は、下記の流れに従って手続きを進めます。
1.派遣会社(派遣元企業)を選定する
2.派遣労働者に求める希望条件を伝える
3.派遣会社(派遣元企業)と労働者派遣契約を締結する
4.派遣労働者を受け入れる
それぞれくわしく確認していきましょう。
1.派遣会社(派遣元企業)を選定する
まずは労働者の派遣を依頼する派遣会社(派遣元企業)を選定します。派遣会社(派遣元企業)によって、派遣している業種や職種、料金体系、サポート内容などが異なります。
複数の事業者を比較したうえで、どこから派遣労働者を受け入れるか検討してみましょう。
なお、労働者派遣事業は許可制となっており、無許可の事業者から労働者派遣を受けた場合は行政指導の対象となってしまいます。派遣元企業を選定する際は、適切に厚生労働省から許可を受けている事業者か確認するようにしましょう。
2.派遣労働者に求める希望条件を伝える
派遣会社(派遣元企業)が選定できたら、次に派遣労働者に求める希望条件を伝えます。
派遣先企業は、派遣労働者を受け入れるにあたっての面接をおこなうことはできません。そのため、具体的なリクエストを出していなければ、実際に派遣された労働者に対してミスマッチを感じてしまう要因にもなります。
なるべく希望に沿った労働者を受け入れるためには、必要とするスキルや人材像を具体的に伝えておくことが大切です。
また、このとき派遣会社(派遣元企業)へ他の従業員の待遇に関する情報提供もおこないます。
3.派遣会社(派遣元企業)と労働者派遣契約を締結する
派遣会社(派遣元企業)へ支払う派遣料金やその他条件に問題がなければ、派遣会社(派遣元企業)と労働者派遣契約を締結します。
その後、派遣会社(派遣元企業)では労働者派遣法に基づき、派遣労働者に対して待遇情報や就業条件などの説明がおこなわれます。
4.派遣労働者を受け入れる
契約手続きを終えると、いよいよ派遣先企業で派遣労働者を受け入れます。もし、他の従業員に対して業務に必要なスキルの習得のために研修などを実施している場合は、派遣労働者に対しても同様に実施しなければなりません。
派遣労働者がスムーズに業務に取り掛かることができるよう、事前に受け入れ体制を整えておきましょう。
まとめ
協定対象派遣労働者は、派遣元企業との間で労使協定を締結している派遣労働者です。待遇条件は労使協定によって定められており、現在は派遣労働者の大半を協定対象派遣労働者が占めています。
派遣労働者の受け入れには即戦力となる人材の確保や採用コストの削減など、多くのメリットがあります。「繁忙期に向けて人手を増やしたい」と考えている企業は、派遣労働者の受け入れを検討してみてはいかがでしょうか。
<ライタープロフィール>
椿 慧理
フリーライター。新卒後に入行した銀行で10年間勤務し、個人・法人営業として金融商品の提案・販売を務める。現在は銀行で培った多様な経験を活かし、金融・人材ライターとして幅広く活動中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者資格を保有(編集:株式会社となりの編プロ)