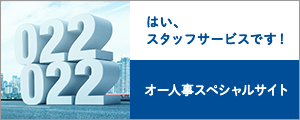雇用安定措置とは?対象者や派遣会社が取るべき措置について解説

派遣労働者の活用には「採用コストを抑えて人材を確保できる」「一時的な人手不足を補える」「社員がコア業務に集中しやすくなる」などさまざまなメリットがあります。
一方で、2015年の派遣労働法改正により雇用安定措置が制定され、業種に関係なく派遣期間に制限が設けられるなど、派遣労働者の活用に注意しなければならない点も増えました。特に長期的な派遣労働者の活用や、派遣労働者の直接雇用を検討している企業では、雇用安定措置の内容を理解し、適切に対応することが求められます。
そこで本記事では、雇用安定措置制度の内容と具体的な措置について詳しく解説します。
目次
雇用安定措置とは

雇用安定措置とは、派遣労働者の安定した就労を維持するために、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)で定められた派遣元事業主(人材派遣会社)に生じる義務のことです。
雇用安定措置の遂行は派遣労働者の意向や状況によって変わるものではありますが、同一組織での派遣就業が3年以上になる見込みがある場合に、雇用安定措置を講じる義務が課せられます。また、派遣労働者が同一組織で1年以上就業した場合には、努力義務が発生します。
まずは雇用安定措置が制定された背景とともに、制度の概要について詳しく解説します。
雇用安定措置が制定された背景
雇用安定措置が制定された背景には、「専業26業務」に該当する業務に対する認識の変化や、派遣先企業による派遣労働者の不当な扱いといった社会問題への対処などが挙げられます。
専業26業務とは、専門知識やスキルが必要な仕事であり、経験の期間で成果が左右される業務だとされる26の業務のことです。ソフトウェア開発や機械設計、秘書、添乗などの業務が該当し、この業務の従事者には派遣期間の制限がなく、半永久的に派遣労働者として同一人物を雇用し続けることが可能でした。
しかしこのことが「本来正社員として雇用すべき労働者を長期にわたって派遣労働者のまま雇用する」「専業26業務に従事させると偽って、該当しない業務を無期限で担当させる」といった制度の悪用を招きます。
こうした背景から、2015年の派遣労働法改正では専業26業務が撤廃され、「業種に関係なく派遣労働者が同じ職場で働けるのは3年まで」という統一的なルールが設けられました。
加えて、派遣労働者が就業に関して不当な扱いを受け続けることが社会問題化したこともあり、派遣労働法の改正に至るわけですが、期限を設けただけでは派遣労働者の安定した雇用は守れません。
そこで、継続的な就労とキャリア形成につなげるための制度として、雇用安定措置が制定されたのです。
雇用安定措置の対象となる派遣労働者の条件
雇用安定措置の対象となる派遣労働者の条件には以下があります。
● 派遣就業見込みが3年
● 継続就業を希望している
● 有期雇用契約の派遣労働者
注意したいのは、あくまで派遣労働者側の意見が優先される点です。派遣終了後、派遣労働者が派遣元の人材派遣会社で継続して働くことを希望しない場合は、雇用安定措置の対象とはなりません。また、派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合も対象外です。
参考:厚生労働省「雇用安定措置について
義務発生のタイミング
雇用安定措置を講じる義務が発生するのは、同一の組織単位の業務に対する派遣就業見込みが1年以上となる場合です。派遣就業見込みが3年となる場合は「義務」、1年以上3年未満の場合は「努力義務」とされています。
例えば契約時に派遣期間を3年で契約した場合、就業開始時点で派遣就業見込みが3年となるため、即時義務が発生します。6ヶ月契約の場合は、次の更新時に派遣就業見込みが1年となるため、この時点で努力義務が発生することになります。
参考:厚生労働省「雇用安定措置について」
派遣元事業主の具体的な雇用安定措置
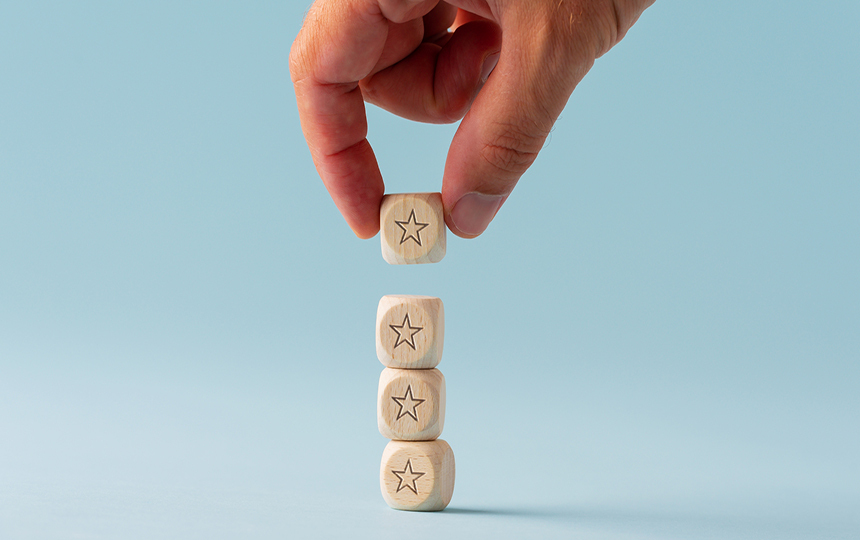
派遣労働者が所定の条件を満たしている場合、派遣元事業は以下の4つのうちいずれかの措置を取る必要があります。
以下参考:厚生労働省「労働者派遣事業報告(令和5年度)」
派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)
派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)は、派遣元から派遣先に対して直接雇用を打診する措置のことです。直接雇用の依頼があった場合、派遣先企業には優先雇用の努力義務が生じます。
派遣労働者の直接雇用は、企業側にとって「3年の期限に悩まされる必要がなくなる」「即戦力を採用できる」「ミスマッチのリスクを押さえられる」「採用コストの削減」などメリットの多い選択です。一方で「労務管理の負担が増える」「社会保険など人材管理コストの増加」といったデメリットもあります。
ただし雇用形態の規定はないため、正社員に限らず契約社員、アルバイト、パートなどどの形態でも問題ありません。厚生労働省による令和5年度の労働者派遣事業報告では、雇用安定措置対象の派遣労働者のうち、直接雇用措置を講じた割合は5.4%。そのうち41.2%が実際に雇用されています。
なお、派遣先への直接雇用の依頼は、あくまで派遣元が講じなければならない措置のひとつで、職業安定法上の職業紹介には該当しません。したがって、派遣先企業は派遣元事業主に対して職業安定法上の職業紹介手数料を支払う義務はないのです。
また、派遣期間満了後であれば派遣先側から直接雇用を打診することも可能ですが、この場合も手数料は必要ありません。
参考:厚生労働省岐阜労働局「労働者派遣事業適正化研修会」
新たな派遣先の提供(2号措置)
2号措置は派遣元事業主が派遣労働者に対して、新たな派遣先を提供する措置です。派遣労働者の能力、経験、居住地、就業場所、通勤時間、そして賃金など以前の派遣先での待遇などを考慮し、合理的な範囲で提供する必要があります。
例えば「エンジニアとして働いていた派遣労働者に、これまで経験していない事務職をすすめる」「転居を伴うような無理のある派遣先をすすめる」などは合理的とはいえません。
とはいえ派遣元は通常、多くの派遣求人を保有しているため、派遣労働者に合わせた新たな派遣先を提供できる可能性はあり、結果として2号措置を取ることが多くなっています。
実際、厚生労働省による令和5年度の労働者派遣事業報告を見ると、雇用安定措置対象の派遣労働者のうち52.8%と半数以上に2号措置が講じられています。なお、この2号措置には派遣元での無期雇用派遣への移行(無期転換ルール)も含まれます。
※関連記事
派遣の「5年ルール」とは?制度内容、適用条件、メリットを解説
派遣元での無期雇用(3号措置)
3号措置は、派遣元で派遣労働者としての業務ではなく、営業や人事部門など別業務への従事者として無期限雇用をする措置です。つまり「派遣元で正社員として雇用すること」と捉えるとわかりやすいでしょう。派遣元のグループ企業などでの雇用も該当します。
派遣労働者として従事していたとはいえ、無期限雇用の際には書類選考、面接、筆記試験など、通常の採用試験と同様の試験が課せられるのが一般的です(ただし、企業や状況によっては、これまでの勤務実績を考慮した面談が中心となる場合もあります)。希望の職種で募集があるとは限らず、3号措置を選ぶ雇用安定措置対象者は少ない傾向です。
厚生労働省による令和5年度の労働者派遣事業報告を見ると、3号措置を受けた対象者はわずか1.2%と全ての措置の中で最低でした。
その他の安定した雇用の継続措置(4号措置)
1~3号のいずれの措置も選択しない場合、「紹介予定派遣の対象とする」「有給の教育訓練をおこなう」などの措置を取らなければなりません。
紹介派遣とは直接雇用を前提とする派遣のことです。6ヶ月の派遣期間の後、あらためて選考がおこなわれ直接雇用の是非が決定します。教育訓練とは資格の取得や職業訓練などが該当します。派遣元事業主は派遣労働者と雇用関係を維持したまま、有給でキャリアアップにつながる措置を講じることが求められます。
厚生労働省による令和5年度の労働者派遣事業報告の結果では、雇用安定措置が講じられたケースのうち4号措置の割合は全体の5.3%でした。さらに、この4号措置のうち紹介予定派遣が選択された割合は8.1%です。
雇用安定措置と関連する制度・注意点

雇用安定措置と関連し、派遣労働者の雇用を守るために整備された制度や注意点を解説します。
労働契約申込みみなし制度
禁止業務への派遣や二重派遣などの違法派遣を是正し、派遣労働者の安定した雇用を担保するために整備された制度に「労働契約申込みみなし制度」があります。
雇用安定措置と同様に2015年に導入された制度で、派遣先企業が違法派遣に該当すると知りながら派遣労働者を受け入れている場合、派遣元の労働条件と同等の条件で労働契約(直接雇用)を申込んだものとみなします。
労働契約申込みみなし制度の対象となるのは、以下の5つです。
● 派遣労働者を港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務派遣といった禁止業務に従事させる
● 無許可の事業主から労働者派遣を受ける
● 事業所単位の期間制限(3年)に違反して労働者派遣を受ける
● 個人単位の期間制限(3年)に違反して労働者派遣を受ける
● 請負契約を締結しているにもかかわらず実際には労働者派遣を受ける偽装請負
ただし、派遣先企業が違法派遣だと知らずに受け入れており、知らなかったことに過失がないと判断された場合は適用されません。
参考:厚生労働省「労働契約申込みみなし制度の概要」
雇用安定措置逃れ
これまで述べてきたように、有期雇用の派遣労働者は3年を超えて同じ企業・課で働き続けることはできません。雇用安定措置は3年を経て派遣契約が終了した際、派遣労働者が失業しないための措置です。
派遣元事業主がこの措置の対応から逃れるために、業務上の必要性がないのに派遣期間を3年未満とすることは「雇用安定措置逃れ」と判断されます。これは義務違反に当たり、労働派遣事業の許可取消など重い措置の対象になります。
企業が適切に対応するためのポイント

雇用安定措置は派遣元に対して課せられる制度ですが、派遣労働者の雇用を守るためには、派遣労働者を受け入れる企業にも適切な対応が求められます。派遣労働者に安心して働いてもらえる環境を提供し、かつ偽装請負など違法行為に巻き込まれないために、以下の点を押さえておきましょう。
雇用安定措置を講じる義務と努力義務の理解
雇用安定措置には「義務」と「努力義務」の2種類があります。この義務と努力義務の違いは、法的拘束力の高さです。義務は努力義務より法的拘束力が高く、規定に対する実行や記録が求められます。努力義務には法的拘束力がありませんが、努力義務をおこたるさまが悪質だった場合は指導などの対象になる可能性があります。
先述のように、派遣就業見込みが3年の場合、雇用安定措置の実行は義務です。1年以上3年未満の場合は努力義務となります。
ほかにも雇用安定措置では、派遣元が対象の派遣労働者の希望する措置内容を聞き取り、派遣元管理台帳(派遣労働者の就業状況や措置内容などを記録する台帳)に記載することを義務づけています。義務違反の場合、労働派遣事業の許可取消といった罰則や監督機関からの厳しい指導が適用されます。
実は、派遣先企業にも義務や努力義務が課せられています。例えば、派遣労働者の日ごとの就業時間や従事する業務の種類、紹介派遣に関する内容、派遣労働者からの苦情やその処置に関する内容などを記録する「派遣先管理台帳」の作成と保管は、派遣先企業の義務です(自社正社員と派遣労働者を合わせた人数が5人以下の場合は免除)。
また、雇用安定措置により派遣元より直接雇用の依頼があった際は、優先雇用の努力義務が生じます。
派遣元との連携
派遣労働者の受け入れに際し、派遣先と派遣元の連携は欠かせません。例えば派遣先が業務内容や職場の雰囲気、求めるスキルや経験、人物像を正確に派遣元に伝えることは、最適な人材の選出に役立ちます。
加えて、業務上の課題や人間関係の悩みについて共有できる体制が整っていれば、派遣元はキャリアカウンセリングを、派遣先は業務調整をおこなうなど、多角的なサポートを提供できるでしょう。
もし、派遣労働者がハラスメントや職場のトラブルに巻き込まれた場合でも、派遣先と派遣元の連携が取れていれば、迅速に対応して被害の拡大を防ぎ、派遣労働者の心身の健康を守ることができます。
派遣労働者は自社の社員ではありませんが、共に働く一員としてサポートすることが派遣労働者の安定した活用につながります。
対象となる派遣労働者への適切な周知や情報提供
派遣先企業としても派遣可能期間の3年を理解し、雇用安定措置対象者へ周知することは大切です。もし何らかの理由で期間を延長したい場合は、派遣先の労働者過半数で組織する「過半数労働組合」の意見を聞くことで、最大3年間延長できる可能性があります。
派遣労働者と普段からコミュニケーションを取っておけば、こうした対応が必要な場合もスムーズに進められるでしょう。
また雇用安定措置の一環として、同一企業で継続して3年間就労する見込みの派遣労働者に対して、派遣先企業は社員募集情報を提供する義務があります。情報提供は「対象者に直接メールなどで情報提供する」「派遣元に情報を提供し、派遣元を通じて対象者に伝える」「事業所内の掲示版に求人票を張り出す」のいずれかの方法でおこないます。
なお、対象者に直接情報提供した場合でも、その事実は派遣元に伝えるのが望ましいとされています。あとで条件の齟齬などが生じないよう、提供した内容は記録しておきましょう。
まとめ
派遣労働者の受け入れには期限があり、雇用安定措置はその期限に達する場合に提供される派遣労働者の雇用安定のための制度です。基本的に派遣元が派遣労働者にヒアリングし、どのような措置を選ぶかを決めていきます。
派遣先企業としても期限があることを理解し、契約にない業務には従事させないなどのルールを守った活用が欠かせません。まずは、自社で受け入れている派遣労働者の契約状況を確認し、雇用安定措置の対象となり得る方がいる場合は、派遣元事業主と連携して適切な準備を進めましょう。そして、派遣労働者とも積極的にコミュニケーションを取り、共に働きやすい環境作りを心掛けてはいかがでしょうか。
<ライタープロフィール>
筆弓あかり
子育てと介護のダブルケアと仕事の両立に悩みながら、ライターとして活動中。美容、転職、介護を中心にさまざまなメディアの記事執筆、ディレクションを担当。転職、採用・人事、法律メディアで編集業務に携わる。「働き方」「仕事の選び方」「ライフスタイル」「美容」に強みを持ち、幅広いビジネスパーソンに向けて発信を続けている(編集:株式会社となりの編プロ)。