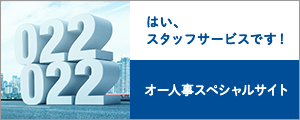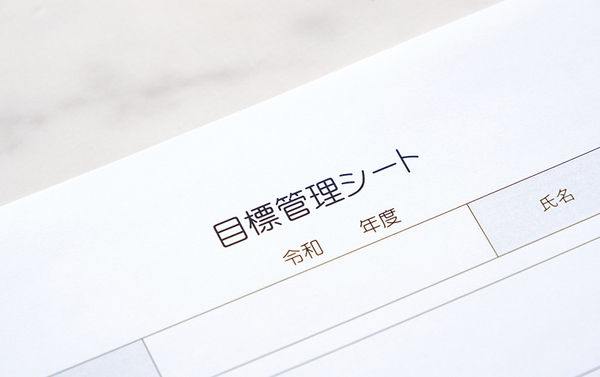準委任契約とは?請負との違い・種類・成果完成型について解説

準委任契約は、主に専門的なサービスや役務の提供を依頼するときに用いられる契約形態です。専門家へ業務を委託できるメリットがあるものの、契約時にはいくつかの注意点があります。
本記事では、準委任契約の特徴や種類、他の類似する契約形態との違い、契約時の注意点について解説します。
目次
準委任契約とは

はじめに、準委任契約業務の概要や主に用いられる具体的な場面、契約の種類について確認していきます。
準委任契約
準委任契約とは業務委託契約の一種で、主に特定の業務を外部の専門家へ依頼するときに用いられる契約です。
準委任契約は「業務の遂行」を目的とした契約であり、成果の達成については問われません。そのため、具体的な成果物が制作されにくい業務や、目に見える成果に直結するとは限らない業務に適用されることが多い契約です。
具体的には、下記のような法律行為以外の業務に用いられています。
・コンサルタントによる経営改善やマーケティング戦略への助言
・公認会計士による会計監査
・システムエンジニアによるシステムの設計・運営
・広告代理店によるキャンペーンの企画・実行
例えば、コンサルタントに経営改善に関する専門的なアドバイスを依頼している場合、適切なアドバイスが行われたにも関わらず、結果として理想通りの経営改善が達成されなかったとしても、業務を依頼されたコンサルタントには責任が発生しません。
なお、業務を依頼する側を「委任者」、業務を受ける側を「受任者」と言います。
準委任契約の種類
準委任契約には、「成果完成型」と「履行割合型」の2つの契約形態があります。
成果完成型
成果完成型とは、依頼した業務やプロジェクトが完了した時点で報酬が支払われる契約形態です。例えば、マーケティング専門のコンサルタントに新商品の販売促進施策の立案や実行を依頼し、成果物が得られたときに報酬を支払う契約が挙げられます。
この契約形態は成果物の納品に基づいて報酬を支払う形を取ることで、委任者の金銭的なリスクを低減することができます。事前に委任者・受任者間で成果物の定義を明確に決めておくと、成果物に対する認識がずれるなどのトラブルを減らせるでしょう。
履行割合型
履行割合型とは、依頼した業務の遂行状況に応じて報酬が支払われる方式です。例えば、システムエンジニアにシステム開発を依頼する際、「設計」「実装」「テスト」「納品」などの工程ごとに報酬を支払う契約が挙げられます。
委任者にとっては、業務の進捗状況を確認しながら報酬を支払うため、リスク管理がしやすくなる点がメリットです。また受任者にとっても、プロジェクトが長期にわたる場合でも定期的に報酬を受け取れ、キャッシュフローが安定しやすくなるという利点があります。
受任者には「善管注意義務」が発生する
準委任契約は業務の遂行を目的とした契約であり、成果の達成については問われませんが、だからといって委任された業務を無責任に取り扱ってよいわけではありません。
依頼を受けた受任者には「善管注意義務」が発生します。これは「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」というもので、民法第644条にも定められています。
例えば、システムエンジニアにシステムの保守・メンテナンスを依頼する際、受任者側は持てる技術や情報を活用し、システムの安全性を確保するよう注意を払わなければならないのです。
準委任契約と他の契約形態との違い

準委任契約と類似した契約形態として、「請負契約」「労働者派遣契約」「委任契約」「業務委託」が挙げられます。それぞれどのような契約形態なのか、詳しく紹介していきましょう。
請負契約との違い
請負契約とは業務委託契約の一種で、特定の業務を完成することを約束して締結される契約です。
請負契約が用いられる業務としては、建築・工事や運送、デザイン制作業務などが挙げられます。例えば建築・工事業務では、依頼された建築物を完成させることが契約の大きな目的です。もし完成に至らなかった場合は「債務不履行」とみなされ、場合によっては損害賠償請求が行われることもあります。
「外部の専門家へ業務を依頼する」という点では準委任契約と似通っているものの、準委任契約では「業務を遂行すること」そのものを目的としている点が大きな相違点です。準委任契約では善管注意義務を遵守していれば、その成果の達成度合いについては問われません。
労働者派遣契約との違い
労働者派遣契約とは、企業が人員確保のために派遣会社から労働者を派遣してもらうための契約です。労働者は派遣された企業との間に雇用契約はないものの、その指揮命令下に入るという特徴があります。
したがって企業は、労働者に就業規則を遵守させ、業務をおこなううえで指揮・監督することが可能です。
一方、準委任契約では、業務の内容について委任者から受任者へ一定の指図をおこなうことはできるものの、働く時間や勤務時の服装といったことまでを命令することはできません。
委任契約との違い
委任契約と準委任契約はいずれも外部の専門家へ業務を依頼するための契約形態ですが、委任契約は弁護士や税理士などに「法律行為」を依頼する際に用いられる契約です。
法律上では委任契約への定めが準委任契約に準用されているため、それ以外の点で大きな違いはありません。
例えば、弁護士に自社が締結する契約書チェックを依頼する際は委任契約が用いられ、システム開発や事業戦略コンサルティングなど法律に関わらない業務に関しては準委任契約が用いられています。
業務委託との違い
業務委託とは、外部の企業や個人に特定の業務を依頼することです。委任者と受任者の間に雇用関係はなく、受任者は対等な関係の下で業務を遂行します。
つまり、これまで紹介した準委任契約や請負契約、委任契約はいずれも業務委託の一種です。どの契約形態を用いるかは、依頼する業務内容や目的、報酬の支払い方、責任の範囲を踏まえたうえで決定するとよいでしょう。
フリーランスとの違い
フリーランスとは、特定の企業に雇用されず、各企業や個人と契約を結んで業務をおこなう働き方やその人材を指す言葉です。
フリーランスは原則として業務委託契約を締結して働くため、業務内容によっては準委任契約を締結することもあります。その際は「善管注意義務」が発生するため、発注した企業がこれに違反していると判断した場合には、フリーランスに損害賠償などを求めることが可能です。
準委任契約のメリット

準委任契約を用いるメリットとして、下記のような点が挙げられます。
・契約期間に制限がなく柔軟に対応ができる
・専門家に業務を委託できる
・業務範囲が定められており契約の透明性が高い
それぞれ詳しく紹介していきましょう。
契約期間に制限がなく柔軟に対応ができる
準委任契約では、双方の合意のもとで納期や契約期間を決定します。このとき「最低〇〇日以上の契約期間が必要」といった法的な制限はありません。
仮に日雇い派遣によって労働者を受け入れる場合、原則雇用期間が31日以上必要なため、企業側は必要以上に人件費の負担が発生することもあるかもしれません。
その点、準委任契約ではそうした法的な制限がないため、双方の都合に応じて自由に契約期間を取り決めることが可能です。例えば「繁忙期だけ業務を委託する」といった対応もでき、人手不足の解消につながるメリットもあります。
専門家に業務を委託できる
専門知識が必要な業務を外部の専門家へ委託できるのも、準委任契約の大きなメリットです。
例えば、経営コンサルティングに長けた人材を社内で確保する場合、高いコストが必要となることも珍しくありません。今後を見据えて社内で人材育成する場合についても、教育にかかるコストは相当なものです。
しかし、準委任契約であれば外部の専門家へ直接依頼ができるので、社内で人材を確保したり教育したりする必要がありません。当然、専門家への報酬は発生するものの、自社で雇用する場合に比べれば安価に済む可能性が高いでしょう。
また、外部へ委託する際は、複数の委託先を比較した上で、より専門性が高いところやニーズが合致するところへ依頼できる点も大きなメリットです。
業務範囲が定められており契約の透明性が高い
準委任契約を締結する際は、主に下記のような事項を記載した契約書を締結します。
・委任する業務内容
・契約期間
・報酬と支払方法
・経費の精算方法
・契約解除をおこなう条件
・成果物の知的財産権に関する取り扱い
・損害賠償責任の有無 など
このように契約書にて業務内容や責任の範囲、契約期間を明確に定めることで、後々トラブルに発展するリスクを防ぐことができます。報酬についても支払うタイミングや支払い方法をきちんと定めておくことで、委任者・受任者どちらも安心感を持ちながら業務を進められるメリットがあります。
準委任契約のデメリット
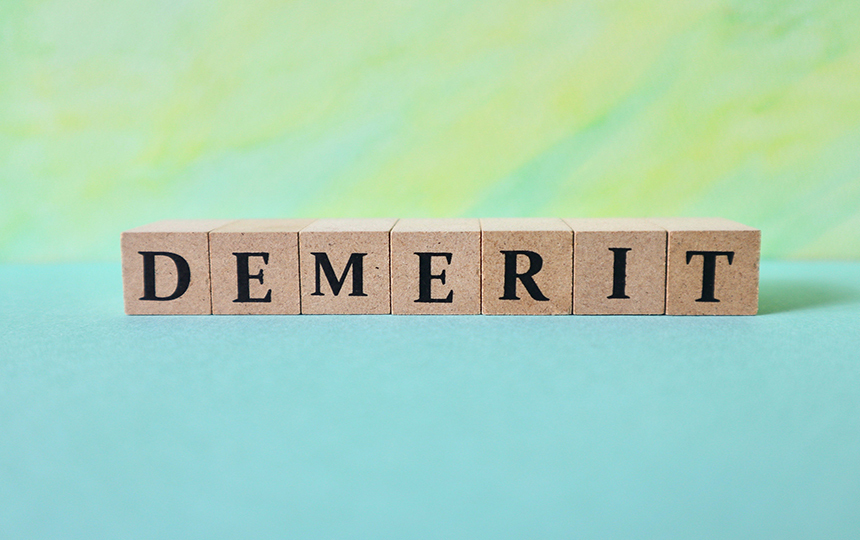
さまざまなメリットがある準委任契約ですが、その一方で下記のようなデメリットも存在します。
・指揮命令権限がない
・期待通りの結果が得られなくても報酬を支払う必要がある
・契約期間内に業務が終わらなくても報酬を支払う必要がある
・成果が不透明になるケースがある
それぞれ詳しく解説していきましょう。
指揮命令権限がない
準委任契約の委任者と受任者の間には雇用契約がなく、指揮命令権限も発生しません。
例えば、派遣労働者を受け入れる場合、企業側には指揮命令権限があるため、業務の進め方や取り組み方などを細かく指示することができます。
しかし準委任契約では、委任者側から受任者へ業務の取り扱いなどについて一定の指示を出すことはできるものの、勤務時間や作業場所、業務の進め方といったことまでを指示することはできません。
「何度も依頼しているから成果物のクオリティには問題がない」といった信頼関係がある場合は、それほど問題ないでしょう。しかし、初めて契約を結ぶ先などに対して細かく業務命令を下せない点は不安に感じられるかもしれません。
受任者に対して具体的な指示・命令を出したい場合については、準委任契約ではなく他の契約形態を選択することもひとつの方法です。
期待通りの結果が得られなくても報酬を支払う必要がある
準委任契約では原則として成果物の保証がないため、期待通りの結果が得られなくても事前に定めた報酬を支払う必要があります。
「経営コンサルティングを頼んだけれど期待する効果が得られなかったため、違うコンサルティング会社に依頼し直す」という場合、当初想定したよりも大きなコストがかかってしまいます。
契約期間内に業務が終わらなくても報酬を支払う必要がある
準委任契約では業務の遂行に対して報酬が支払われますが、仮に契約期間内に業務が終わらなかったとしても、予定していた報酬を支払う必要があります。例えば、システム開発のプロジェクトの進捗が遅れた場合、工期が延びたことでコストが膨らむ可能性があるのです。
このほか「想定外の作業が発生した」「当初の工数見積もりが甘かった」などを理由に、当初予定していたコストを大幅に上回ってしまうことも考えられます。
成果が不透明になるケースがある
準委任契約では業務の遂行そのものが契約の目的となるため、成果の基準が曖昧になるケースがあります。
もし「思っていたような成果が得られなかった」という場合でも報酬を支払う必要があるため、結果として委任者側に不満が残ることも考えられるでしょう。
双方に不満のないように業務を進めるためには、契約を締結する段階で「報酬を支払う具体的な基準はどのようなものか」「どのような成果を求めるか」といったことを明確に定めておくことが大切です。
準委任契約の注意点

準委任契約を用いる際は、下記のような点に注意する必要があります。
・偽装請負とならないように注意が必要
・契約内容を明記しトラブルを防ぐ
・収入印紙が必要な場合がある
それぞれ詳しく解説していきましょう。
偽装請負とならないよう注意が必要
準委任契約では「偽装請負」とならないよう注意が必要です。偽装請負とは、契約上は準委任契約であるにもかかわらず、実態は労働者派遣に当てはまるものを指します。
準委任契約を結ぶ企業の中には、「人件費を削減したい」「労働者派遣契約をおこなう手間をかけたくない」といった気持ちから、労働者派遣契約ではなく準委任契約を選ぶところもあるようです。
しかし、実態として「業務内容について指示命令を出す」「勤務時間を指示する」といったことが行われていれば、偽装請負とみなされる可能性が高いと言えます。
また、偽装請負をおこなうつもりがなくても、知識不足などの要因によって法令違反を犯してしまう場合もあります。準委任契約を結ぶ場合は、法的な要件や禁止行為などをきちんと理解したうえで委託をおこなうことが大切です。
契約内容を明記しトラブルを防ぐ
準委任契約を締結する際は、後々トラブルに発展することを防ぐために双方の認識をすり合わせておく必要があります。特に、次のような点は契約書にしっかりと明記しておきましょう。
・委任する業務内容
・契約期間
・報酬と支払方法
・経費の精算方法
・契約解除をおこなう条件
・成果物の知的財産権に関する取り扱い
・損害賠償責任の有無 など
例えば、業務内容を具体的に明記しておくことで「想定していた成果物が得られない」などの事態を防ぐ効果があります。また、受任する側にとっても「業務内容が曖昧でわかりにくい」といった負担が生じにくくなるでしょう。
加えて、特にトラブルになりやすい報酬面についても注意が必要です。「どの段階で報酬が発生するのか」「成果が得られなかったときも報酬が支払われるのか」といったことは双方で合意の上で明記しておきましょう。報酬の支払い方法や振込手数料の取り扱いなどについても定めておくと安心です。
収入印紙が必要な場合がある
準委任契約の契約書については、原則収入印紙の貼付は不要です。ただし「第1号文書」や「第7号文書」に該当する場合は、収入印紙を貼付しなければなりません。
| 文書 | 概要 |
| 第1号文書 | 無体財産権の譲渡に関する契約書 |
| 第7号文書 | 継続的取引の基本となる契約書 |
例えば、第1号文書の「無体財産権の譲渡に関する契約書」に該当するものとして、システムやアプリ、プログラムなどの開発に関する準委任契約が挙げられます。
もし、収入印紙の貼付を失念してしまった場合、ペナルティとして「過怠税」が課される可能性があります。過怠税では本来納めるべき印紙税の最大3倍もの税金が課されてしまうため、準委任契約を締結する際は必ず収入印紙の貼付の要否を確認しておきましょう。
まとめ
準委任契約は、特定の業務を外部企業や個人へ依頼する際に用いられる契約形態です。専門家へ業務を依頼できるメリットがある一方、委任側に指揮命令権限がないことや、成果が不透明になる可能性がある点には注意が必要です。
また、類似する契約形態として請負契約や委任契約などが挙げられます。外部への業務委託を検討する際は、業務内容や目的、報酬の支払い方などを踏まえたうえで、どの契約形態が適切か検討してみるとよいでしょう。
<ライター:椿慧理>
フリーライター。新卒後に入行した銀行で10年間勤務し、個人・法人営業として金融商品の提案・販売を務める。現在は銀行で培った多様な経験を活かし、金融・人材ライターとして幅広く活動中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者資格を保有(編集:株式会社となりの編プロ)