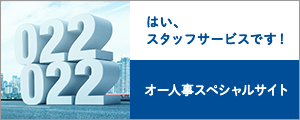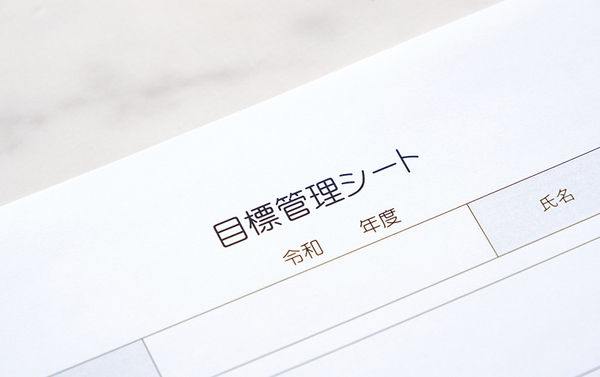出生後休業支援給付金とは?支給要件・企業側の対応について解説

2025年4月より「出生後休業支援給付金」の支給がスタートします。育児休業を取得する際は「育児休業給付金」が給付されますが、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、出生後休業支援給付金の制度概要や支給要件、従来の給付金との違いについて解説します。
目次
出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金とは、共働き世帯の子育てを支援するため、原則として両親ともに育児休業を取得したときに受けられる給付金です。まずは、出生後休業支援給付金の制度概要や支給要件を確認していきましょう。
制度の概要
出生後休業支援給付金とは、令和6年の雇用保険制度改正に伴い、新しく創設された制度です。
子が生まれてから一定期間内に、原則両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生時育児休業給付金」が、または「育児休業給付金」に上乗せで「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
出生後休業支援給付と従来の育児休業給付の違い
雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、育児休業給付金が給付されます。しかし、給付率は休業開始前賃金の67%(手取り額の8割相当)となっており、育児休業中は収入の減少が避けられません。そのため、特に主な生計者にとっては育児休業の取得をためらう大きな要因となっていました。
しかし、新たに創設される出生後休業支援給付金は、一定の支給要件を満たした被保険者に対して、休業開始前賃金の13%相当額が上乗せで給付されます。これにより、育児休業給付金と合わせて給付率が80%(手取り額の10割相当)へと引き上げられることとなります。
支給対象となる要件
出生後休業支援給付金は、子が生まれてから一定期間内に被保険者と配偶者のどちらもが14日以上の育児休業を取得することが要件となっています。この一定期間は男女で異なっており、詳細は以下の通りです。
・男性:子の出生後8週間以内
・女性:産後休業後8週間以内
支給されるのは最大28日間で、休業開始前賃金の13%相当額が育児休業給付金に上乗せされる仕組みです。
ただし、配偶者が専業主婦(夫)や自営業者の場合や、ひとり親家庭の場合は、本人の育休取得のみで出生後休業支援給付金を受け取ることができます。この点は、本記事内の「出生後休業支援給付の注意点」で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。
支給申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請手続きは、定められた日までに事業所の所在地を管轄するハローワークへ必要書類を提出します。この提出期限は、手続きの内容によって異なります。
|
・受給資格確認手続きのみ実施する場合:初回の支給申請をおこなう日まで |
また、提出する書類は以下の通りです。
|
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 |
出生後休業支援給付金が不支給となる条件

出生後休業支援給付金は、以下の条件に当てはまると支給が認められないケースがあります。
・育児休業期間中に一定以上の賃金が支払われた
・出生後休業支援給付金の申請期限を過ぎた
・雇用保険に未加入だった
・育児休業の要件を満たしていない
それぞれ詳しく確認していきましょう。
育児休業期間中に一定以上の賃金が支払われた
育児休業期間中であっても、労使の話し合いのもとの合意があれば一時的に就労することができます。その場合は賃金が支払われることになりますが、賃金月額の80%以上の賃金が支払われた場合は育児休業給付金が給付されません。
出生後休業支援給付金は育児休業給付金に上乗せして給付されるものですので、育児休業給付金が支給されなければ出生後休業支援給付金も支給されないことになります。
また、賃金が80%未満の場合も、給付金が減額支給となるため注意が必要です。
出生後休業支援給付金の申請期限を過ぎた
前述の通り、出生後休業支援給付金の支給申請には、場合によって異なる期限が定められています。この期限を過ぎた場合は申請が認められない恐れがありますので、必ず期限内に所轄のハローワークへ申請手続きをおこないましょう。
なお、申請手続きをおこなうのは原則事業主ですが、提出する書類の中には母子手帳など従業員から提出してもらうものもあります。期限内に申請手続きがおこなえるよう、必要書類の提出を従業員へ事前に呼びかけて早めの準備を進めておきましょう。
雇用保険に未加入だった
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者を対象とした制度です。そのため、自営業者やフリーランス、雇用保険に未加入のパート・アルバイトなどは給付の対象外となります。
育児休業の要件を満たしていない
前述の通り、出生後休業支援給付金は対象となる期間や休業日数などが定められています。
|
対象となる期間 |
・男性:子の出生後8週間以内 |
|
対象となる休業日数 |
14日以上の育児休業 |
対象となる期間を過ぎてから育児休業を取得した場合や、14日未満の育児休業などは支給の対象となりません。
また、出生後休業支援給付金は原則、被保険者とその配偶者の両方が育児休業を取得することを対象としています。
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、本人の育休取得のみで支給が認められるケースがあります。次の章でくわしく確認していきましょう。
出生後休業支援給付金を「本人のみの育休取得」で受給できるケース

出生後休業支援給付金は、原則両親ともに育児休業を取得することを支給条件としています。ただし、以下の条件に当てはまる場合は本人が育休を取得することで支給対象となります。
・配偶者が専業主婦(夫)の場合
・配偶者が自営業の場合
・ひとり親家庭の場合
それぞれくわしく解説していきましょう。
配偶者が専業主婦(夫)の場合
配偶者が専業主婦(夫)の場合、本人の育休取得のみで出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。その場合、以下の書類を添付して提出する必要があります。
・支給対象者の配偶者であることを確認できるもの(世帯全員が記載された住民票の写しなど)
・収入がないことを確認できるもの(配偶者の直近の課税証明書、受給資格者証の写し)
なお、課税証明書に給与収入が記載されている場合は、事業主が発行した退職証明書の写しの提出も必要です。
配偶者が自営業の場合
配偶者が自営業者やフリーランスの場合も、本人の育休取得のみで出生後休業支援給付金の支給を受けられます。その場合、以下の書類の提出を求められます。
・支給対象者の配偶者であることを確認できるもの(世帯全員が記載された住民票の写しなど)
・事業所得があり、給与所得を得ていないことを確認できるもの(配偶者の直近の課税証明書)
なお、課税証明書に給与所得が記載されている場合、事業主が発行した退職証明書の写しの提出も必要です。その給与所得が役員報酬によるものである場合は、役員名簿なども併せて提出してください。
ひとり親の場合
配偶者がいないひとり親世帯も、出生後休業支援給付金の対象となります。その場合、以下の書類を添付書類として提出する必要があります。
・戸籍謄(抄)本
・世帯全員について記載された住民票の写し
上記以外に、ひとり親を対象とした公的制度の利用が確認できる書類の提出でも対応可能です。具体的には「遺族基礎年金の国民年金証書」「児童扶養手当の受給を証明する書類」「母子家庭に対する手当てや助成制度を受給していることが分かる書類」などが該当します。
出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金の違い

令和6年雇用保険制度改正では、出生後休業支援給付金のほかに「育児時短就業給付金」も新たに施行されます。ここからは、育児時短就業給付金の制度概要や支給要件について学んでいきましょう。
育児時短就業給付金とは
育児時短就業給付金とは、育児中に柔軟な働き方を選択できるように支援する制度です。2歳に満たない子を養育するために時短勤務で就業し、時短勤務以前の賃金に比べて低下した場合に給付金が支給されます。
育児休業が明けた後でも「子どもの保育園の送迎が必要」「子どもの体調不良で急な対応が求められる」といった理由から、時短勤務を選ぶ人も少なくありません。しかし、勤務時間が短くなることでフルタイム勤務時に比べて賃金が低下することもあり、経済的に不安を抱える人も多く見られます。
そこで、育児時短就業給付金は、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給し、時短勤務によって減少した賃金をカバーする目的があります。
ただし、時短勤務を始めるときの賃金水準を超えないように調整が行われる仕組みで、時短勤務以前の賃金を超える金額を受け取ることはできません。
支給対象となる要件
育児時短就業給付金の支給対象となるのは、以下の要件を満たす人です。
・2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
・育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること
ただし、以下に該当する場合は支給が受けられません。
・時短勤務で賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて減少していないとき
・時短勤務で支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
・育児時短就業給付金の支給額が最低限度額以下であるとき
なお、2025年7月31日までの育児時短就業給付金の支給限度額は45万9,000円、最低限度額は2,295円です。これらの限度額は毎年8月1日に見直しが行われます。
出生後休業支援給付金に関する企業側のメリット

出生後休業支援給付金の制度は、企業側にとって以下のようなメリットがあります。
・従業員の育休取得促進
・企業イメージの向上
・採用活動へのプラス効果
それぞれくわしく解説していきましょう。
従業員の育休取得促進
育児休業の取得中は育児休業給付金の支給を受けられますが、手取り額の8割程度の支給となるため、育休前に比べて収入が減少することが避けられませんでした。そのため、特に主な生計者が育児休業を取得することに経済的な不安を感じ、「育休を取得したいけれど、家計のことを考えると難しい」という人も多く見られていました。
しかし、出生後休業支援給付金を育児休業給付金に上乗せして支払うことができれば、育休取得者は手取り額の10割を受け取ることができ、収入が減少する不安なく育児休業を取得できるようになります。
従業員が育休を取得しやすくなることは、企業にとって人材の確保や離職率の低下を防ぐメリットがあります。育児休業が取得しやすい環境が整うことで、従業員の満足度が向上し、誰もが働きやすい職場環境の構築に繋がるでしょう。
企業イメージの向上
共働きが進む現在、従業員が育児休業を取りやすい環境を整えることは、企業の果たすべき社会的責任のひとつともいえます。出生後休業支援給付金の施行により育児休業取得が定着すれば、従業員のライフステージに配慮した柔軟な働き方を推進していると見なされて「きちんと社会的責任を果たしている企業だ」と評価されることが期待できます。
こうした企業イメージの向上は、企業ブランドの強化や競争力の向上にもつながり、結果的に企業の価値を向上させる重要な要素にもなるといえるでしょう。
採用活動へのプラス効果
出生後休業支援給付金によって育児休業取得が定着すると、企業の採用活動にもプラスの効果が期待できます。
最近では、共働きの広がりによって「育児休業を取得しやすいか」という点を重視している求職者も珍しくありません。ライフスタイルに柔軟に対応できる企業を求める声も多く見られます。育児休業を取得できる環境が整っている企業は、そうした求職者にとって魅力的に映るでしょう。
実際に厚生労働省が行った「令和5年度 男性の育児休業等取得率の公表状況調査」によると、育休取得率を公表している企業が感じた変化として「新卒・中途採用応募人材の増加」が挙げられています。
この調査結果からも、従業員の育休取得に積極的に取り組んでいる企業は、人材確保の面でも優位性を保ちやすいといえるでしょう。
出生後休業支援給付金の企業側のデメリット・課題

さまざまなメリットがある出生後休業支援給付金の制度ですが、一方で以下のようなデメリットや課題もあります。
・実務上の負担が増える
・制度理解の促進が必要
それぞれくわしく解説していきましょう。
実務上の負担が増える
出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、従業員を雇用する事業主が申請手続きをおこなう必要があり、総務・人事担当者の業務負担が増加する懸念があります。新設された制度のため、申請フローや事務手順が社内で十分に定着するまでは手続きに時間がかかり、スムーズに進めることが難しいケースもあるかもしれません。
また、出生後休業支援給付制度によって育児休業中の手取り額が増加することから、これまでに比べて育児休業を取得する従業員が増加することも考えられます。人手が限られる中で業務負担が増加する点については、あらかじめ「申請フローに関する勉強会をおこなう」「他の業務の効率化に取り組む」などの対策を考えておく必要があるでしょう。
制度理解の促進が必要
出生後休業支援給付金について、育児休業を取得する従業員や総務・人事担当者にもまだあまり浸透していない可能性があります。もし申請期限までに必要な手続きが取られなければ、育児休業を取得している従業員が十分な給付金を受けられない可能性もあります。
よって、従業員が安心して給付金の支給を受けられるよう、社内で制度に対する理解を深め、適切なサポート体制を整えておく必要があります。
特に、支給申請手続きをおこなう総務・人事担当者には、制度概要や支給申請に関する研修を実施することが有効です。
さらに、これから育児休業を取得する可能性のある従業員にも制度を周知するなど、積極的に情報提供をおこなうようにしましょう。
出生後休業支援給付金で企業がおこなう対応

従業員が出生後休業支援給付金の支給を受けるにあたって、企業側ではいくつかの対応を取る必要があります。くわしく確認していきましょう。
企業に必要な対応
出生後休業支援給付金は、原則両親ともに育児休業を取得する場合に支給されます。従来、育児休業は女性の取得が多かったものの、出生後休業支援給付金の支給要件を満たすためには男性も育児休業を取得する必要があります。
ただし、男性の育児休業の取得率を上げるためには、誰もが平等に育児休業を取りやすい雰囲気を作ることや、周囲の理解を得ることが欠かせません。
したがって企業は、性別にかかわらず育児休業を取得しやすい環境を整備することが求められます。特に、男性従業員が育児休業を取得する際、職場で遠慮や負担を感じることがないように制度の周知を徹底し、管理職を含む社内全体で理解を深めることが重要です。
時短勤務者への対応
2025年4月からは出生後休業給付金と併せて、時短就業給付金の制度も施行されます。時短就業給付金は、時短勤務によって減少した賃金をカバーするための給付金です。
企業は育児休業取得の後押しと併せて、時短勤務を利用できる環境整備にも努める必要があります。
特に、時短勤務者は「周囲に迷惑をかけるのが申し訳ない」「キャリアが停滞しそうで不安」などと感じることが少なくありません。企業は従業員がこうした不安を抱くことがないよう、業務分担を見直したり、効率化に取り組んだりすることが大切です。
また従業員のキャリア形成についても、評価制度の見直しやスキルアップのサポートなどが必要だといえるでしょう。
まとめ
2025年4月より施行される出生後休業支援給付金は、育休中の収入減をカバーする制度です。育児休業給付金と合わせて受給することで、手取り額10割を受け取れることとなり、経済的な不安を和らげながら育児休業を取得することができます。
従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整えることは、人材の確保や従業員の離職防止にもつながります。ぜひ女性だけでなく男性も気軽に育児休業を取得できる環境を整備していきましょう。
<ライタープロフィール>
椿 慧理
フリーライター。新卒後に入行した銀行で10年間勤務し、個人・法人営業として金融商品の提案・販売を務める。現在は銀行で培った多様な経験を活かし、金融・人材ライターとして幅広く活動中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者資格を保有(編集:株式会社となりの編プロ)