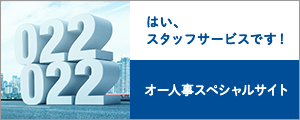定年後の再雇用制度とは?導入メリット・手続き・注意点を解説

再雇用制度とは、定年を迎えた従業員が一度退職したうえで、改めて企業と雇用契約を結び直し、引き続き就業できる制度のことです。2025年4月の法改正により、65歳までの全希望者を対象とした継続雇用が義務化され、企業にはより実務的かつ丁寧な制度運用が求められるようになりました。
労働人口が減少する中で、企業にとって経験豊富なシニア人材をどのように活用していくかが、持続可能な経営の大きな鍵となっています。特に定年後も働き続けたいと希望する高年齢者の増加により、「再雇用制度」への注目が一層高まっているのが現状です。
本記事では、再雇用制度の基本から法的な背景、導入メリットと注意点、手続きの流れまで、企業担当者として押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
再雇用制度とは

再雇用制度とは、企業で定年を迎えた従業員が一度退職した後、改めて同じ企業や子会社などと雇用契約を結び、引き続き働くことができる制度です。定年制を採用している企業においては、高年齢者の雇用機会を確保する手段のひとつとして広く導入されています。
かつては、再雇用にあたって企業が一定の基準(勤務成績や健康状態など)を設けることが認められていましたが、2025年4月の法改正により、65歳までの雇用確保措置として「希望者全員を対象とする再雇用」が義務化されています。そのため、企業は原則として再雇用を希望するすべての従業員に対し、雇用機会を提供しなければなりません。なお、再雇用先は同一企業に限らず、子会社や関連会社などでの雇用継続も可能ですが、その際は本人の同意を得たうえでの対応が求められます。
高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度」の一種
高年齢者雇用安定法とは
再雇用制度は、「高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)」に基づき導入されるものです。この法律は、少子高齢化による労働力不足への対応策として、65歳までの安定的な雇用機会の確保を目的に制定された法律です。近年は70歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正も加えられ、企業の対応がより重要視されるようになりました。
企業は高齢者雇用確保措置のいずれかの対応が義務
企業には、以下のいずれかの「高年齢者雇用確保措置」を講じることが義務づけられています。
1. 定年制の廃止
2. 定年年齢の引上げ
3. 継続雇用制度の導入(再雇用制度または勤務延長制度)
このうち、多くの企業で柔軟な運用が可能な再雇用制度を選択しており、厚生労働省の最新の調査では次のような傾向が示されています。
令和6年「高年齢者雇用状況等報告書」によると、高年齢者雇用確保措置を講じている企業のうち、「継続雇用制度の導入」が67.4%と最も多く、「定年の引上げ(28.7%)」「定年制の廃止(3.9%)」を大きく上回っています。
【参考】厚生労働省|令和6年「高年齢者雇用状況等報告」集計結果
「勤務延長制度」との違い
再雇用制度と似た制度に「勤務延長制度」がありますが、両者には明確な違いがあります。
再雇用制度は、定年退職を一度経たうえで、改めて新たな労働契約を締結するものです。そのため雇用関係は一旦終了し、労働条件や雇用形態、給与などは新たな契約内容に基づいて再設定されます。
一方、勤務延長制度は、定年を迎えても退職扱いにはしないのが一般的です。現行の雇用契約を延長して勤務を継続する方式のため、「退職→再雇用」ではなく、「契約の延長」という位置づけになります。
企業としてどちらを選択するかは、就業規則の整備状況や労使協議の内容に応じて検討する必要があるでしょう。
高年齢者雇用安定法の主な改正点
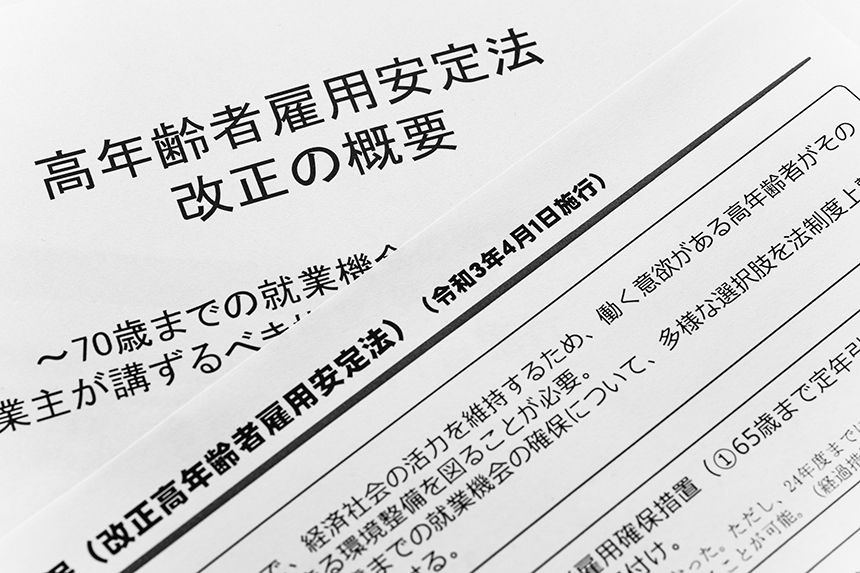
高年齢者雇用安定法は、少子高齢化や年金支給年齢の引上げなど社会状況の変化にあわせて、段階的に見直しがおこなわれてきました。ここでは、企業の対応に大きな影響を与えた主要な改正内容を確認しまう。
2013年の改正:希望者全員を対象とした雇用確保が義務化
2013年(平成25年)の改正では、企業に対し「65歳までの雇用確保措置」を講じることが義務化されています。それまでは、再雇用の対象者について一定の基準を設けることも可能とされていましたが、改正により「基準に基づく選別」が原則としてできなくなり、「希望者全員を対象とする再雇用制度等の整備」が求められました。この改正を機に、社会的に再雇用制度の整備を進める流れが加速します。
2021年の改正:70歳までの就業確保措置が努力義務に
2021年(令和3年)4月の改正では、70歳までの就業機会を確保するための措置が企業の努力義務として新設されています。具体的には、以下のいずれかの対応を「努力義務」として講じることが求められました。
1. 70歳までの定年の引上げ
2. 70歳までの継続雇用制度の導入(再雇用・勤務延長)
3. 他の企業への再就職の実現
4. 業務委託契約による就業機会の提供
5. 社会貢献事業等への従事機会の確保
この改正は、従来の単なる雇用確保から、「多様な働き方の選択肢の提供」へと企業の対応を拡張するものであり、就業機会の柔軟化が進むきっかけとなりました。
【参考】:厚生労働省|高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
再雇用制度の導入の企業側メリット

再雇用制度は、企業側にとっても多くのメリットがあります。ここでは、主なメリットを5つの視点から解説します。
1. 従業員が長年培ってきた経験・スキル・人脈を活かせる
2. 若手社員への技術やノウハウの安定的な継承
3. 新規採用・育成にかかるコストの削減
4. 他の従業員の安心感やモチベーション向上につながる可能性
5. 助成金制度の活用による経済的支援
1. 従業員が長年培ってきた経験・スキル・人脈を活かせる
再雇用により、長年企業に貢献してきた従業員の豊富な業務経験や専門スキル、社内外の人脈を引き続き活用できます。とくに、属人化しやすい業務やクライアント対応など、継続的な関係性が求められる業務においては、シニア社員の経験は大きな戦力となります。
2. 若手社員への技術やノウハウの安定的な継承
現場の実務に精通したベテラン社員を再雇用することで、若手社員へのOJT(On-the-Job Training)や技術伝承がスムーズになります。教える側にとっても、定年後の働き方として「指導役」や「後進育成」を意識することで、役割の明確化とやりがいの創出にもつながります。
3. 新規採用・育成にかかるコストの削減
人材の新規採用には、求人費用や選考・面接対応、採用担当者の工数、入社後の研修や教育コストなど、さまざまな時間的・経済的な負担が発生します。再雇用であれば、すでに自社文化や業務内容に精通しているため、採用・育成にかかる初期コストを大幅に抑えることが可能です。
4. 他の従業員の安心感やモチベーション向上につながる可能性
定年後も働ける制度があることは、現役世代の従業員にとっても将来への安心感を与えます。長く働き続けられる環境は、エンゲージメントやロイヤルティの向上にも寄与するといえるでしょう。
また、年齢や世代を超えた人材が共に働くことで、多様な価値観の導入による組織風土の活性化も期待できます。ベテランと若手が刺激を与え合うことで、社内コミュニケーションの幅も広がります。
5. 助成金制度の活用による経済的支援
再雇用制度を導入・運用するにあたり、一定の条件を満たせば国の助成金が活用できる場合があります。例えば、定年後の継続雇用を促進する取り組みに対して支給される「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コースなど)」があげられます。これらの制度を上手く活用することで、再雇用にかかる人件費や制度整備のコストを一部補うことが可能です。
【参考】:厚生労働省|65歳超雇用推進助成金
再雇用制度の導入の企業側の課題・注意点

再雇用制度の導入・運用には、企業として配慮すべき点や運用上の課題も存在します。以下で、特に注意が必要なポイントを整理していきましょう。
1. 労働条件の変更により従業員のモチベーション低下の可能性
再雇用後は、有期契約や時短勤務など、現役時代と比較して異なる労働条件での雇用契約となるケースが多いです。特に、賃金の大幅な減額や役職・業務内容の変更がある場合、本人のやる気や仕事への姿勢に影響を及ぼすことがあります。
再雇用制度の設計にあたっては、職務の内容と報酬のバランスを丁寧に説明し、合理的かつ納得感のある条件提示を意識することが非常に重要です。
2. 他の従業員と待遇面の不均衡が生じないよう配慮が必要
再雇用制度を導入する際には、現役世代の従業員との間に生じる待遇差に対する配慮も欠かせません。例えば、再雇用者が比較的軽い業務であるにもかかわらず一定の給与や柔軟な働き方を認められている場合、現役社員から「優遇されている」と受け取られてしまうケースが想定されます。
このような不公平感は、職場全体のモチベーションやチームワークに影響を与えることもあるため、再雇用者の待遇の妥当性や背景について、社内での情報共有や説明責任を果たすことが大切です。
特に、同一労働同一賃金の観点からも、業務内容や責任の程度に見合った待遇であるかという客観性が求められます。現役世代とのバランスを考慮しながら、再雇用者の待遇を合理的に設定し、理由も明確にすることがポイントです。
再雇用制度の導入・運用の手続きと注意点
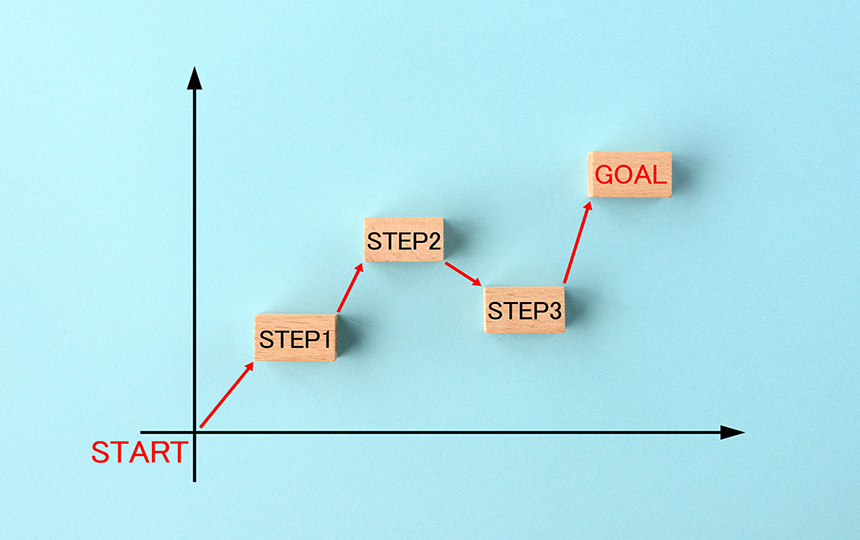
本章では、定年後の再雇用に至るまでの流れと、契約締結時の留意点を解説します。
1. 定年後の再雇用までの主な流れ
再雇用は退職後に「再契約」という手続きになるため、段階的な対応が必要です。企業と従業員が互いに納得した上で再雇用を進めるため、以下のステップを丁寧に進めましょう。
1. 再雇用の対象となる従業員本人の継続勤務の意思を確認任
定年を迎える前に、本人に対して継続勤務の希望の有無を事前に確認します。確認のタイミングとしては、定年前の面談や書面での意向確認が一般的です。
2. 再雇用後の労働条件の説明
本人の意思を確認後、再雇用の場合の労働条件(職務内容・勤務時間・給与・休日など)について具体的に説明をおこないます。条件の見直しがある際は、その理由や背景も合わせて説明し、納得を得られるように配慮しましょう。
3. 労働条件に合意のうえ退職手続きをおこなう
再雇用制度は一度退職した後に再度雇用契約を結ぶため、定年退職の手続きは形式上必要です。従業員が退職に同意し、その後の再雇用契約に進むという流れになります。
4. 再度雇用契約を締結
定年退職後に、改めて企業と労働契約を締結します。この契約は通常、有期雇用契約となるケースが多く、雇用期間や更新条件、就業規則の適用なども明示する必要があります。
契約時に注意すべきポイント
再雇用における契約は、一般の新規雇用とは異なる側面もあるため、慎重な取り扱いが求められます。
労働条件は書面で明確に提示する
再雇用契約では、雇用形態(有期契約社員・嘱託等)、契約期間、更新の有無、賃金、労働時間等の条件を必ず書面で提示します。特に、有期契約に関しては更新上限や無期転換ルールにも配慮が必要です。
契約条件が曖昧なままでは、後のトラブルにつながる可能性があるため、書面での明示と本人の署名・押印の取得が基本となります。
再雇用制度に関する就業規則の作成・従業員への周知
再雇用制度を制度化する場合は、就業規則や再雇用規程に内容を明記し、従業員に周知する必要があります。就業規則には、対象年齢、契約期間、勤務条件、更新可否、退職後の申請手続きなどを明示しておくと、トラブルを防止に効果的です。
周知は掲示・配布・イントラネット上での公開など、確実に内容を把握できる形でおこないましょう。
再雇用後の職務内容・責任範囲・勤務時間等の具体化
再雇用された従業員に対し、担当業務、責任の範囲、勤務時間といった点を事前に明確化しておきましょう。特に、現役時代との業務の違いや責任軽減がある場合は、その旨も具体的に説明するとベターです。再雇用者本人の不安を軽減し、配属先部署との調整も円滑になります。
再雇用後の給与・年金・社会保険について

再雇用制度を導入する際は、雇用契約や業務内容だけでなく、給与水準の設定や、年金・社会保険の取り扱いについても適切に整備・説明する必要があります。ここでは企業側が押さえておきたい実務対応のポイントを解説していきます。
再雇用後の給与設定
再雇用後は、定年前とは異なる労働条件となることが多いため、それに伴い給与水準も見直されます。ただし、給与を一律に引き下げることはできず、以下のような点に留意が必要です。
同一労働同一賃金の原則が適用される
業務内容や責任の程度が現役社員と同程度である場合、賃金差を設ける際には合理的な説明が求められます。再雇用後に業務内容が軽減される場合でも、その内容に応じた設定と説明が必要です。
h4: 給与減額には合理的な理由が必要
再雇用後の給与が減額される場合、その理由が職務の変更や責任の範囲縮小などとの整合性が必要です。個別の説明や合意が不十分なままの減額は、後のトラブルにつながりかねません。
減額の目安は「定年前の60%~70%程度」
再雇用後の賃金は定年時の6~7割程度を目安とした運用が多いようです。ただし、業務内容や勤務日数の実態に即した制度設計が前提です。
再雇用制度に関する年金の手続き
定年退職後に再雇用される従業員が厚生年金の受給資格を有している場合、再雇用後の給与水準によっては在職老齢年金の調整が発生する可能性があります。
企業側が年金の申請手続きを代行する義務はありませんが、以下のような実務対応・配慮が求められるでしょう。
再雇用後の給与水準を説明する際に、在職老齢年金への影響についても案内
在職老齢年金制度では、賃金と年金額の合計が一定額を超えると、年金が一部または全額支給停止となる可能性があります。令和7年度の支給停止調整額は51万円となっており、基本月額(老齢厚生年金の月額(加給年金を除く))と総報酬月額相当額の合計が51万円を超えた場合、年金額の調整が入ります。年金を受給している再雇用者に対しては、事前に制度概要を説明しておくとトラブル防止に役立ちます。
※支給停止調整額は年度によって改定されます。最新の情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
社内通知や面談で、年金に関する相談先(年金事務所など)を周知
企業に相談されるケースが多いため、あらかじめ外部相談窓口を案内しておくと安心です。企業としては、制度の案内と理解促進を目的とした対応に留めつつ、本人の判断・手続きに委ねることが原則です。
社会保険の手続き
定年退職後に再雇用する場合、形式上は一度退職してからの再雇用となるため、社会保険の手続きも一旦喪失手続きをしてから再取得という流れになります。実務的に注意すべきポイントを以下に整理します。
再雇用時に社会保険を取得する手続きが必要
再雇用制度では、退職日と再雇用開始日が同日になるケースが一般的です。この場合、健康保険・厚生年金保険について、「同日得喪(どうじつとくそう)」という処理が必要です。
この際、手続き漏れや届出遅延があると、資格取得日にずれが生じ、保険料計算や給付に支障が生じる可能性があります。人事・総務部門では、退職日と再雇用契約開始日が同日になることを前提に、あらかじめ社内フローやチェックリストを整備しておくことが重要です。
<同日得喪とは>
同一日付での保険資格喪失と再取得を行う処理を指します。例えば、3月31日付で定年退職し、1日も空けずに再雇用契約を結ぶ場合、4月1日付で喪失手続きをし、同日付で再取得となります。(社会保険の資格喪失は、退職日の翌日となるため)
65歳以降も社会保険の加入対象となる場合
再雇用の対象者が65歳以上である場合でも、一定の条件(週所定労働時間が一般社員の4分の3以上など)を満たせば、引き続き厚生年金保険の加入対象となります。この場合、保険料の負担は現役時と同様に、企業と本人で折半されます。
なお、厚生年金には加入年齢の上限がないため、70歳になるまでの間は原則として加入対象です。ただし、70歳に達した時点(誕生日の前日)で被保険者資格は自動的に喪失するため、該当時には資格喪失届の提出と、その後の報酬情報の届出(70歳以上被用者報酬月額届)が必要となります。
健康保険については、75歳未満であれば引き続き被保険者として加入が可能です。(75歳以上になると後期高齢者医療制度に切り替わり、健康保険は脱退)
定年後の再雇用では、制度的に例外処理や特有の規定が多いため、より専門的な知識が求められます。
再雇用制度に関するよくある質問

再雇用制度の導入・運用にあたり、企業として押さえておくべき基本的な疑問をQ&A形式で見ていきましょう。
Q1:再雇用制度は義務ですか?
A:一定の年齢に達した従業員に対して、再雇用制度を含む雇用確保措置を講じることは企業にとって法的義務です。
高年齢者雇用安定法により、企業は以下のいずれかの高齢者雇用確保措置を講じることが義務づけられています。
1. 定年制の廃止
2. 定年年齢の引上げ
3. 継続雇用制度の導入(再雇用制度または勤務延長制度)
このうち再雇用制度は、継続雇用制度の一形態であり、多くの企業が現実的な選択肢として導入しています。特に2025年4月の改正により、「希望者全員を対象とする再雇用」が義務化され、企業による任意の選別は原則として認められなくなりました。
Q2:再雇用を拒否することはできますか?
A:基本的に、企業側から再雇用を拒否することはできません。
高年齢者雇用安定法第9条第3項に基づいて策定された「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」では、継続雇用をおこなわないことが認められるケースが明記されていますが、その内容は非常に限定的です。
例えば、次のような場合が該当するとされています。
● 著しい非違行為(懲戒に相当する重大な問題行動)がある場合
● 明らかに職務遂行が困難な健康状態である場合
これらは、労働契約法第16条における「解雇の合理性・相当性」基準と同程度の厳格な条件が求められるものであり、企業側の一方的な判断による再雇用拒否は基本的に認められません。実務上のポイントとして、継続雇用を見送る判断をする場合には、十分な客観的理由と説明責任を果たすことが求められます。事前に就業規則や再雇用基準の整備、文書での記録化を徹底しましょう。
まとめ
再雇用制度は、定年を迎えた従業員の豊富な経験や技術を引き続き活用できる有効な手段であり、人材確保や若手育成にもつながる重要な制度です。特に2025年の法改正により、希望者全員を対象とした再雇用が義務化され、企業にはより慎重かつ実務的な対応が求められることとなりました。制度導入にあたっては、就業規則の整備や労働条件の明示、社会保険・年金の正確な手続きが不可欠です。なお、再雇用制度だけでなく、即戦力となる派遣人材を活用することも、必要な人材を柔軟に確保する手段のひとつです。参考に以下のリンクもご覧ください。自社の状況にあわせて、最適な人材活用のあり方を検討していきましょう。
スタッフサービスグループ|人材をお探しの企業様へ
<執筆監修者プロフィール>
川西 菜都美(監修兼ライター)
結喜社会保険労務士事務所代表。お母さんと子どものための社会保険労務士。自身の経験から、子育てと仕事の両立に悩む女性の相談にもあたっている。金融、製造、小売業などさまざまな業界を渡り歩いた経験を活かして、クライアントごとのニーズにあわせたきめ細やかな対応を心がけている。