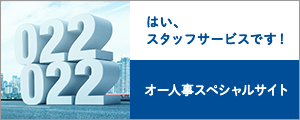建設業への派遣は原則禁止!適用除外業務と活用のポイントを解説

建設業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。特に高齢化による技能労働者の減少や若年層の入職者不足も影響し、現場の人材確保が難しくなっているのが現状です。また、2024年4月から時間外労働の上限規制が施行されたことで、より一層労働力の確保が急がれています。このような人材不足解消の一手として、派遣という選択肢に注目が集まっていますが、建設業には派遣が禁止されている業務もあるため注意が必要です。本記事では、建設業における派遣のポイントをわかりやすく解説します。
目次
建設業における人材不足の現状と課題

建設業界の人材不足は年々深刻化しています。国土交通省の調査でも、労働者の高齢化と若年層の減少が指摘されており、さらに2024年4月から時間外労働の上限規制が施行されたことで、より一層の労働力確保が求められる状況になっています。本節では、人材不足の実態と採用活動における具体的な課題について掘り下げます。
建設業界における人材不足の深刻化
建設業界では、慢性的な人材不足が深刻化しています。国土交通省の調査によると、高齢化の進行と若年層の入職者不足が主な原因となっており、現場作業を担う技能労働者の減少が顕著ということがわかります。
この人手不足は、単なる少子高齢化というだけでなく、昨年4月より施工された時間外労働の上限規制(いわゆる「2024年問題」)や近年の建設需要の増加によってさらに加速しています。公共工事やインフラ整備、都市再開発プロジェクトの拡大等により、現場の人材ニーズに労働力の供給が追いついていないのが現状です。
参考:国土交通省|建設労働需給調査結果(令和6年12月調査)
採用活動の課題
特に建設業の採用活動においては、以下の点が課題となっています。
1. 求職者の確保が困難
建設業界は他業種と比較して労働環境が厳しいと言われることが多く、求職者が集まりにくい状況です。
求人広告を出しても応募が集まりにくいことから採用活動が長期化し、採用コストが高騰する傾向にあります。
2. 定着率の低さ
建設業では、技能の習得に一定の時間がかかる職種も少なくありません。未経験者がすぐに即戦力になるのは難しい環境です。しかし、採用しても労働環境や体力的な負担になじめずに短期間で退職するケースも珍しくなく、定着率の低さが課題となっています。
3. 採用競争の激化
2024年問題も影響し、人材不足は建設業界以外でも重要なテーマとなっています。2024年問題とは、働き方改革関連法案により時間外労働の上限規制が適用されることで、人手不足がさらに深刻化するとされている課題です。建設業界のほかにも物流・医療など様々な業界で、労働時間の短縮が求められています。そのため、他業界との採用競争という点でも、建設業の採用はますます厳しくなっていると言わざるをえません。
労働者派遣法における建設業への派遣の適用除外について

労働者派遣法において、建設業務は原則として派遣の対象外とされています。本章では、禁止の背景や派遣可能な職種について解説します。
建設業務への派遣は原則禁止
法律で定められた「建設業務」の定義
労働者派遣法では、「建設業務」について明確な定義が設けられています。具体的には、建設工事の施工に直接関わる業務を指しており、以下のような作業が含まれます。
● 建築・土木工事の現場作業
● 型枠工事、鉄筋工事、配管工事、塗装工事などの専門技術を要する業務
● 現場での作業員としての職務全般
これらについては、労働者派遣の利用が法律上禁止されており、派遣社員を活用することはできません。
参考:
厚生労働省・熊本労働局|労働者派遣法により、建設業務への労働者派遣は禁止されています。
厚生労働省|労働者派遣事業を行うことができない業務は・・・
禁止の理由
建設業務への派遣が禁止されている理由には、以下のような背景があります。
1. 安全管理の責任の明確化
建設業は、現場での安全管理が非常に重要な業種です。直接雇用された自社の社員であれば、企業側が直接管理しやすいですが、派遣労働者では指揮命令系統が複雑になり安全管理が徹底しにくくなるため、派遣を禁止しています。
2. 長期間の雇用安定の確保
建設業は長期的な技術習得が必要な職種が多く、短期間の雇用を前提とする派遣労働とはマッチしづらい場合もあります。労働者の雇用安定と技術の継承を考慮し、派遣ではなく直接雇用が推奨されているという一面があります。
3. 元請・下請関係の適正化
建設業界は、現場において元請企業と下請企業の関係が多層化しているケースが一般的です。そこに派遣労働者が加わると契約関係がさらに複雑化し、指揮命令系統や適正な労働環境の維持が難しくなることが理由の一つです。
派遣が可能な業務(適用除外業務)
ただし、建設業のすべての職種で派遣が禁止されているわけではありません。ここでは、例外を解説します。
施工管理業務
施工管理業務は、建設現場の安全管理や工程管理を担う職種であり、実際の工事作業ではありません。管理業務が中心となるため、派遣の適用除外となっています。
施工管理技士の資格を持つ派遣社員であれば、現場の監督や品質管理、工程の調整などを担当することが可能です。ただし、単なる現場作業員としての派遣は認められないため、業務範囲を明確にする必要があります。
CADオペレーター、BIM/CIMオペレーター
建築設計や土木設計に関わるCADオペレーターやBIM/CIMオペレーターも、派遣が可能な職種の一つです。これらの職種は、設計ソフトを用いた図面作成や3Dモデリングをおこなうため、直接的な建設作業には該当しないという理由で適用除外となっています。
特に、近年ではBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やCIM(コンストラクション・インフォメーション・モデリング)の導入が進んでおり、こうしたデジタル技術を活用できる人材の需要が高まってきています。
建設現場の事務業務
建設現場には、事務作業を担当するスタッフが必要です。工事書類の作成、データ入力、スケジュール管理、労務管理といった業務は、建設工事の直接的な施工には該当しないため、派遣が認められています。
特に、建設プロジェクトの規模が大きくなると、現場での事務業務の負担が増加するため、派遣社員を活用して事務作業を効率化する企業が珍しくありません。
その他(クレーンの運転や電気工事など)
建設業務の中には、特定の資格や高度な技術が必要な業務について、適用除外となっているものがあります。例えば、以下のような業務では、派遣労働者の活用が認められるケースがあります。
● クレーンの運転(クレーン運転士の資格を持つ者)
● 電気工事(電気工事士などの国家資格を保有する者)
● 設備保守・点検業務(専門技術を要する作業)
これらの業務は、専門資格を有することが前提となるため、単純作業員としての派遣は認められませんが、技術者としての派遣であれば可能とされています。
派遣社員活用のメリット
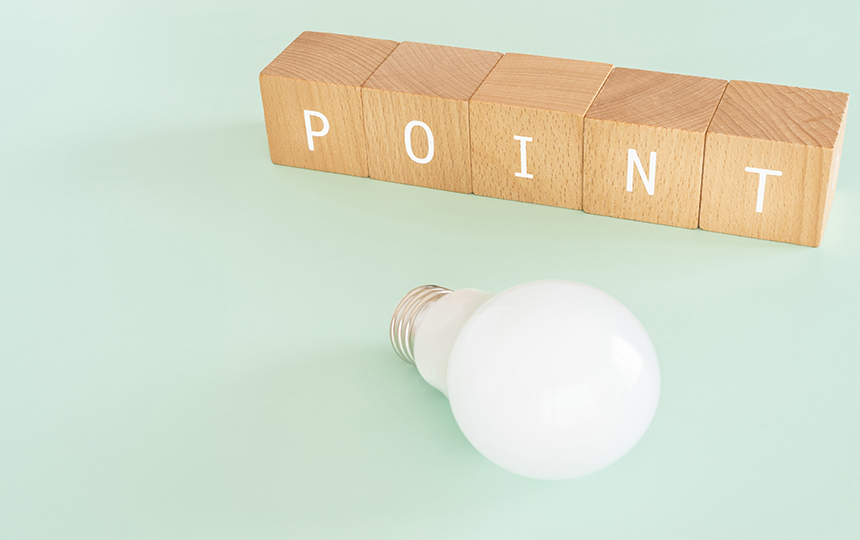
ここでは、建設業における派遣社員活用の主なメリットを3つの視点から解説します。
即戦力人材の確保
建設業界では、業務の専門性が高く、一定のスキルや経験を持つ人材が求められます。しかし、自社での採用活動で経験者からの応募がなかった場合は未経験者を採用せざるをえず、教育に時間を要してしまうケースも多いのが現状です。
派遣社員を活用すれば、一定の経験やスキルを持つ人材をスピーディーに確保できるため、即戦力として現場に配置することが可能です。派遣会社は登録者のスキルや経歴を把握しているため、自社のニーズに合った適切な人材を紹介してもらいやすいというメリットもあります。
採用コストの削減
前述のとおり、建設業界における採用活動は長期化するケースもあり、その場合は多くの時間と費用がかかります。派遣を活用することにより、求人広告費や採用担当者の負担、面接・選考の手間を軽減できます。
柔軟な人員調整
建設業の現場では、プロジェクトごとに必要な人員が変動することが多く、繁忙期と閑散期の差が激しいケースもあります。そのため、業務量に応じて柔軟に人材を確保できる仕組みが求められています。
派遣を活用することで、プロジェクト期間や繁忙期に合わせて必要な人数だけ人材を確保できるので、ニーズに応じて適正な労働力を確保できる点が魅力です。
建設業で派遣社員を活用する際の注意点

本章では、建設業で派遣社員を活用する際に注意すべきポイントを詳しく解説します。
適用除外業務の正確な把握
建設業務への派遣は原則禁止されていますが、これまで述べてきたように施工管理やCADオペレーターなど、一部の業務については適用除外として派遣が認められています。しかし、どの業務が派遣可能かは専門的な知識が求められ、判断が難しいケースも少なくありません。
判断に迷った場合は、以下の対応を検討しましょう。
● 労働局に相談する
労働基準監督署や各都道府県の労働局では、建設業における派遣の適用範囲について相談が可能です。事前に確認することで、違法派遣のリスクを回避できます。
● 社会保険労務士や弁護士などの専門家に確認する
労働諸法や派遣法に精通した専門家のアドバイスを受けることで、リスクを未然に防ぐことにつながります。
● 派遣会社と連携し業務範囲を明確にする
曖昧なまま契約を結ぶのではなく、「派遣社員が従事する業務内容」を明確にし、違法にならないよう確認をおこなうのもよいでしょう。
適用除外の範囲を誤ると労働者派遣法違反となる可能性があるため、慎重な確認が必要で
す。
派遣会社との連携
派遣社員を適切に活用するためには、派遣会社との円滑な連携が非常に重要になります。以下でポイントをおさえましょう。
派遣契約書の確認
建設業における派遣では、契約内容の厳密な確認が特に重要です。
以下に、確認しておくとよい具体的な内容をあげますので参考にしてみてください。
● 業務内容が適用除外業務に該当しているか
● 契約期間が適切か
● 指揮命令系統が明確になっているか
● 労働条件が適正に定められているか
また、定期的に派遣会社と契約内容を見直すことで、法改正や業務状況の変化に対応しやすくなります。
派遣社員への適切な指示・教育
派遣社員は直接雇用の社員とは異なり、指揮命令権の所在が重要なポイントとなります。特に建設業では、安全管理や業務の進め方に関する指導が必要になるため、以下の点を意識して対応することが重要です。
● 業務範囲を明確に伝える(適用除外業務以外の作業を指示しない)
● 安全衛生教育を実施する(建設現場での事故防止のため)
● 派遣元(派遣会社)と連携し、適切なフォローをおこなう
派遣社員を適切に管理することで、現場の安全性を確保し、労働環境のトラブルの防止につながります。
偽装請負への注意
建設業での派遣社員の活用において、特に注意すべきなのが偽装請負の問題です。偽装請負とは、本来「請負契約」であるべきところを、実態としては派遣契約に該当する形で運用しているケースを指します。
偽装請負のリスク
偽装請負とみなされた場合、企業は労働者派遣法違反による行政指導や是正勧告を受ける可能性があります。その他にも、違法派遣と判断され「労働契約申し込みみなし制度」が適用されると、違反企業が派遣社員を直接雇用する義務が生じるといったケースも想定されます。
また、例えば労災発生時に責任の所在が不明確になる等のリスクもあるため、偽装請負にならないように細心の注意を払いましょう。
参考:厚生労働省|派遣労働者、労働者派遣事業・請負事業に携わる皆さまへ 労働契約申込みみなし制度の概要
指揮命令関係の明確化
偽装請負とならないためには、派遣社員に対する指揮命令関係を明確にし、請負契約との違いを理解することが重要です。派遣契約をする上で以下のポイントを確認しましょう。
● 派遣社員への指示は、原則として派遣先(受け入れ企業)が直接おこなう
● 労働時間・業務内容は契約に沿ったものになっているかに留意する
● 派遣では、業務の進め方や休憩時間や勤務時間、休日の管理等は派遣先の企業が指示を出す
まとめ
建設業界では人材不足が深刻化しており、派遣社員の活用が有効な解決策となる場合があります。ただし、直接の工事作業といった建設業務への派遣は原則禁止であり、適用除外業務のみ認められているため注意が必要です。派遣を適切に活用することで、人材不足の解消や人材コストをおさえることができます。法令を遵守しながら、最適な人材活用を進めましょう。
<ライタープロフィール>
川西 菜都美(監修兼ライター)
結喜社会保険労務士事務所代表。お母さんと子どものための社労士。自身の経験から、子育てと仕事の両立に悩む女性の相談にもあたっている。金融、製造、小売業などさまざまな業界を渡り歩いた経験を活かして、クライアントごとのニーズにあわせたきめ細やかな対応を心がけている。