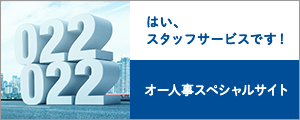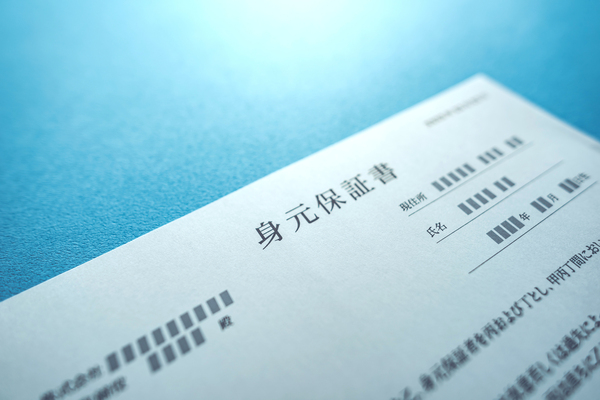
2025年施行「育児・介護休業法改正」企業が対応すべきポイントと注意点

「育児・介護休業法」は、男女問わず働く人々が仕事と育児・介護を両立しやすい環境を整え、会社からの離職者を防ぐための法律です。もともとは「育児休業法」でしたが、1995年10月1日に介護休業に関する規定が追加され「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」に変更されました。そして、2024年5月に「育児・介護休業法改正」が成立し、2025年4月より段階的に施行されます。本記事では、具体的な改正内容や、企業の効率的な進め方、その際の注意点などを解説します。
目次
育児・介護休業法とは
そもそも育児・介護休業法とは、どのような法律なのでしょうか。さらに今回改正に至った背景について紹介します。
育児・介護休業法の概要
育児介護休業法とは、育児や介護をおこなう従業員が仕事と家庭を両立できるように支援するための法律です。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う従業員の福祉に関する法律」といい、もともとは1991年5月に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)として制定されました。その後、1995年10月1日に介護休業に関する規定が追加され「育児・介護休業法」に変更。そして、2024年5月に「育児・介護休業法改正」が成立し、2025年4月より段階的に施行されることになりました。
育児・介護休業法改正の背景
日本では少子高齢化が進行し、労働力不足が深刻化しています。特に、中小企業では人材の確保と定着が大きな課題となっています。その課題を解消するためには、育児や介護との両立を支援する制度の充実が求められています。昨今においては、コロナ禍を契機に、多くの企業でテレワーク が導入され、働き方が多様化してきました。
また総務省の「令和4年就業構造基本調査 」(2023年)によると、「介護・看護」を理由に離職した人が約10万人にもおよびます。そこで政府は、企業に対し従業員が仕事を辞めずに働き続けられる環境づくりを促進するため、この法改正に至りました。
2025年 育児介護休業法改正のポイント
男女問わず従業員が育児や介護をしながら働き続けられる環境の整備を目的として、大幅な変更をおこないました。そのポイントは「育児と介護の両立支援の強化」「柔軟な働き方の実現」「育児休業取得促進と職場環境整備」の3点です。概要を解説します。
育児と介護の両立支援の強化
介護による離職防止のための相談窓口の設置や、早い段階での情報提供などの措置の義務化、子どもの看護休暇の拡大など、仕事と介護の両立支援を強化します。また、妊娠・出産などの申出時や、子どもが3歳になるまでの適切な時期に就業条件の見直しなどの個別の意向聴取もおこないます。
柔軟な働き方の実現の促進
働き方の選択肢を広げる施策を強化します。具体的には、3歳以上で小学校就学前の子どもを持つ従業員への柔軟な勤務制度の義務化(短時間勤務・テレワークの導入、時差出勤の拡充など)、残業免除の拡大 などをおこないます。
育児休業取得促進と職場環境整備
企業が従業員の育児休業取得を促し、復職後も働きやすい環境を整えるように、環境整備を強化していきます。例えば、育児休業取得状況の公表義務を従業員300人超の企業に拡大し、取得率向上を促進します。また、育休取得前後の個別相談や復職支援の徹底、育休取得を妨げない職場風土の醸成にも取り組めるように制度を整えます。
育児に関する主な改正点

まず育児に関する、詳細な改正点をチェックしましょう。
柔軟な働き方の拡充
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員においては、事業主(以下、企業)は次の5つのうち2つ以上の措置を選択しておこなう義務があります。一方、従業員はそのうち1つを選択して利用することができます。
・始業時刻等の変更
・月10日以上のテレワークなど
・新たな休暇の付与(年に10日)
・保育施設の設置運営
・短時間勤務制度
また企業が上記の措置を選ぶ時には、企業内の従業員の過半数を代表する組合などから意見を聴取する必要があります。
(2)個別周知・意向確認の義務化
3歳未満の子を育てる従業員に対して、子どもが3歳になる適切な時期において、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、(1)で選択した措置に関する内容の周知と、制度利用の意向の確認を個別におこなう義務があります。なお、従業員に利用を控えさせるような個別周知や意向確認は認められません。
|
周知時期
|
・従業員の子どもが3歳の誕生日を迎える1ヶ月前までの1年間 |
|
周知事項 |
1.企業が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 |
|
個別周知・ |
1面談 2書面交付 3FAX 4電子メールなど のいずれか |
なお、今紹介した(1)(2)の施策は2025年10月1日から施行される制度です。
残業免除の対象拡大
育児・介護休業法改正により、所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます。従来は「3歳未満の子を養育する従業員」が対象でしたが、改正後は「小学校就学前の子を養育する従業員」まで対象が広がります。
この改正により、より多くの子育て中の従業員が残業免除を申請できるようになり、仕事と育児の両立がより実現しやすくなってきます。なお、残業免除の請求に関しては、会社の事業運営に支障をきたす場合など、一定の条件下では適用を制限することもできます。※ この施策は2025年4月1日より施行される制度です。
子の看護等休暇の拡充
2025年4月1日より、「子の看護休暇」が『子の看護等休暇』へと名称変更になり、制度が拡充されます。まず対象となる子どもの範囲が、改正前は小学校就学前だったのが、改正後は小学校3年生まで拡大。より多くの育児中の従業員が休暇を取得しやすくなります。
また、これまではおもに子どもの病気やケガの看護のために取得できる制度でしたが、今回の改正により、感染症による学級閉鎖・休園などで子どもの世話が必要な場合も取得が可能です。さらに、子どもの入園式・卒園式などの学校行事にも利用できるようになりました。
なおこれまで「労使協定」により、継続雇用期間6ヶ月未満の従業員は「子の看護休暇」制度の対象から除外されていましたが、この仕組みも廃止されました。なお、週の所定労働日数が2日以下の従業員については、除外可能となります。
育児におけるテレワーク導入の促進
テレワークとは、自宅や外出先など、オフィス以外の場所で働く勤務スタイルのことです。企業には、2025年4月1日より「3歳未満の子どもを養育する従業員がテレワークを選択できる措置」を講じる努力義務が課されます。柔軟な働き方を後押しする施策の1つとして、今後企業には積極的な対応が求められます。
意向聴取と配慮の義務化
従業員が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たとき、または、子どもが3歳になる前の1年間の適切な時期に、企業は従業員の意向を個別に聴取することが義務づけられました。詳細な時期、聴取内容、聴取方法は次の通りです。
|
意向聴取の時期 |
(1)従業員が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出たとき |
|
聴取内容 |
1.勤務時間帯(始業および終業の時刻) |
|
意向聴取の方法 |
1面談 2書面交付 3FAX 4電子メールなど のいずれか |
先に紹介した、「柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務化」と比較すると、前者は従業員に対して柔軟な働き方を案内し、活用を促すことが目的です。一方、この「妊娠・出産の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取」は、従業員の具体的な希望を企業が聞き取り、可能な範囲でそのニーズに対応することが目的となります。この違いを理解した上で、従業員のニーズに対して、適切な施策をおこなうようにしましょう。
育児休業取得状況の公表義務拡大
2025年4月1日より、男性従業員の育児休業取得状況の公表義務が拡大されます。これまでは、常時雇用する従業員が1,000人を超える企業が対象でした。改正後は300人を超える企業が対象となります。公表内容は、次の2つのうちいずれかの割合を年1回、公表前事業年度の終了後のおおむね3ヶ月以内に、公表する必要があります。
1.育児休業等の取得割合
2.育児休業と育児目的休暇の取得率
公表場所は、インターネットで一般の人々が閲覧できる、自社ホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」が推奨されています。
次世代育成支援対策推進法の改正
次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法)とは、子どもを生み育てやすい環境を整えるために、企業や自治体が積極的に取り組むことを促す法律です。一定の基準を満たした企業には、子育てサポート企業として、次世代法に基づき、厚生労働大臣から「くるみん」「プラチナくるみん」の認定を受ける制度も運用しています。
2025年4月の改正では、常時雇用従業員数100人超の企業には、行動計画における育児休業取得状況や労働時間の状況を把握・分析し、具体的な数値目標を設定することが義務化されました。なお、常時雇用従業員数 100人以下の企業は、努力義務になっています。
さらに「くるみん認定」や、より高い水準の取り組みをおこなう企業への「プラチナくるみん認定」の基準が改正され、企業の取り組み状況に応じた認定がおこなわれます。この次世代法の有効期限が、2025年3月31日から2035年3月31日まで延長されています。
介護に関する主な改正点

介護においても、改正点がいくつかあります。ご紹介します。
介護休暇の取得要件緩和
介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。改正前は、介護休暇は半日単位でしか取得できませんでした。そのため短時間の介護や通院付き添いなどでも、半日分の休暇を取得する必要があり、柔軟な対応が難しい状況でした。2025年4月の改正からは時間単位での取得ができるので、従業員は必要な時間だけ介護休暇を取得できるようになり、仕事と介護の両立がしやすくなりました。企業側は、時間単位での休暇取得に対応するため、労働時間管理のシステムや方法の見直しが求められますが、それにより従業員の定着率の向上にもつながります。
介護におけるテレワーク導入の促進
2025年4月から、要介護の家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように、企業にそのための施策を求める努力義務が導入されます。法的な強制力はありませんが、企業が積極的にテレワーク環境を整備することで、従業員の離職防止やモチベーション向上につながり、生産性や企業イメージの向上にも貢献します。
両立支援制度の個別周知・意向確認の義務化
介護離職を防止するために、家族の介護が必要となった従業員と、介護に直面する可能性がある従業員に対して、適切な情報提供とサポートをおこなうことで、仕事と介護の両立を支援し、離職を防ぐことを目的としています。
(1)介護が必要な従業員への情報提供
従業員から介護に直面した旨の申し出を受けた場合、企業は介護休業制度などに関する、次の事項の周知と介護休業制度の取得、介護両立支援制度などの利用の意向確認を、個別におこなうことが義務化されます。
|
周知事項 |
(1)介護休業に関する制度、介護両立支援制度など(制度の内容) |
|
個別周知・意向確認の方法 |
1面談 2書面交付 3FAX 4電子メールなど のいずれか |
(2)40歳に達する従業員への情報提供
従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度(※)などの理解を深めるため、企業は介護休業制度などに関する次の事項について情報提供をすることが義務化されます。
|
情報提供期間 |
(1)従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) |
|
情報提供事項 |
1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) |
|
情報提供の方法 |
1面談 2書面交付 3FAX 4電子メールなど のいずれか |
情報提供にあたっては、「介護休業制度」が使えるだけでなく、介護の体制を構築するため一定期間休業できる場合に対応するなど、制度の目的も踏まえておこなうことが大切です。情報提供の際は、従業員に対して介護保険制度についても周知するようにしましょう。
※なお介護両立支援制度には、次のような制度が含まれています。
|
介護休業制度 |
要介護状態にある家族一人につき、最大93日間の介護休業を取得できる制度です。分割して3回まで取得が可能。介護休業給付金(休業前賃金67%)も受け取れます。 |
|
介護休暇制度 |
家族の介護や通院の付き添いのために年間5日(2人以上なら10日)取得できる制度です。2025年4月1日からは時間探知で取得できます。なお、要介護状態の家族を介護するすべての従業員が対象ですが、労使協定により一部の従業員(入社6ヶ月未満や、所定労働日数が2日以下の従業員など)は除外される場合があります。申請手段は書類提出に限定されず、口頭での申し出も可能です。 |
|
所定労働時間の短縮などの措置 |
・時短勤務 |
◆これらのうち少なくとも1つを企業が選択して実施します。
雇用環境の整備
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑におこなわれるようにするため、企業は次の①~④のいずれか、または複数の措置を講じる必要があります。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の従業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
企業が対応すべきこと
育児・介護に関する主な改正点に応じて、企業は制度や施策をどのように見直していけばいいのでしょうか。6つのポイントで解説します。
就業規則の見直し
2025年4月に施行される内容においては、同月までに自社の就業規則を確認して、法改正に合わせて修正・追加をしていく必要があります。育児・介護休業に関する規則の規定例や社内様式例が厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ぜひご参照ください。
参考URL: 育児・介護休業等に関する規則の規定例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/04.pdf
参考URL: 育児・介護休業等に関する規則の社内様式例
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/05.pdf
業務体制の見直し
2025年4月の法改正に伴い、残業免除の適用範囲の延長や子の看護休暇の取得事由の拡大により、従来の従業員数では業務に対応しきれない可能性があります。従業員一人ひとりの業務分掌の見直しや業務フローの簡略化などをおこないながら、最適な従業員数を確保することが求められます。それにより、安定した業務オペレーションが確立できるように取り組んでいきましょう。
従業員への周知と研修
法改正に伴い、企業は新制度や既存制度の変更点を従業員へ正しく伝えることが求められます。そのため、育児・介護休業制度の改正ポイントやその背景、活用法に関する研修を、一般の従業員から管理職まで幅広く実施し、理解を促しましょう。
従業員一人ひとりの制度を正しく理解することで、利用する側も遠慮せずに育児や介護に専念でき、支える側も快く送り出せる職場環境が整います。単なる情報共有にとどまらず、誰もが利用しやすい雰囲気づくりが重要です。
育児休業取得状況の公表準備
常時雇用する従業員が300人を超える企業(従来は1,000人超の企業)は過去1年間の男性従業員の育児休業取得状況を整理して、取得率を算出し、公表内容・方法を検討する必要があります。その上で自社のホームページや厚生労働省の「両立支援のひろば」など、公表媒体を選び、統一フォーマットで公表します。なお、公表は年に1回おこなう必要があります。そして公表前の事業年度(決算時期)の終了後、おおむね3ヶ月以内とされています。
面談等の強化
仕事と育児・介護との両立において支援が必要な従業員、今後必要になる可能性がある従業員に対して、企業は、さまざまな措置の周知と利用意向を個別で確認することが義務づけられました。なお、面接はオンラインで実施でき、定期的な人事面談とあわせて実施することも可能です。
※面談が受けられる従業員の条件は、上記での「育児・介護に関する主な改正点」で紹介した通りですので、ご注意ください。
継続的な見直しの実施
今回の法改正に合わせて、研修や個別面談の強化などをおこなっても、その成果がすぐに現れるわけではありません。それは全員が同じように理解できるわけではないからです。しかし、その状態を放置しておくと、「制度はあるが、取得者が増えない」「取得しにくい雰囲気がある」などの問題も発生してきます。制度を有効活用し、柔軟な働き方ができる環境を整えることで、従業員の定着率も向上します。そのため継続的に従業員にヒアリングしながら、制度の改善は必要不可欠になってくるでしょう。
まとめ
2025年4月施行の育児・介護休業法の改正では細かな法改正があり、しっかりと対応していかないと従業員は適切な制度を受けられなくなり、企業のコンプライアンス違反にもつながります。そのため、事前の就業規則の改正や、全従業員に周知するための研修の徹底が必要になるでしょう。また部下からの相談にも的確に対応できるように、管理職向けの教育・周知が特に重要です。2025年10月1日施行の施策もあり、人事部はスケジュール調整して、漏れがないように対応するようにしましょう。
<ライタープロフィール>
西谷 忠和
採用ライター&キャリアコンサルタント。新卒・中途採用などのメディアにて制作ディレクターを経験後、2007年に独立。現在は、求人メディアの広告、採用オウンドメディアの企画・編集・取材・執筆に携わっている。これまで2500名近くを取材。またライフワークとして、20~50代のビジネスパーソンやフリーランスのキャリア支援をおこなうキャリアコンサルタントとしても活動中。