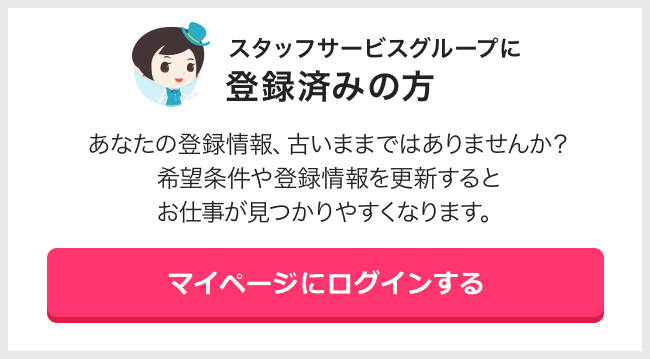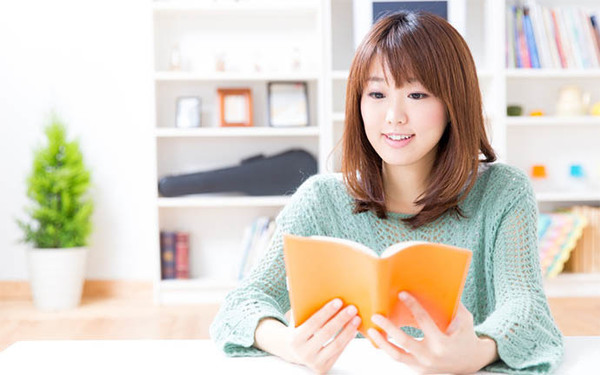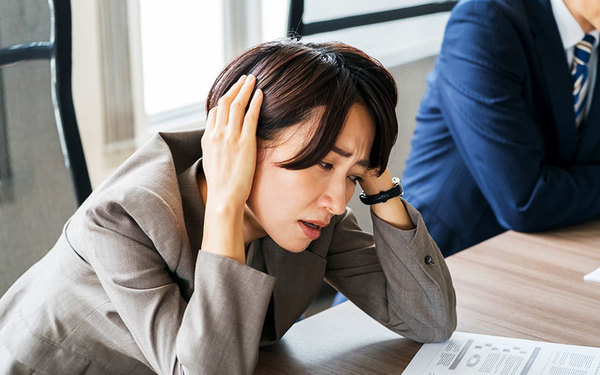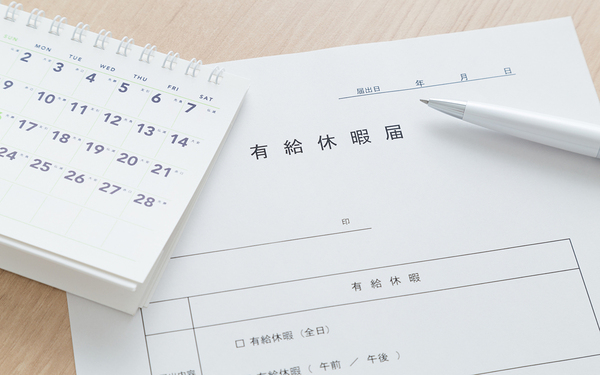失業保険の確定申告は原則不要!必要なケース・書き方を解説

失業保険を受給すると確定申告が必要になるのか、疑問に思うかもしれません。結論からお伝えすると、失業保険は非課税として扱われるため、基本的に確定申告の必要はありません。しかし、例外的に確定申告が必要になるケースや、確定申告によって還付金を受け取れるケースがあります。
そこで本記事では、失業保険の確定申告に関する基本的な内容や、確定申告が必要なパターン、具体的な手続きの流れなどを解説します。失業保険を受給中の人や、これから受給を検討している人は、ぜひ確認してみてください。
目次
失業保険は原則確定申告が不要

まずは失業保険の仕組みや確定申告について見ていきましょう。
失業保険とは
失業保険とは、雇用保険の「基本手当」のことです。仕事を失って収入源がなくなった人が安定した生活を送り、再就職の準備を進めるために支給されます。
失業状態であることが受給条件ですが、その他の主な要件は次のとおりです。
|
雇用保険の被保険者期間が一定期間以上であること |
一般的には、退職前の2年間に通算して12カ月以上、雇用保険に加入していた実績が必要とされる。倒産や解雇などの会社都合退職では、この期間要件が短縮される場合もある。 |
|
再就職の意思・能力があること |
仕事を探す活動(求職活動)をおこなっているかどうかがチェックされる。ハローワークでの失業認定日に来所する必要がある。また、再就職先を探していることを定期的に確認されるのが一般的。 |
失業保険は、求職中の方が安定した生活を送るために支給されており、税制上の「所得」とは見なされません。そのため、給付金そのものには所得税がかからず、原則的には確定申告が不要とされているのです。
確定申告とは
確定申告とは「1月1日から12月31日までの所得を申告し、所得税を納める手続き」のことです。たとえばフリーランスや個人事業主などの場合、給与所得や事業所得、雑所得など、すべての所得を合算し、毎年確定申告をおこなっています。
会社員など企業に雇用されている場合は、毎月の給与からあらかじめ所得税が差し引かれ、年末調整によって正確な納税額を再計算しています。もし所得税を払いすぎていたら還付を受け、不足があれば追加で納めることになりますが、いずれにしても雇用主が年末調整をおこなうため、自分で確定申告をする必要は基本的にありません。
しかし「会社員なら確定申告は全く必要ない」と決めつけてしまうのは要注意です。いくつかのケースでは、確定申告が必要になることがあります。以下で詳しく説明しますので、当てはまるものがないか確認してみましょう。
確定申告が必要なケース
失業保険そのものは非課税ですが、一部の条件が該当する場合は確定申告の手続きが必要になります。
年度途中で退職し、年末調整をしていない場合
会社員として働いていた人が年度の途中で退職した場合、年末調整を受けられないのが一般的です。年末調整をせずに仕事を辞めると、その年の1月から退職日まで給与所得が未精算となる恐れがあります。確定申告をおこない、正しい金額の所得税を納めましょう。
失業中にアルバイトなどで収入を得た場合
失業保険は失業状態かつ求職活動中の人に支給される給付金ではあるものの、失業中にアルバイトをすることも可能です。アルバイトの収入は課税対象として扱われます。そのため、失業保険を受け取っている間の収入によっては、確定申告が必要になる可能性があるので注意しましょう。
なお、失業保険受給中のアルバイトについては、一般的に以下のような扱いとなっています。
● 週20時間未満の労働:現アルバイト先と並行して、他所で週20時間以上の労働をする意思や能力があれば、失業保険を継続受給できる
● 週20時間以上の労働:「アルバイト先に就職した」という扱いになり、失業保険の受給対象から外れる
また、アルバイトが「就職」の扱いにならない場合でも「1日4時間以上働いた場合には、失業保険が不支給になる」「1日4時間未満働いた場合には、賃金に応じて減額される場合がある」など、失業保険が受け取れなかったり減額されたりするケースもあります。詳しくは、管轄のハローワークに問い合わせて確認するとよいでしょう。
さらに、「一週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用が見込まれる」という条件を超えると、アルバイト先で雇用保険に加入しなくてはなりません。その場合も失業保険が継続されない可能性が高いため、ご注意ください。
確定申告をおこなった方がよいケース
上記で挙げたケースとは別に、確定申告をしたほうが得になるケースもあります。失業保険は非課税ですが、所得税が還付される機会を見逃さないようにしましょう。
失業中に社会保険料を支払った場合
退職すると、これまで会社を通じて加入していた健康保険について、その任意継続もしくは国民健康保険への切り替えが必要となります。さらに、厚生年金も国民年金へと切り替わり、自分で保険料を支払うことになるでしょう。
これらの社会保険料を支払った場合、確定申告時に社会保険料控除として計上すれば、所得税が軽減される可能性があります。失業中にアルバイト収入や他の課税所得がある場合は申告を検討するとよいでしょう。
医療費控除や雑損控除などがある場合
1年間に支払った医療費の自己負担額が一定額を超える場合に利用できる「医療費控除」や、災害や盗難などで資産に損害があった場合に適用できる「雑損控除」は、退職して失業中であっても対象となります。
確定申告をすることで課税所得が少なくなり、結果として支払った税金の一部が戻ってくることがありますので、当てはまるかどうか確認してみてください。
税金の還付を受けられる可能性がある場合
退職時期によっては、失業で所得が減り前年に源泉徴収された税金が過払いになっているケースがあります。確定申告によって還付を受けられる可能性があるので、必ず申告しましょう。
失業保険と同時に退職金を受け取った場合
退職金は税制上で「退職所得」という区分に分類され、そのまま受け取ると20.42%の所得税と復興税が課せられます。ただし、確定申告で「退職金控除」となれば課税額を大きく減らすことが可能です。
例として、勤続年数40年で3,000万円の退職金が支給された場合のシミュレーションをしてみましょう。
|
そのまま受け取った場合の手取額 |
2,387万4,000円 |
|
退職金控除が適用された場合の手取額 |
2,921万9,678円 |
※CASIO「退職金の税金-高精度計算サイト」で計算
ただし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の所得税は会社で退職時に調整されるのが一般的です。もしこの申告書を提出していない場合は、忘れずに確定申告をして退職金控除を受けましょう。
確定申告の手順

ここからは、実際に確定申告をおこなうときの基本的な流れを解説します。書類準備から提出、納付・還付までのステップを順番に見ていきましょう。
必要書類の準備
確定申告をする際は、以下のような書類や情報をそろえる必要があります。
|
確定申告書(AまたはB) |
給与所得者や年金受給者は「確定申告書A」を使うことが多い。フリーランスや複数の所得区分がある場合は「確定申告書B」を使用する。 |
|
源泉徴収票 |
会社員として働いていた時期がある場合、退職時に会社から受け取っておく。 |
|
印鑑・マイナンバー |
申告書にマイナンバーを記入が必要。場合によって本人確認書類の提示や写しの提出も必要となる。 |
|
社会保険料の領収書、控除証明書 |
国民健康保険料や国民年金保険料を支払った証明書などを使用。 |
|
医療費控除の明細書 |
薬局や病院でもらう領収書、健康保険組合からの「医療費通知」などを使用。 |
|
各種控除証明書 |
生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受ける場合は、それぞれの証明書が必要となる。 |
必要な書類をあらかじめそろえておけば、申告書の作成作業をスムーズに進められます。もし書類を紛失してしまった場合は、会社や金融機関などを通じて早めに再発行の手続きをおこないましょう。
確定申告書の作成
確定申告書は、以下のいずれかの方法で作成できます。
|
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、一般的な確定申告ソフトを利用する |
パソコンやスマホで利用可能。サイト上の指示に従って入力すると、自動計算や書類作成ができる。最後にPDFで出力し、紙に印刷して提出するか、e-Taxを通じて申告する。 |
|
e-Tax(電子申告システム)を使う |
マイナンバーカードを読み取るカードリーダーやe-Tax対応のスマホを使うと、オンライン上で申告を完結できる。 |
|
税務署や市区町村の窓口で用紙に記入する |
繁忙期(2~3月)になると窓口が混雑するが、わからない点を直接相談できるメリットがある。 |
確定申告の初心者におすすめなのは、自動計算やスムーズな書類作成が可能な国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」や一般的な確定申告ソフト、そしていつでもどこからでも確定申告が可能なe-Taxの利用です。
ただし自分で確定申告の手続きをするのが難しい場合は、税務署の担当者に電話や窓口などで相談しながら申告するとよいでしょう。
確定申告書の提出
確定申告書の提出方法は、以下の3パターンのいずれかを選びます。
|
税務署窓口へ持参 |
税務署の開庁時間内に書類を持ち込む。その場で不足書類などを確認してもらえるのが利点。 |
|
郵送 |
税務署の窓口まで行かなくてもよいので便利。ただし書類の不備があると追加対応が必要になる。 |
|
e-Tax(電子申告) |
マイナンバー方式やID・パスワード方式を用いてオンライン上で申告する。24時間いつでも手続き可能だが、期限ギリギリはアクセスが集中するため、時間に余裕を持って申告するとよい。 |
提出期限は通常、翌年の3月15日となります(休日の場合は翌開庁日)。この期限に間に合わないと申告漏れや延滞税、加算税のペナルティを負う可能性があるため、早めの対応がおすすめです。
所得税の納付・還付
申告後に所得税額が確定し、追加で納付する必要があれば所得税を納めましょう。税務署や金融機関で現金による納付か、クレジットカードで振替納税を利用できます。納付期限は申告書提出と同じく3月15日頃ですが、振替納税の場合は少し遅い時期(4月中頃)に引き落としされますので、口座の残高不足に注意が必要です。
所得税が還付される場合は、申告書を提出してからおよそ1カ月~1カ月半ほどで指定口座に振り込まれます。また、e-Taxを使って電子申告すると、さらに早く還付が完了するケースが一般的です。ただし、申告方法に関わらず、申告内容に誤りや不備があれば還付の処理が遅れてしまう恐れがあるので気をつけましょう。
失業保険に関する留意点

失業保険は求職中でも安定した生活を送ることができる心強い制度ですが、その他の所得や控除、再就職の際の手続きなどで、注意すべき点がいくつかあります。
失業保険の不正受給はNG
就業しているにも関わらず失業保険をもらっていたり、給付金以外の収入を隠したりとハローワークへの報告に誤りや嘘が見つかった場合、「不正受給」と見なされて、以下のようなペナルティを科される可能性があります。
● 受給した失業保険の返還
● 受給停止や再就職手当などの支給停止
● 財産の差し押さえ
悪質な場合は、刑事罰の対象となることも考えられます。ハローワークには正しい情報を報告しましょう。
失業保険は年収に含まれない
転職活動や応募先との面接などで、よくある質問のひとつが「年収」についてです。もし年収を聞かれた場合は、失業保険は含めず、前職や失業保険を受給する前の所得で答えましょう。
非課税である失業保険を年収に加えてしまうと、答えた金額と源泉徴収票とで金額がずれてしまい、誤解を招く恐れがあります。
再就職時の手続き
再就職が決まった場合、以下の手続きをおこないます。
|
社会保険料の切り替え |
任意継続から国民健康保険への切り替え、または新しい会社の健康保険への加入手続きをおこなう。 |
|
前職の源泉徴収票の提出 |
転職先に前職の源泉徴収票を提出し、正確な年末調整を受けるための手続きを進める。 |
|
扶養控除等申告書の提出 |
家族の扶養控除を受けるため、新しい勤務先へ必要な書類を提出する。 |
手続きせずにいると年末調整や保険料の計算に影響が出てしまいます。再就職が決まったら速やかに対応しましょう。
失業保険の確定申告に関するよくある質問
失業保険に関する確定申告については、さまざまな疑問が寄せられます。最後に、よくある質問にまとめてお答えしますので、事前に疑問を解消しておきましょう。
退職金を受け取った場合、確定申告は必要?
前職の会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、自分で確定申告をする必要はありません。
もしこの申告書を提出していなかった場合は、確定申告が必要です。適切な税額にするため、退職所得控除も申告しましょう。
再就職手当は確定申告が必要?
再就職手当は、早期再就職を促すための給付金です。失業手当と同じく、基本的には確定申告の対象外となっているため、確定申告は必要ありません。
※関連記事:https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_151.html
失業手当をもらっていたら確定申告でばれる?
失業手当については確定申告書に記載されることはないため、就職先に提出する源泉徴収票や確定申告書の内容から「過去に失業手当を受給していた」という事実が知られる心配はありません。ただし、失業中のアルバイト収入などは確定申告をおこなうと記録として残ります。
まとめ
失業保険は非課税所得として扱われるため、基本的に確定申告は必要ありません。しかし、退職後の給与所得が年末調整を受けられなかった場合や、医療費、退職金など他の収入や支出が発生した場合は、確定申告によって税負担を軽減できる可能性があります。
また、失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、ハローワークに正確に報告しなくてはいけません。失業保険の受給資格は就労の状況により判断されるため、収入や働き方は事前に相談しておくことが望ましいでしょう。
失業中の手続きや控除を正しく理解しておくことで、その後の生活はより安定しやすくなります。確定申告が必要になった場合は、今回の記事をぜひお役立てください。
- ライター:いしかわ りの
- フリーライター。元保育士。出産や子育てを経験する中で家計管理や資産運用の大切さに気付き、FP3級を取得。多様な働き方を選択してきた経験も活かし、現在は保育、金融、人材系メディアなど幅広いジャンルの記事に携わっている(編集:株式会社となりの編プロ)