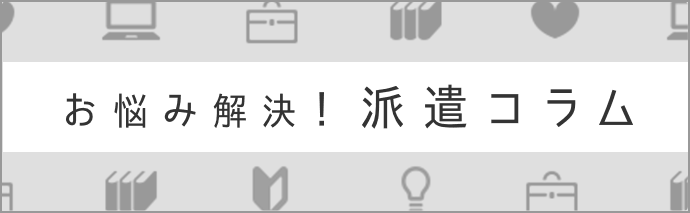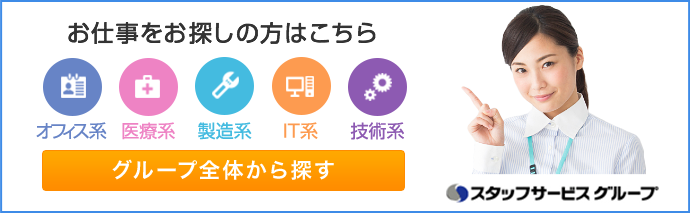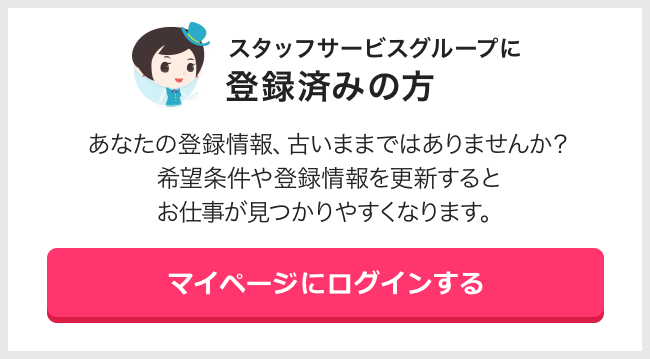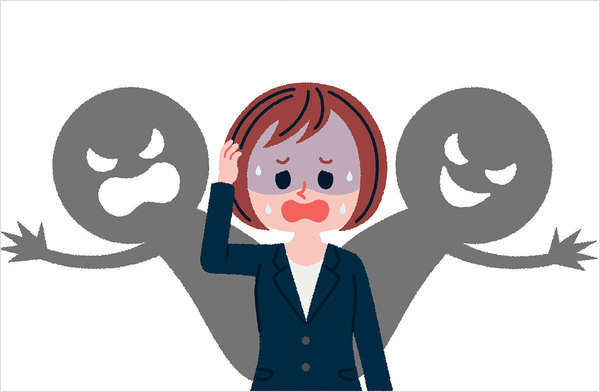フレックスタイム制とは?仕組みやメリット、残業代について解説

働き方改革が進み、仕事探しにおいて「柔軟な働き方ができるかどうか」に注目が集まるようになりました。働く時間に関する制度はいくつかありますが、それぞれの違いや特徴を知っている人は少ないかもしれません。
そこで今回は、働く時間を自由に決められる点で人気の高い「フレックスタイム制」について解説します。フレックスタイム制の仕組みや特徴だけでなく、メリットやデメリット、適している業界や職種についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)について総労働時間をあらかじめ定めておき、その範囲内で労働者が⽇々の始業・終業時刻を決められる制度です。労働者が自分で働く時間を決められるため、ワークライフバランスを実現しやすいことが最大のメリットです。
フレックスタイム制のしくみ
フレックスタイム制は、以下5つの要素から成り立っています。
● 清算期間
● 総労働時間
● コアタイム
● フレキシブルタイム
● 標準労働時間
上記の内容を明らかにすることで「いつからいつまでの間に、何時間働くべきなのか」「勤務すべき時間帯と、勤務しなくても良い時間帯」「1日の目安となる労働時間(=標準労働時間)」が決まります。
それぞれの内容について解説しましょう。
まず清算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、上記の「いつからいつまでの間に」に当たる部分です。当初は上限1ヶ月とされていましたが、2019年の法改正で上限3ヶ月に延長されました。
総労働時間は労働すべき時間のことで、法定労働時間である週平均40時間を基準に計算します。例えば清算期間を3ヶ月とした場合、4月から6月の総労働時間は以下となります。
| 1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(30日+31日+30日)÷7=520時間 |
つまり、4月から6月の労働時間の合計が520時間になればよく、この範囲内で「今日は予定があるから早く帰ろう」「今月は忙しいから長めに働こう」などと自分で調整できます。
コアタイムとフレキシブルタイムは、1日の働き方に関する言葉です。コアタイムは必ず働かないといけない時間帯、フレキシブルタイムは勤務してもしなくてもよい時間帯を指します。
例えばコアタイムが11~16時、フレキシブルタイムが7~11時と16~20時の企業があるとします。この場合、7時に出勤して16時に退勤したり、11時に出社して20時に退勤したりするなど、自由に調整してよいのです。
なお企業によってはコアタイムを設定せず「いつ勤務をしてもよい」とする場合があります。このようなコアタイムのないフレックスタイム制を、「スーパーフレックスタイム制(フルフレックス)」と言います。
そして標準労働時間とは、標準となる1日の労働時間のことです。清算期間内の総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間が基準となります。この標準労働時間は、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎になる重要なものです。例えば、フレックスタイム制で働く人が年次有給休暇を1日取得すると、標準労働時間分だけ労働したものと見なされます。
フレックスタイム制については、就業規則と労使協定に項目を設けて記載されているため、入社時によく確認するとよいでしょう。
変形労働制との違い
フレックスタイム制は変形労働時間制のひとつですが、変形労働制では企業が就業時間の決定権を持っています。また、繁忙期や閑散期に合わせて、月単位や年単位で労働時間を調整します。変形労働制の例として、シフト制の働き方をイメージすると分かりやすいでしょう。
時差出勤制度との違い
時差出勤制度も、自由に出勤・退勤時間を変えられる点でフレックスタイム制と似ています。しかし、時差出勤制度は通勤ラッシュ緩和のために作られた制度のため、1日の所定労働時間を変えられません。1時間早く退社するためには1時間早く出社し、1時間遅く出社した場合は、退社時間を1時間遅くする必要があります。
フレックスタイム制に適した業界・職種

近年、フレックスタイム制は多くの業界や職種で導入されています。どのような業界・職種でフレックスタイム制が導入されるケースが多いのか、確認していきましょう。
フレックスタイム制を導入する企業が多い業界は?
2023年の「就労条件総合調査」によると、フレックスタイム制を採用している企業は全体で6.8%でした。フレックスタイム制を導入している企業が多い業界は、情報通信業、学術研究・専門技術サービス業、電気・ガスなどのインフラ事業、複合サービス事業、金融・保険業などです。また、社員数が多いほどフレックスタイム制の導入率が高く、従業員数1,000人以上の企業では30.7%の企業で導入されていました。
フレックスタイム制が適している職種
フレックスタイム制はエンジニア、プログラマー、デザイナーなどに適していると言われています。これらの職種は、決められた範囲の作業を1人で進められ、社内外に対しては都合のよいタイミングでチャットを返すなどのコミュニケーションを取ることが多いからです。同じような働き方で自分のペースで業務を進められる企画職や事務職も、フレックスタイム制に適しているでしょう。
また、IT業界や金融業界、人材業界などの無形商材を扱う企業では、営業職でもフレックスタイム制の導入が進んでいます。営業職は社外とのコミュニケーションが多いので、フレックスタイム制を導入することで、顧客に合わせて柔軟にスケジュールを組み立てることができます。
フレックスタイム制が適していない職種
フレックスタイム制が適していない職種は、社内でのリアルタイムのコミュニケーションが多く求められる職種です。営業時間が決まっている店舗での接客業や、設備の稼動時間が決まっている工場のライン業務などは、社員の就業時間を揃えた方が効率的に業務を進められるため、フレックスタイム制には適していません。こうした職種においては、フレックスタイム制ではなく、就業時間が決まっている固定労働時間制や、変形時間労働制が適用されています。
フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制には、メリットとデメリットの両面があります。それぞれの内容を知っておき、仕事選びに役立てましょう。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制の最大のメリットは、自分で就業時間を決められるため、ワークライフバランスを実現しやすいことです。保育園のお迎えや、趣味、副業の状況に合わせて出勤や退勤の時間を設定でき、プライベートの時間を確保しやすくなります。
また、通勤ラッシュを避けて通勤時のストレスを緩和したり、遅くまで残業をした翌日に遅めに出勤したりすることもできるので、心身の健康管理もしやすくなるでしょう。業務量が少ない時には早めに退勤することで、メリハリをつけて働くこともできます。
なお、企業にとってもフレックスタイム制のメリットは多くあります。労働者が自ら退勤時間を設定することで、退勤時間までに仕事を終わらせようという意識が高まり、無駄な残業の削減や業務効率の向上が期待できます。また、ワークライフバランスが実現しやすいことから、生活環境の変化による退職を減らすことができ、採用活動時も応募者を集めやすいため、優秀な人材の確保や多様性のある組織を作りやすくなります。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制は労働者それぞれが就業時間を決めるからこそ、上司や同僚に相談したいときに相手が出勤していないということも起こります。そのため、社内のコミュニケーション量が減りやすく、新人教育や、迅速なフィードバック・意思決定が必要な業務にはあまり向いていません。
また、労働者自身に自己管理能力が求められます。タスク管理や時間管理が苦手な社員にとっては、残業時間が余計に長くなってしまったり、仕事を後回しにしているうちに期日までに終わらなくなってしまったりする可能性があります。
こうしたデメリットを解消するために、コアタイムを設定してコアタイム中に必要なコミュニケーションを取る、業務に慣れるまで新人にはフレックスタイム制を適用しない、という対応をしている企業もあります。
なお人事担当者にとっては、労働時間の管理や残業代の計算方法が複雑なため、フレックスタイム制を導入することで業務の難易度が高くなるというデメリットもあります。
フレックスタイム制の残業代について

フレックスタイム制における残業時間とは、清算期間中の実労働時間のうち、総労働時間を超過した時間のことです。清算期間の長さによって残業代の計算方法は変わるため、注意が必要です。ここでは、精算期間が1ヶ月の場合、3ヶ月の場合の計算例を紹介しましょう。
参考:厚生労働省ほか「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
清算期間が1ヶ月の場合の計算例
清算期間が1ヶ月の場合は、総労働時間から超過した実労働時間分が残業代となります。例えば、4月の実労働時間が220時間だった場合、残業時間は以下の方法で計算し、48.6時間となります。
・法定の総労働時間
週の平均労働時間(40時間)×4月の暦日数(30日)÷7=171.4時間
・4月の残業時間
実労働時間(220時間)− 法定の総労働時間(171.4時間)=48.6時間
清算期間が3ヶ月の場合の計算例
清算期間が1ヶ月を超える場合、残業時間は1ヶ月単位と清算期間全体の2つに分けて考えます。1ヶ月間単位では、週の平均労働時間が50時間を超えているかを確認し、清算期間全体では、その精算期間の終わりに、総労働時間の超過分を確認する必要があります。
例えば、次の実労働時間で働いた場合、4~6月の3ヶ月間の残業代を計算してみましょう。
<実労働時間>
4月:220時間
5月:172時間
6月:165時間
合計労働時間:557時間
1.ひと月ごとに週の平均労働時間数を計算
月ごとに週の平均労働時間が50時間を超えているかを確認すると、超過したのは4月のみでした。4月の残業代の対象となる残業時間の計算は以下のとおりです。
・4月の週の平均労働時間が50時間だった場合の総労働時間
50時間×30日÷7=214.2時間
・4月に週の平均労働時間50時間を超過した時間
実労働時間(220時間)- 週平均労働時間50時間(214.2時間)=5.8時間 ……①
2.清算期間が終わるときに、清算期間全体で①を除いた残業時間を計算
・4月から6月の総労働時間
1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数(30日+31日+30日)÷7=520時間
・支払うべき残業代の対象となる残業時間
実労働時間(557時間)- 清算済みの残業時間(5.8時間)- 法定の総労働時間(520時間)=31.2時間分
よって、この場合は6月分の給与にて、31.2時間分の残業代が支給されます。
このように、清算期間によって残業時間の計算方法は大きく異なります。2019年に清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されましたが、3ヶ月の清算期間を採用している企業は少なく、ほとんどのフレックスタイム制導入企業は1ヶ月ごとに清算しています。清算期間が1ヶ月を超えると残業代の計算が複雑になることは、1ヶ月ごとに清算する企業が多い理由のひとつかもしれません。
フレックスタイム制を導入している企業を知る方法

フレックスタイム制を導入している企業は、次のような方法で探すことができます。
会社の採用ページ
フレックスタイム制を導入している企業に魅力を感じる人は多いため、会社の採用ページでアピールしている企業があります。また、中途採用のページだけでなく新卒採用のページを見ると、学生向けにより詳しい福利厚生や働き方が説明されている場合もあります。
加えて社員インタビューなども確認すると、標準的な1日のスケジュールなどが掲載されていて、勤務時間の柔軟性がわかることがあります。
求人サイト
求人サイトでは、フレックスタイム制を導入している企業に絞って検索することが可能です。検索キーワードに「フレックス」などを設定したり、最初から検索条件の1つにフレックスタイム制の項目が設けられているサイトもあります。
スタッフサービスグループでは、キーワードに「フレックス」を設定して検索することでフレックス制を導入している企業の求人を探すことができます。
「フレックス」の求人一覧はこちら
説明会・面接
求人票や採用情報からはフレックスタイム制の導入状況がわからない場合や、運用の詳細まで知りたい時には、説明会や面接で直接社員に聞いてみましょう。ただし、ストレートに聞いてしまうと「フレックスタイム制があるから志望しているのだ」と思われてしまう危険性があります。
そのため、質問するときは「公式サイトでフレックスタイム制を導入していると記載がありましたが、社員の方は平均して何時頃に出勤・退勤されていますか?」「コアタイムの時間はどのくらいですか?」など、入社後のイメージを持つためにスケジュールを確認しているというスタンスが伝わるように聞いてみましょう。
口コミ
実際に働いている社員と会うことが難しい場合は、口コミから働き方の実態を知ることができます。ただし、口コミサイトは匿名性が高いため、間違った情報や制度が変わる前の古い情報も混ざっている可能性があります。目にした情報だけを鵜呑みにせず、複数の情報をすり合わせて確認しましょう。
まとめ

フレックスタイム制は、個々人の業務やプライベートの都合に合わせて柔軟に働く時間を変えられる魅力的な制度です。しかし、同僚とすぐにコミュニケーションが取れない、労務管理や給与計算が複雑になるというデメリットもあります。こうしたメリットやデメリット、制度の特徴をきちんと知った上で、フレックスタイム制が自分に合った働き方なのかどうかを吟味するとよいでしょう。
スタッフサービスグループでは、豊富な求人の中から、一人ひとりに合った働き方をご提案しています。興味のある方はぜひご相談ください。
<ライタープロフィール>
伊藤ゆかこ
フリーランスのキャリアコンサルタント兼ライター。人材派遣・紹介業での転職支援や採用支援を経験する中で、より多様なキャリアの提案をしたいと思い独立。現在は転職支援やキャリア相談を受けながら、転職やキャリア、採用に関わる記事制作に携わっている。(編集:株式会社となりの編プロ)