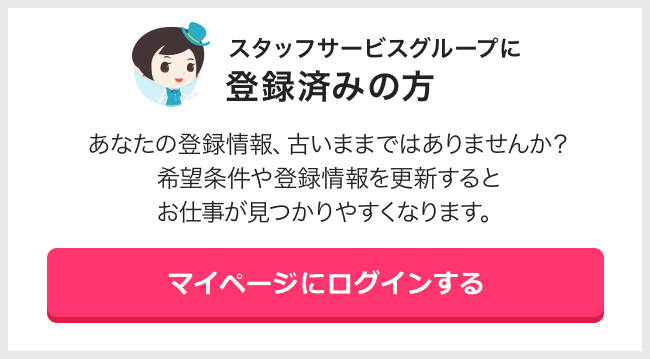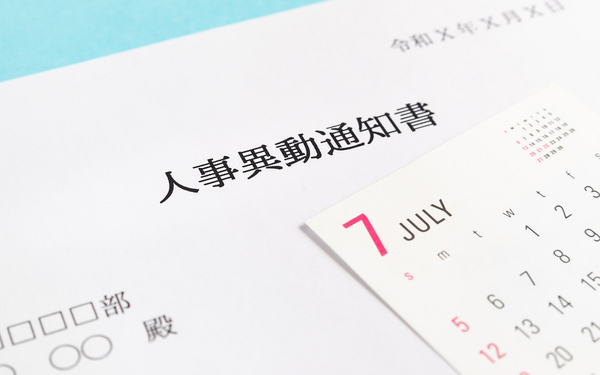派遣スタッフも健康診断を受けられる? 条件や負担費用を解説

派遣スタッフでも健康診断を受けられるかどうかは、派遣スタッフとして働いている人、これから派遣で働くことを考えている人にとって気になる点です。基本的には、派遣労働者も健康診断を受けられます。ただし、派遣スタッフの場合、受診するために満たすべき条件や費用などに関する注意点があるので、今回はそれらについて詳しく解説していきます。
目次
派遣スタッフも健康診断を受けられる

派遣スタッフは正社員と同様に、企業が提供する健康診断を受けられます。派遣元企業や派遣先企業の法的義務、健康診断の種類や検査項目について紹介します。
派遣労働者の健康診断は、法律で決まっている
企業には雇用する従業員の安全衛生と健康を守る責務があります。これを法制化したのが「労働安全衛生法(安衛法)」で、1972年に労働基準法から分離されました。労働安全衛生法66条において「健康診断の義務」が定められ、同120条には罰則規定もあります。
健康診断に関する法の規定は、派遣労働者も対象となります。「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、通称労働者派遣法の45条において、労働者派遣事業は労働安全衛生法の適用を受けるとされています。
一般健康診断と特殊健康診断の違い
労働安全衛生法で規定される健康診断には「一般健康診断」と「特殊健康診断」があります。
一般健康診断は誰もが対象となる健康診断です。常時使用される一般の労働者を対象とする健康診断として、1年に1回実施される定期健康診断のほか、雇入時健康診断があります。また、深夜業に従事する者などに対して行う健康診断の頻度はさらに高く定められています。
特殊健康診断とは、化学物質や放射線などに関わる有害な業務に従事する労働者のための健康診断で、具体的な業務や健康診断の項目、頻度などが同法で規定されています。
派遣という労働形式では雇用主と職場が異なるため、雇用契約がある「派遣元企業」だけでなく「派遣先企業」も労働安全衛生法の適用を受け、派遣スタッフの安全衛生確保の義務を負います。このため、派遣元と派遣先の企業は労働者派遣契約のなかで安全衛生についてそれぞれが負う責任を定めることになっています。
具体的には「一般健康診断は派遣元企業が実施し、業務に伴って必要となる特殊健康診断は派遣先企業が実施する」といった形になり、費用もそれぞれが負担します。
| 対象 | 費用負担 | |
| 一般健康診断 ・定期健康診断 ・雇入時健康診断など |
すべての常時使用する 労働者が対象 |
派遣元企業 |
| 特殊健康診断 | 労働安全衛生法で定める 有害な業務に従事する労働者 |
派遣先企業 |
健康診断の項目
労働安全衛生規則第44条などにより、健康診断の項目が定められています。以下は定期健康診断の項目です。
<定期健康診断の項目>
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※)、体重、腹囲(※)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※)及び喀痰(かくたん)検査(※)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
9 血糖検査(※)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査(※)
※の項目は、受診者の年齢などを考慮のうえ、医師の判断により省略が可能とされているので、実施されないこともあります。
健康診断を受けるための条件

労働安全衛生法に基づく定期健康診断の対象者は、「常時使用する労働者」です。
健康診断の実施義務が発生する条件
■常時使用される労働者
常時使用される労働者なら、雇い入れから1年経っていなくても対象となります。
■以下の①②の両方を満たす短時間労働者
① 無期契約、または有期契約で1年以上使用されることが予定される者であること
② 週所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
常時使用される労働者なら、雇い入れから1年経っていなくても対象です。
これを派遣スタッフにあてはめるとどうなるのか? 一般的には以下となっています。
まず、派遣会社に派遣スタッフ登録をしているだけでは勤務実績がないため、健康診断を受診できません。実際にいつ健康診断を受けられるかどうかは、勤務が発生するときに締結する派遣会社との契約によります。したがって、派遣会社ごとに条件が異なります。派遣会社それぞれが就業年月などの基準を定め、実施しています。
※スタッフサービスの場合、健康診断の実施規定は以下となっています。
---------------------------------------------------------------------
健康診断の受診対象
<就業1年目>
算定月(春または秋)の時点で、雇用契約が4.5ヶ月以上経過かつ、週30時間以上のご契約の方
<就業2年目以降>
ご就業1年目と同時期(春夏健診または秋冬健診)に、週30時間以上のご契約の方
※受診対象就業開始日によって、健康診断の時期が異なります。健康診断受診日前に雇用契約が終了してしまった場合は、定期健康診断を受診することはできません。
参考サイト
https://www.staffservice.co.jp/benefits/health.html
---------------------------------------------------------------------
実際にいつ健康診断を受診できるのかについては、個別の雇用契約書で確認してください。また、不明点があれば派遣元企業の担当窓口に問い合わせをしましょう。
健康診断を受診する流れと費用負担

基準を満たした場合、派遣スタッフにメールや文書で健康診断受診の案内が届きます。受診の手順や費用について解説します。
定期健康診断は1年に1回、自分で申し込む
定期健康診断は1年に1回実施されることが一般的で、これは正社員と同程度です。一般的な健康診断の場合、所要時間は半日または1日です。案内が届いたら必要事項を確認し、自分で健康診断の予約をしましょう。
健康診断を実施する期間内で希望する日時に予約が取りづらいこともあります。特に、期間終了の間際は混雑して予約できない可能性があるので、早めに手続きをすることをおすすめします。
受診後には診断結果が届き、自分の健康状態を確認することができます。もしも再検査の通知があれば自分で病院へ行きましょう。再検査や治療の費用は自己負担となりますが、早期に対処することが最重要です。
受診費用、給与や交通費はどうなる?
一般健康診断の費用は派遣元企業が負担するため原則として無料です。しかし自分でオプションの検診を申し込んだ場合は追加費用を支払う必要があります。また、受診の際にいったん実費を立て替え払いして後で払い戻しを受ける場合もあるので、不安な点があれば事前に確認しましょう。
次に注意したいのは給与規定です。派遣スタッフの場合、健康診断は業務の範囲外となり原則として無給です。休日、または有給休暇を取得して受診しましょう。健康診断にかかる交通費などの経費支給はないため、指定医療機関のうちで最寄りの病院を選ぶようにするとよいでしょう。
「派遣先から受診の許可がもらえない」など、疑問点あれこれ

「健康診断を受診したいが、派遣先企業から休みをもらえない」など、派遣スタッフの健康診断に関するよくある疑問点について解説します。
派遣先で休みの許可が出ない場合は?
前述したように、派遣スタッフが健康診断を受ける場合は勤務時間外となります。平日フルタイムで勤務している派遣スタッフの場合、平日に休みを取らないと健康診断が受けられない場合もあるでしょう。そんなときは休日を取得する必要がありますが、もし「健康診断受診のため」として派遣先企業に申請しても休みの許可が出ない場合はどうすればいいでしょうか。
この場合、すぐに派遣元企業の担当者に相談しましょう。健康診断の受診は労働者派遣法で定められている派遣労働者の権利なので、受診条件を満たしているにも関わらず派遣先企業が受診を拒否することは罰則の対象になります。また、特殊健康診断の場合には派遣先企業に実施の義務がありますが、これが実施されない場合も同様です。
派遣スタッフの健康診断受診は義務?
派遣スタッフの場合健康診断は無給であることから、休みを取ってまで健康診断を受診したくないと考える人もいるかもしれません。また、受診したい気持ちはあるが忙しくて予約を取れなかったという場合もあるでしょう。もし健康診断を受診しなかった場合はどうなるのでしょうか。
受診しなかった場合の罰則などはありませんが、労働安全衛生法第120条では、受診対象者に健康診断を受けさせない企業には、50万円以下の罰金が科されます。企業によっては就業規則で「従業員は健康診断を受けなければならない」と義務付けているところもあり、受診しなかった派遣スタッフは懲戒処分の対象になりえます。
また、派遣スタッフ自身も健康管理が何より重要ということを考えれば、健康診断はできるだけ受診した方がよいでしょう。
まとめ
企業が従業員の安全と健康を守る義務を定めた「労働安全衛生法」に基づき、派遣スタッフも健康診断を受けることができます。一定の条件を満たしたうえで、1年に1回の定期健康診断を受診することが一般的です。通知がきたときは速やかに内容を確認し、必要に応じて休暇を取得して予約を済ませます。自分自身の健康管理のため、健康診断の機会を積極的に活用しましょう。