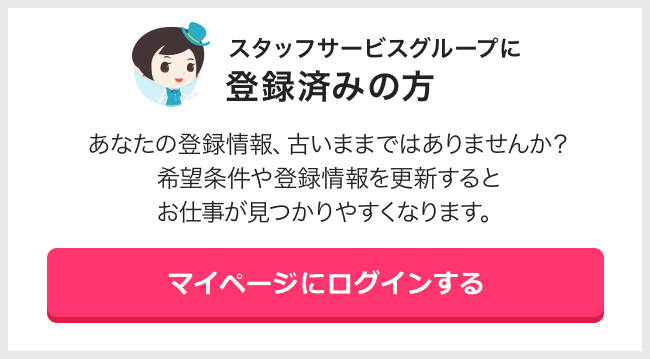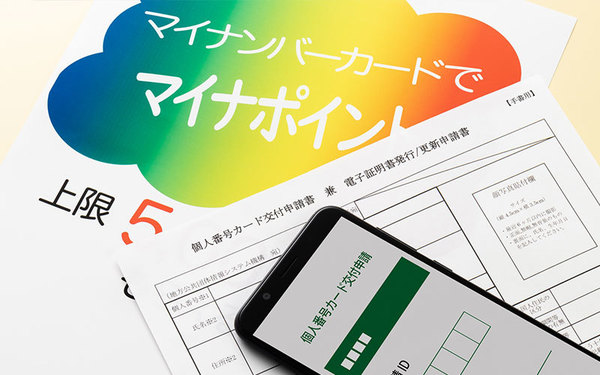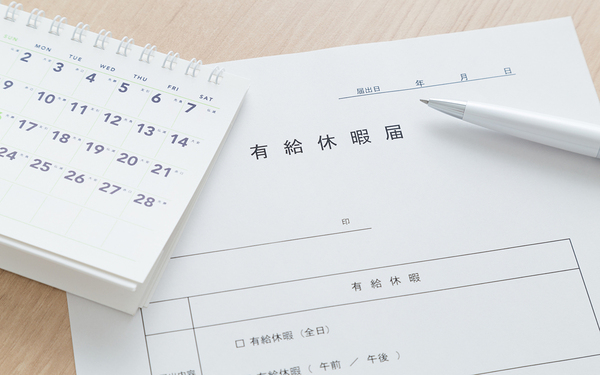扶養の壁とは?扶養の種類・年収の壁・扶養内で働くポイントを解説

配偶者の扶養に入りながら働く人にとって注意が必要なこととして「扶養の壁」があります。扶養の壁とは税金や社会保険料の負担が発生する基準のことです。ただし、扶養の壁には、さまざまな「年収の壁」が存在しており、それぞれで条件が異なります。
本記事では、扶養の壁の概要や年収の壁を解説するとともに、扶養の範囲内で働くための対策や社会保険に加入するメリットについて紹介します。
目次
扶養の壁とは
扶養の壁とは、一定の年収を超えると税制上の扶養控除や社会保険の扶養資格を失い、税金や社会保険料の負担が発生する基準のことを指します。扶養とは、1人だけの収入では生活が難しい人に対し、家族が経済的な援助を提供することです。よくある例として挙げられるのは、夫が扶養者で妻が被扶養者というケースです。
被扶養者の年収が扶養の範囲内であれば、被扶養者は社会保険料や住民税、所得税の支払いが免除されます。しかし扶養範囲には上限があり、被扶養者の年収がこの上限を超えると、社会保険料や住民税、所得税の支払い義務が発生します。
パートやアルバイトで働く人が、家庭での手取り収入の減少回避を目的として、労働時間を抑制するケースは珍しくありません。それにより、人手不足に悩まされる問題がさまざまな企業で発生しています。
労働者側と企業側の双方にとって影響の大きな制限であることから「扶養の壁」と呼ばれるようになりました。
扶養には2種類ある
扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ異なる年収の上限が設定されています。ここでは、それぞれの扶養について解説します。
税制上の扶養
税制上の扶養には、配偶者控除・配偶者特別控除があり、配偶者の年収が上限内であれば所得税と住民税が控除されます。配偶者が会社員と自営業のどちらでも適用対象です。
配偶者特別控除の場合、控除額は、年収150万円以下を満額に減少し、年収201万円まで控除額が設定されています。学生やフリーターなど、親の扶養に入っている場合の配偶者控除の年収上限は、103万円以下までです。
年収は、掛け持ちや年の途中で退職した会社の分も含めて、その年の1月から12月の合計で算出します。交通費は計算の対象外です。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、扶養者が勤める会社の社会保険の扶養を指します。扶養に入ることにより、被扶養者の国民年金や健康保険の保険料が控除されます。ただし、親の扶養に入っている場合は、健康保険のみが控除の対象です。そのため、20歳以上であれば国民年金保険料を支払う必要があります。
社会保険の加入基準となる年収の対象には、交通費も含まれます。扶養者の扶養から外れる条件は以下のとおりです。
● 被扶養者が勤務先の社会保険に入った場合
● 年間の収入が130万円を安定的に超えると判断された場合
詳細な基準は各健康保険組合や協会けんぽによって異なるため、確認が必要です。
収入調整が必要な理由
パートとして働く人が、収入調整のために労働時間を調整するケースは珍しくありません。これは、被扶養者の年収が上限を超えると、社会保険料や住民税、所得税の支払い義務が発生するためです。
年収が上がったのにもかかわらず支払いが増えた結果、手元に残るお金が減ってしまっては働いた甲斐を感じられなくなるかもしれません。そのため、労働時間から年収を算出し、上限を超えそうな場合は労働時間を抑制します。つまり、手取り額の確保のために収入調整をしているのです。
年収の壁とは

税制上の扶養と社会保険上の扶養で年収の上限額が異なり、それぞれの年収上限の金額を壁と表現し、〇〇万円の壁と呼んでいます。ここでは、それぞれの年収の壁について解説します。
103万円の壁(税金)
103万円の壁は、所得税が課税される年収の壁です。これは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計が103万円になるためです。所得税は年収に対して課税額が設定される税金ですが、年収が103万円以下の場合は非課税になります。
仮に年収が130万円の場合、支払う所得税額は以下のようになります。
年収130万円-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=課税所得27万円
課税所得27万円×所得税率5%=所得税額13,500円
なお、2025年度(令和7年度)の税制改正により、所得税がかかり始める年収の壁は123万円に引き上げられることが決まっています。
106万円の壁(社会保険)
106万円の壁とは、2022年10月の法改正によりできた年収の壁です。社会保険(厚生年金・健康保険)の適用条件が拡大されたことにより、年収106万円が新たな壁となりました。106万円の壁には残業代は含まれません。
ただし、厚生年金を負担すると将来受け取る年金が上乗せされます。そのため、106万円の壁はデメリットだけとはいえません。
130万円の壁(社会保険)
130万円の壁も、社会保険に関する年収の壁です。従業員数が50人以下の企業のような、前述した社会保険の適用条件を満たしていない場合でも、年収が130万円を超えると扶養から外れ、国民年金と国民健康保険を支払わなければなりません。130万円の壁には、残業代や休日手当、不動産収入なども含まれます。
150万円の壁(税金)
150万円の壁は、配偶者特別控除が満額受けられるかどうかの壁です。年収150万円までであれば、配偶者特別控除は満額の38万円です。年収150万円を超えると、収入が増えるにつれて配偶者特別控除額が減っていきます。配偶者特別控除の詳しい解説については後述します。
労働者が直面する扶養の壁

労働者が直面する扶養の壁として、社会保険上の扶養と税制上の扶養があることは前述したとおりです。ここでは、それぞれの扶養で直面する問題について解説します。
社会保険の扶養条件
2022年10月の法改正により社会保険の扶養条件が拡大され、以下のとおりとなりました。
● 勤務先企業の従業員数が51人以上(2024年9月までは100人以下)
● 週に20時間以上勤務している
● 1か月の賃金が額8.8万円(年収106万円相当)以上
● 雇用期間が2か月以上見込まれている
● 学生でない(夜間や定時制は除く)
1か月の賃金を算出する場合、以下のものは対象外です。
● 臨時に支払われる賃金や1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当や賞与)
● 時間外労働や休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例:残業手当)
● 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:通勤手当や家族手当)
この条件を満たした場合、社会保険への加入が義務となり、毎月の給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。従業員数が50人以下の企業でも、労使合意(労働者の1/2以上と事業主が社会保険への加入に合意すること)に基づき申し出している場合や、地方公共団体に属する事業所は、従業員数が51人と同等の規模と判断されます。
税制上の扶養における配偶者控除と配偶者特別控除とは
税制上の扶養における控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があり、どちらも被扶養者を扶養している扶養者の税負担を軽減できるものです。被扶養者の所得額が48万円以下の場合は配偶者控除、48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除を利用できます。
配偶者控除
配偶者控除は、被扶養者がいる扶養者が受けられる所得控除です。配偶者控除を受けるには、被扶養者が以下の条件を満たしていなければなりません。
● 民法の規定による被扶養者(内縁関係の人は対象外)
● 扶養者と生計を一にしている
● 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
● 青色申告者の事業専従者として、1年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
所得金額は、収入から給与所得控除を差し引いたものです。そのため、被扶養者の年収が103万円以下であれば配偶者控除が受けられます。配偶者控除の控除額は、扶養者の合計所得金額や被扶養者の年齢によって、以下のように異なります。
|
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
|||
|
一般の控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
|||
|
所得税 |
住民税 |
所得税 |
住民税 |
|
|
900万円以下 |
38万円 |
33万円 |
48万円 |
38万円 |
|
900万超950万円以下 |
26万円 |
22万円 |
32万円 |
26万円 |
|
950万超1,000万円以下 |
13万円 |
11万円 |
16万円 |
13万円 |
合計所得金額が900万円以下の場合、年収問わず同じ控除額になります。合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えるとゼロになります。
そのため、配偶者控除を利用するには、扶養者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。また、被扶養者が70歳以上になると控除額が増加します。
参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、被扶養者の年間の合計所得金額が48万円を超えた場合の措置として設けられた所得控除です。扶養者と被扶養者それぞれの合計所得によって以下のように一定金額の所得控除が受けられます。
|
被扶養者の合計所得金額(給与収入のみの場合の年収) |
扶養者の合計所得金額 |
||
|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
|
|
48万超 95万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
|
95万超 100万円以下 |
36万円 |
24万円 |
12万円 |
|
100万超 105万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
105万超 110万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
110万超 115万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
115万超 120万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
120万超 125万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
125万超 130万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
130万超 133万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
|
133万円超 |
0円 |
0円 |
0円 |
被扶養者の合計所得金額が95万円以下(年収150万円以下)であれば、所得税と住民税の控除額は配偶者控除と同じですが、被扶養者の合計所得金額が95万円(年収150万円)を超えると段階的に控除額が減少します。
被扶養者の合計所得金額が133万円(年収201.6万円)を超えると、所得税と住民税の控除はゼロになるため、201万円にも年収の壁があるといえるでしょう。
参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
扶養の範囲内で働くための対策

扶養の範囲内で働くための対策として以下の3つが挙げられます。
● 社会保険加入の条件を確認する
● 一時的に収入が増えた場合の対応
● 働き方で収入を調整する
ここでは、それぞれの対策について解説します。
社会保険加入の条件を確認する
扶養の範囲内で働くのであれば、勤務先の従業員数と労働時間などの社会保険加入の条件を確認したうえで、収入や出勤日数、労働時間を調整する必要があります。例えば年収を130万円未満に抑えるのであれば、月収を108,333円程度にしなければなりません。
残業で月収108,333円を超えるケースがひと月のみあるような場合は、扶養範囲と認められます。しかし、社会保険の加入は月収ベースでも判断されるため、2か月連続で108,333円を超えたり3か月平均での月収が108,333円を超えたりする場合は、扶養から外れてしまう可能性があります。
社会保険の加入条件の年収は、交通費も含まれる点にも注意しましょう。企業によって、社会保険加入の要件が異なるため、事前に確認が必要です。
一時的に収入が増えた場合の対応
収入を抑えたいと思っていても、トラブル発生や繁忙期などで残業せざるを得ず、月収や年収が扶養範囲を超えてしまうケースもあるでしょう。その場合の措置として設けられている制度に「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」があります。
パートやアルバイトで働く人の収入が一時的に扶養範囲を超えた場合でも、事業主がその旨を証明すれば扶養対象として認められます。
参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
働き方で収入を調整する
扶養の範囲内で働く方法として、働き方で収入を調整するのもひとつです。近年では柔軟な働き方を導入している企業が増えており、在宅ワークや単発バイトで人材を活用する企業も増えてきました。
働く時間を選べるようフレックス制度を導入したり、労働時間を抑えて働きたい人向けに時短勤務を導入したりする企業も存在します。副業や単発バイトを活用したり、フレックス制度や時短勤務のある企業で働いたりすれば、効率的に扶養範囲内での収入調整ができるでしょう。
副業、単発バイトの活用
副業や単発バイトは、自分で働く時間を決められるため、時間や収入の調整が容易にできます。パソコンでのデータ入力や、軽作業、イベントスタッフなどの仕事であれば、未経験でも採用される可能性が高いでしょう。
スキルや資格を持っているのであれば、単価が高い仕事を受けられる可能性もあります。複数の仕事を受ければ、収入調整はさらにしやすくなります。
フレックス制度や時短勤務
フレックス制度を導入している企業で働けば、働く時間を自分で調整できます。ただし、全員が出社する「コアタイム」を設けている場合や繁忙期による業務量増加の場合、時間調整が難しくなる可能性があるため、注意が必要です。
時短勤務をするのもひとつの方法です。月収や年収が扶養範囲内に収まる時間で契約して働けば、労働時間を調整する必要がなくなります。
社会保険に加入するメリット

扶養範囲内で働けば、社会保険料や税金の控除といったメリットがあります。ここでは、狭義の社会保険である「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」のメリットについて解説します。
健康保険のメリット
健康保険とは、医療費の一部を負担してくれる保険です。保険証を提示すれば、年齢に合わせて以下の負担で治療が受けられます。
0歳~6歳(義務教育就学前):2割
7歳(義務教育就学後)~70歳未満:3割
70歳~75歳未満:2割(現役並み所得者は3割)
75歳以上:1割(現役並み所得者は3割)
社会保険に加入した場合、健康保険料の半額は会社負担です。扶養を外れて国民健康保険に加入した場合、全額自己負担になります。
また、社会保険に加入すれば、傷病手当金や出産手当金がもらえるメリットがあります。傷病手当金は、病気やケガによる休職期間中に給与の2/3相当の金額が支給される制度です。病気やケガで休んだ4日目から受け取れます。支給期間は開始から通算で1年6か月です。
出産手当金は妊娠・出産に伴う休業中の生活支援を目的とした給付金で、出産を理由に休職する場合に給与の2/3相当の金額を受け取れます。出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)と、出産後56日以内に仕事を休むことが支給条件です。支給期間は出産前42日から出産後56日までの最大98日分です。
厚生年金保険のメリット
厚生年金保険とは、働いている間に支払う保険料を積み立て、老後に年金として受け取れる制度です。保険料は給与から天引きされ、企業がその半分を負担します。厚生年金保険のメリットとして、挙げられるのは以下の2つです。
● 基礎年金にプラスして老齢年金がもらえる
● 障害年金や遺族年金も保障される
厚生年金は、基礎年金(国民年金)に上乗せされるため、将来もらえる年金が増加します。将来受け取る年金額は、納付期間や給与額に応じて決まり、納付期間が長く、給与が高いほど受け取る年金額も多くなります。
国民年金における障害基礎年金の対象は、障害等級1・2級のみです。一方、障害厚生年金では、3級の場合に一時金が支給されます。また、国民年金における遺族基礎年金は要件を満たす配偶者もしくは子のみの支給となっていますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者と子、父母、孫、祖父母が受け取れます。
厚生年金保険は、将来への金銭面での保障として大きなメリットがある制度です。
介護保険
介護保険とは、高齢者や身体障がい者など、日常生活に支障をきたす方々が必要とする介護サービスを受けられる制度です。原則として、40歳以上で介護が必要になった人が対象です。
40歳になると介護保険料の加入義務が生じます。40歳から64歳までの被保険者は、加入している健康保険と合わせて徴収される仕組みになっており、社会保険に加入すると、健康保険と同様に企業が半額を負担します。
介護認定を受けた場合、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護サービスを利用できますが、サービスを受けるには費用を支払わなければなりません。社会保険に加入していれば、自己負担額が1~3割で済むため、経済的負担が抑えられることもメリットです。
まとめ

扶養の壁とは、一定の年収を超えると税制上の扶養控除や社会保険の扶養資格を失い、税金や社会保険料の負担が発生する基準のことです。年収の上限を超えた場合、年収が上がったのにもかかわらず支払いが増え、手元に残るお金が減ってしまいます。手取り額の確保のためには、扶養条件を確認したうえで、収入調整が必要です。
収入を調整する方法として、副業や単発バイトを活用するほか、派遣社員として働く方法もあります。扶養範囲内で働ける派遣を選択すれば、収入調整が容易になります。本記事を参考に扶養の壁を理解し、自分に適した働き方を見つけましょう。
- ライター:田仲ダイ
- エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。