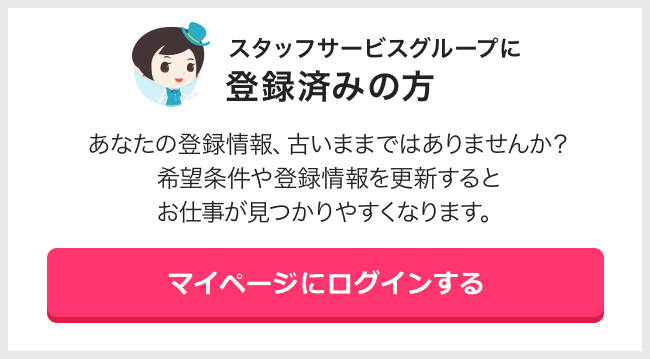派遣社員は住宅ローンを組める?審査項目やポイントを解説

大きな金額を借り入れる住宅ローンでは、申し込む人の返済能力や信用情報などが確認され、審査がおこなわれます。審査では就業形態や収入状況なども重視されることから、「派遣社員では審査に通らないかもしれない……」と不安を感じる人も少なくありません。
そこでこの記事では、派遣社員が住宅ローンを組めるのかどうか、審査で重視される項目、申し込む際のポイントなどを解説します。
目次
派遣社員は住宅ローンを組める?

国土交通省の「令和6年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」によると、長期・固定金利の住宅ローン審査において「派遣社員は対象外」としている金融機関は974社の回答のうち368社、つまり約4割にのぼっています。
しかし見方を変えれば、約6割の金融機関では派遣社員でも住宅ローンを組める可能性があるということです。最初から諦めずに、適切な金融機関を選ぶことが重要です。
派遣社員が住宅ローン審査で不利になりやすい理由
住宅ローンの審査では主に「安定した収入があること」が重視される傾向にあります。安定した収入源がある人は、返済にも見通しがつきやすいためです。
一方、派遣社員は契約更新のタイミングで雇用関係が終了する可能性もあることから、正社員と比較して「収入が安定しにくい」と判断される要因にもなります。
また、住宅ローンの審査では勤続年数についても申告します。派遣社員では「3年ルール」と呼ばれる制度があり、原則同一の派遣先の事業所で3年を超えて働き続けることができません。そのため、正社員に比べてどうしても勤続期間が短くなりやすい傾向があるのです。
こうした点も、金融機関が「長期的な返済能力に不安がある」と判断するきっかけになるかもしれません。
住宅ローン審査でチェックされる主な項目

住宅ローンの審査で重視する具体的な項目は、どの金融機関でも公表していません。しかし一般的には、主に下記のような項目をチェックしているといわれています。
・年齢
・収入状況
・信用情報
・勤務先・勤続年数
・自己資金の準備状況
それぞれどのようなポイントをチェックされるのか解説していきましょう。
年齢
住宅ローンでは、申し込みにあたって年齢に関する条件が定められており、審査で重視されるポイントのひとつとなっています。条件は各金融機関によって異なりますが、「満18歳から満70歳」とされていることが一般的です。
また、申し込む時だけでなく「完済時の年齢が満80歳以下であること」も条件とされることが多くなっています。たとえば、50歳で借り入れる場合、借入期間を30年以上にすると80歳を超えての返済となるため、審査で不利にはたらくこともあるかもしれません。
なお、最近では借入期間が40年を超えるような住宅ローン商品も登場しています。借入期間を長くすることで月々の返済金額を抑えられるメリットがあるものの、年齢の条件を踏まえると誰もが利用できるわけではありません。
たとえば、借入期間40年の住宅ローンを組むには完済時の年齢が80歳以下である必要があるため、借入時の年齢が40歳を超えると申し込みの対象外となる可能性があります。
収入状況
前述の国土交通省の調査によると、住宅ローンの審査項目で「年収」を選択した金融機関は96.0%となっており、ほとんどの金融機関で年収がチェックされていることが分かります。
具体的な年収の水準についての回答は下記の通りです。
・100万以上・・・288社
・150万以上・・・390社
・200万円以上・・・67社
・250万以上・・・24社
・その他・・・184社
※参考:国土交通省「令和6年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」
年収の水準は各金融機関によって異なりますが、100~150万円以上としている金融機関が多いことからそれほど厳しい審査水準ではないことが推測されます。
ただし、年収水準は借入額によっても異なります。年収に対して借入希望額が大きい場合は、「返済能力がない」として希望する金額が借りられないこともあるかもしれません。
信用情報
住宅ローンに限らず、借り入れをおこなう際は必ず信用情報がチェックされます。信用情報とは、過去のローンやクレジットカードなどの申し込み履歴や利用状況に関する情報のことです。
信用情報は「信用情報機関」にて管理され、必要に応じて金融機関やカード会社と共有されます。ローンの申し込みを受けた金融機関は信用情報を照会し、「これまで期日に遅れることなく返済・支払いをおこなっているか」「同時期に複数社にローンの申込みをおこなっていないか」などの観点で確認しています。
もし過去にローンの返済やクレジットカードの支払いに遅れた履歴があると、「住宅ローンの返済が難しいのではないか」と判断されてしまうこともあるでしょう。
勤務先・勤続年数
返済能力を判断する際は、勤務先や勤続年数も重要な要素となります。前述の国土交通省の調査では、住宅ローン審査において下記のような職業に関する項目を設けている金融機関が多く見られました。
・業種・・・42.4%
・雇用形態・・・69.5%
・雇用先の規模・・・31.8%
・勤続年数・・・93.2%
※参考:国土交通省「令和6年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」
安定した勤務先に長年勤めている人は収入の見通しがつきやすく、審査でプラスに働く可能性があります。一方、勤続年数が短い人は現在の収入状況が今後も続くかどうかが推測しづらいため、審査で不利になることもあるかもしれません。
上記結果を見ると、勤続年数を特に重視する傾向があることから、一般的に勤続年数が短くなりやすい派遣社員は、審査で敬遠されてしまうことも懸念されます。
自己資金の準備状況
自己資金の有無やその金額も、住宅ローンの審査でチェックされる項目のひとつです。
住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査(2024年10月)」によると、住宅ローンを借りた人の融資率(住宅価格に対する借入額の割合)は、「90%超~100%以下」が25.1%と最も多くなっています。次いで「80%超~90%以下」が16.5%と2番目に多いことから、住宅価格のおよそ1~2割程度の自己資金を用意する人が多いようです。
十分な自己資金があると借入額を抑えられ、返済負担が軽減されるため、審査で有利にはたらく可能性があります。一方、住宅購入費用をすべて住宅ローンでまかなう場合、そのぶん返済比率も高くなることから、慎重に審査される可能性が高まります。
派遣社員の住宅ローンのイメージ

住宅ローンを借り入れる際は、借入額や総返済額、毎月の支払額などをシミュレーションしておく必要があります。ここでは、具体的な例をもとに住宅ローンの返済負担を試算してみましょう。
前提条件は下記の通りです。
・月給:24万円(時給1,500円 × 8時間 × 20日)
・賞与:月給の1ヶ月分 × 年2回
・年収:336万円
・預貯金(頭金):350万円
仮に3,000万円の物件を購入する場合、頭金として350万円を入れると、借入額は2,650万円となります。35年の全期間固定タイプで1.8%の金利が適用された場合、毎月の返済額や総返済額は下記の通りです。
・毎月の返済額:8万6,000円
・総返済額:3,574万円
一般的に返済負担率は10~35%に収めることが望ましいとされています。このケースでは返済負担率が約30%となりますので、収支バランスの観点からも無理がないといえるでしょう。
※上記の金利はあくまで一例です。実際の金利は申し込み時点の市場動向や金融機関、個人の条件などによって異なります。最新の情報をご確認ください。
派遣社員が住宅ローンを申し込む際のポイント

派遣社員が住宅ローンを申し込む際には、いくつか気をつけたいポイントがあります。くわしく紹介していきましょう。
複数の金融機関を比較する
ひとくちに住宅ローンといっても、その商品性は金融機関によってさまざまです。住宅ローンを借り入れる際は、複数の金融機関を比較してより自分の意向に合うところを選ぶようにしましょう。
特に、金利タイプや金利水準、申込条件などは必ずチェックしておきたいポイントです。公式サイトで情報収集したり、金融機関の相談窓口を積極的に活用したりすることがおすすめです。
フラット35の利用を検討する
「フラット35」は、住宅金融支援機構と金融機関が提携して扱っている住宅ローンです。審査基準が民間の金融機関が提供する住宅ローンと異なり、勤続年数や雇用形態などの条件が比較的柔軟な場合があるため、派遣社員にとって有力な選択肢の一つとなり得ます。
金利タイプは、借入期間中ずっと同じ金利が続く「全期間固定金利型」です。適用される金利は窓口となる金融機関によっても異なるため、相談時に合わせて確認しておくとよいでしょう。
返済負担率を算出する
返済負担率とは、年収に占める返済額の割合を指します。返済額が大きくなるほど生活に与える負担が大きくなることから、住宅ローンを借りる際は慎重に借入額を決定する必要があります。特に、収入が安定しにくい派遣社員の場合はなおさらでしょう。
前述の通り、返済負担率は一般的に10~35%程度が目安とされています。仮に年収が350万の場合、年間返済額は35万円~122万円程度になる計算です。
また、派遣社員は現在の収入水準だけでなく、「今後勤務先が変わって収入が変動しても返済していけるか」ということも念頭に置いて借入額を決めるようにしましょう。
無理のない資金計画を立てる
マイホームの購入は「人生の3大支出」のひとつともされるほど、大きな支出を伴うライフイベントです。楽しみなことも多い一方、住宅ローンの借り入れをきっかけに収支バランスを崩す人も珍しくありません。
これから長い期間をかけて住宅ローンを返済していくためには、無理のない資金計画を立てることが大切です。たとえば「収入が減少しても払い続けられるか」「急な出費にも対応できるか」など、あらゆるシーンを想定しながら計画を立てていきましょう。
また、変動金利タイプで借り入れる場合は、金利上昇によって返済負担が増加した場合も想定しておく必要があります。
信用情報の確認と改善をおこなう
住宅ローン審査で必ず照会される信用情報は、自身で開示請求すれば内容を確認することができます。開示請求の方法は各機関によって異なり、インターネットで受け付けているところもあります。過去の支払い状況に不安がある場合は、どのような情報が記録されているか確認しておくとよいでしょう。
また、カードローンなどの利用残高がある場合は、住宅ローンに申し込む前に完済しておくのもひとつの方法です。
収入合算やペアローンを活用する
住宅ローンは、単独ではなく収入合算やペアローンによって借り入れる方法もあります。
収入合算とは、申込者のほかに配偶者などの収入を加味して審査を受ける方法です。単独での審査に不安がある場合は、収入合算を活用するのもよいでしょう。
また、ペアローンは1つの物件に対して2人で借り入れをおこなう方法です。2人が別々に住宅ローンを組むことから、それぞれ住宅ローン控除を受けられるメリットもあります。
ただし、収入合算とペアローンのどちらも、配偶者などの収入が減少したときのリスクを考慮しておかなければなりません。ライフプランの変化などを考慮しながら返済計画を立てるようにしましょう。
まとめ
住宅ローンの審査では勤続年数などをもとに返済能力が判断されます。派遣社員の場合、正社員に比べて収入が不安定になりやすいため、審査で不利にはたらくことも考えられます。
なるべく希望する条件で住宅ローンを借りるために、まずは、複数の金融機関で借入条件を比較したり、必要に応じて収入合算やペアローンの借り入れを検討してみましょう。理想のマイホームを手に入れるために、さまざまな工夫をこらしてみましょう。
- ライター:椿 慧理
- フリーライター。新卒後に入行した銀行で10年間勤務し、個人・法人営業として金融商品の提案・販売を務める。現在は銀行で培った多様な経験を活かし、金融・人材ライターとして幅広く活動中。2級ファイナンシャル・プランニング技能士、1種外務員資格、内部管理責任者資格を保有(編集:株式会社となりの編プロ)