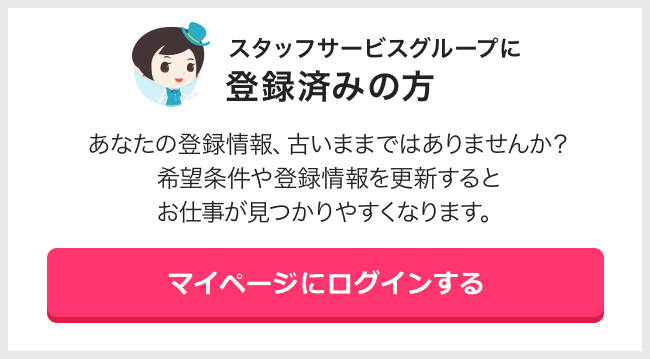年間休日とは?年間休日の平均や職場選びのポイントを解説

職場を決める際に、気になる情報として年間休日を挙げる人は少なくないでしょう。年間休日とは企業が定める1年間の休日数で、法律によって基準があるものの明確に日数が定められているわけではありません。
そのため、企業の裁量で日にちや曜日を設定できます。年間休日の考え方を理解すれば、職場選びの参考になるでしょう。本記事では、年間休日の定義や平均休日日数、日数ごとの設定パターンとともに職場選びの際のポイントについて解説します。
目次
年間休日とは
年間休日とは、企業が定める1年間の休日数です。休日には、労働基準法により定められている「法定休日」と企業が定める「法定外休日」があります。法定休日は「使用者(会社)が労働者に与えなければならない週に1回以上の休日または4週間で4回以上の休日」です。法定外休日は、夏季休暇や年末年始休暇、企業の特別な休日が該当します。
具体的な年間休日数は企業の裁量にゆだねられており、法定休日を遵守していれば、それ以上の休日を設けても構いません。そのため、年間休日数は企業や事業所によって異なります。
休日の定義
出勤しない日がすべて休日に含まれるわけではありません。例えば、有給休暇は労働基準法によって年5日以上の取得が義務化されている「法定休暇」です。個人によって取得日が異なるため、企業が指定した休日には含まれません。
ほかにも、結婚休暇やバースデー休暇といった企業独自の休暇も、年間休日には含まれません。ただし、夏季休暇や年末年始休暇などの、全員が一斉に休むことを指定された休暇は年間休日に含まれます。
法律上の定め
労働基準法第35条では、企業に対し「週に1回以上の休日または4週間で4回以上の休日を与えること」が定められています。労働基準法第32条では、週の労働時間の上限は40時間に定められています。
これらの定めから逆算した場合、企業が確保しなければならない年間休日数は、以下のとおりです。
1年間の労働時間上限:365日/7日×40時間=2085.7時間
1年間の労働日数上限:2085.7時間/8時間=260日
最低年間休日数:365日-260日=105日
ただし、あくまでも1日の労働時間を8時間とした場合の日数です。そのため、1日の労働時間が8時間より少なければ、最低年間休日数は105日よりも少なくなります。
参考: e-Gov法令検索「労働基準法」
休暇や休業との違い
休暇や休業は、休日とは定義が異なります。休暇や休業は、企業から労働を免除される日です。休暇には「法定休暇」と「特別休暇」があります。法定休暇は法律上設けられた休暇で、特別休暇は会社が独自に設ける休暇をいいます。それぞれに該当する主な休暇は以下のとおりです。
|
法定休暇 |
特別休暇 |
|
・有給休暇 |
・バースデー休暇 |
休暇が数日程度の短期ものであるのに対し、休業は長期的に労働を免除される日です。休業には、介護休業や育児休業が該当します。
休日は、企業が指定した「労働義務がない日」であるのに対し、休暇と休業は「労働が免除される日」であることが違いといえるでしょう。
年間休日の平均
年間休日は企業によって異なります。労働者の平均だけでなく、業種や職種、企業規模の平均がわかれば、職場を探す際の参考になるでしょう。ここでは、それぞれの平均年間休日を紹介します。
労働者の平均
厚生労働省の調査によると、2021年の平均年間休日数は115.3日でした。休日数ごとの分布は以下のとおりです。120~129日に設定している企業が最も多いことがわかります。
|
年間休日総数 |
割合 |
|
130日以上 |
1.7% |
|
120~129日 |
32.4% |
|
110~119日 |
21.1% |
|
100~109日 |
31.4% |
|
90~99日 |
6.2% |
|
80~89日 |
3.5% |
|
70~79日 |
1.6% |
|
69日以下 |
1.9% |
参考:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 労働時間制度 結果の概要」
業種ごとの平均
厚生労働省の調査によると、業種ごとの平均年間休日数は以下のとおりでした。上位の業種は120日に迫っているものの、下位の業種では100日前後となっており、業種によって差があることがわかります。
|
順位 |
業種 |
平均年間休日数 |
|
1 |
情報通信業 |
118.8日 |
|
1 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
118.8日 |
|
3 |
金融業、保険業 |
118.4日 |
|
4 |
電気・ガス・熱供給・水道業 |
116.8日 |
|
5 |
教育、学習支援業 |
112.7日 |
|
6 |
製造業 |
111.4日 |
|
7 |
複合サービス事業 |
110.4日 |
|
8 |
不動産業、物品賃貸業 |
109.6日 |
|
9 |
医療、福祉 |
109.4日 |
|
10 |
サービス業(他に分類されないもの) |
109.0日 |
|
11 |
卸売業、小売業 |
105.7日 |
|
12 |
生活関連サービス業、娯楽業 |
104.6日 |
|
13 |
建設業 |
104.0日 |
|
14 |
鉱業、採石業、砂利採取業 |
103.8日 |
|
15 |
運輸業、郵便業 |
100.3日 |
|
16 |
宿泊業、飲食サービス業 |
97.1日 |
参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」
企業規模ごとの平均
厚生労働省の調査によると、2021年の企業ごとの平均年間休日数は115.3日でした。企業規模が小さくなるにつれて、休日数が少なくなっていることがわかります。
|
年間休日総数 |
平均年間休日数 |
|
1,000人以上 |
119.3日 |
|
300~999人 |
117.3日 |
|
100~299人 |
113.1日 |
|
30~99人 |
111.2日 |
参考:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 労働時間制度 結果の概要」
年間休日数ごとの休日間隔

業種や企業規模によって平均年間休日に差があることがわかりましたが、年間休日数だけでは、どの程度の間隔で休日があるのかイメージしにくいかもしれません。週に2回休日があるとした場合の年間休日数を計算すると、以下のとおりになります。
1年間当たりの週の総数:365日/7日=52週
年間休日数:52週×2=104日
週に2回休日があれば、最低年間休日数はほとんど確保できます。祝日や年末年始などの休みを設けるのであれば、年間休日数を増やしたり、毎週の休日を調整したりしなければなりません。
企業によって休日の設定方法が異なるものの、年間休日数からどのような設定パターンがあるのかを予測できます。ここでは、土日休みをベースとした場合の、年間休日数ごとの休日設定について解説します。
125日の場合
年間休日数が125日の場合、週に2回休日があるだけでなく、祝日や夏季休暇、年末年始休暇などが休日に設定されています。例えば、2023年は祝日が16日あり、その場合の休日日数は以下のとおりです。
年間休日数:104日(週休2日)+16日=120日
祝日に加え、夏季休暇や年末年始で5日程度の休日を設ければ、125日になります。
120日の場合
年間休日数が120日の場合、毎週の休日を調整しているケースが考えられます。週休2日と祝日だけで年間休日数が120日となるものの、その場合は夏季休暇や年末年始休暇がとれません。サービス業ではない企業では、夏季休暇や年末年始休暇が設けられているはずです。
年間休日数が120日の場合は、祝日や夏季休暇がある週の土曜日の中から5日程度を出勤日にして調整していることが考えられるでしょう。
110日の場合
年間休日数が110日の場合、祝日の扱いで年間休日を調整しています。週休2日と夏季休暇や年末年始休暇を設けると110日程度になります。その場合、祝日の休みを設けられません。調整方法として予想できるパターンは以下の2つです。
● 祝日や夏季休暇がある週の土曜日を出勤日+夏季休暇や年末年始休暇を設ける
● 週休2日+夏季休暇や年末年始休暇を設ける
祝日は休日にするものの、同じ週の土曜日を出勤日とすることにより休日数を相殺するパターンと、祝日自体を休日にしないパターンがあります。中には、2つのパターンを組み合わせる企業もあります。
105日の場合
年間休日数が105日は、労働基準法での最低年間休日数です。ただし、夏季休暇や年末年始休暇を設けないことは考えにくいでしょう。105日の場合に想定できる調整方法は以下のとおりです。
土曜日を隔週出勤+祝日+夏季休暇や年末年始休暇を設ける
土曜日を隔週または月1出勤+夏季休暇や年末年始休暇を設ける
105日の場合、完全に週休2日を確保することは困難です。ただし、その場合は労働基準法で定められた1週間の労働時間を超過する可能性があるため、1日の労働時間が8時間よりも少ないことが考えられるでしょう。
年間休日数が105日を下回っていても違法ではないケース
労働基準法では1日や1週間、1年間の労働時間が定められています。休日についても1週間に1日の休日を確保することは定められているものの、年間休日数が定められているわけではありません。そのため、年間休日数が105日を下回っていても違法にならないケースがあります。違法にならないケースとして挙げられるのは以下のとおりです。
● 1日あたりの労働時間が短い
● 変形労働時間制を採用している
週休1日の場合、祝日や夏季休暇、年末年始休暇を設けても、52日+16日+5日で年間休日は73日です。しかし、1日当たりの労働時間が6時間であれば、週休1日でも1週間の労働時間は36時間です。労働基準法で定められている40時間よりも少ないため、違法にはなりません。
また、変形労働時間制を採用している場合、月単位や年単位で労働時間を換算します。労働基準法で定められている「1週間に1日の休日」さえ確保していれば違法にはなりません。
年間休日数が105日を下回っていても、必ずしも違法となるわけではないことを理解しておきましょう。
年間休日の注意点

年間休日の考え方に対する注意点として、以下の2つが挙げられます。
● 日にちや曜日は会社が設定する
● 週休2日制と完全週休2日制は異なる
ここでは、それぞれの注意点について解説します。
日にちや曜日は会社が設定する
休日の日にちや曜日は、法律で定められているわけではありません。法律で定められているのは、労働時間や1週間当たりの休日数です。そのため、たとえ年間休日数が同じでも、企業によって休める日や曜日が異なります。
規模の大きい企業であれば、部署や事業所によって、休日が異なるケースもあるでしょう。例えば小売業であれば、現場の従業員は平日を休みに、本部の従業員は土日を休みに設定しているケースもあります。
休日を設定する権限は企業側にあることを理解しておきましょう。
週休2日制と完全週休2日制は異なる
休日を理解するうえで、週休2日制の意味について理解しておかなければなりません。週休2日制とは、月に1回以上、週に2回の休日がある制度です。毎週2回の休日がある制度は「完全週休2日制」といいます。
週休2日制という名称がついているため混同されるケースがありますが「完全」の有無により年間休日数が大きく異なるため、注意が必要です。
休日が多い職場を探すには
休日が多い職場を探すのであれば、以下のポイントを押さえる必要があります。
● 規模が大きい会社や休みが多い業界を探す
● 福利厚生や休暇制度も確認する
● 有給の取得率も確認する
ここでは、それぞれのポイントについて解説します。
規模が大きい企業や休みが多い業界を探す
休日数が多い職場を探すのであれば、規模が大きい会社や休みが多い業界を探すのもひとつの手です。前述したように、規模が大きい企業ほど年間休日数は多い傾向にあります。
業界では「情報通信業」「学術研究、専門・技術サービス業」「金融業、保険業」の年間休日が多いことが明らかになっています。このような企業や業界から探していけば、しっかり休める職場と巡り合える可能性が高まるでしょう。
福利厚生や休暇制度も確認する
福利厚生や休暇制度も確認しておくと良いでしょう。前述したように、結婚休暇やバースデー休暇といった企業独自の休暇は年間休日数に含まれません。そのため、企業の年間休日数が少なくても、独自の休暇があれば総合的な休日は多い可能性があります。
また、育児休暇や介護休暇といった、将来的に必要になる休暇が整備されているかどうかもポイントです。これらの休暇が整備されており、実際に利用した例が多ければ、安心して働けます。
休日数だけで判断するのではなく、制度も含めて休日数や働きやすさを比べましょう。
有給休暇の取得率も確認する
有給休暇の取得率も、確認しておきたいポイントです。企業独自の休暇と同様に、有給休暇も年間休日数には含まれません。現在は年間5日の取得義務があるものの、それ以上の取得については企業の制度や風土によって異なります。
厚生労働省の調査によると、平均取得日数の上位3業種は以下のとおりでした。
複合サービス事業:14.4日
電気・ガス・熱供給・水道業:14.4日
製造業:12.3日
積極的に有給休暇を取得する企業であれば、年間休日数に対して10日以上も休日が増える可能性があります。有給休暇の取得率や取得数も確認しておきましょう。
参考:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 労働時間制度 結果の概要」
まとめ

年間休日とは、企業が定める1年間の休日数で、法定休日と法定外休日があります。法定休日とは「週に1回以上の休日または4週間で4回以上の休日」で、法定外休日は夏季休暇や年末年始休暇、企業の特別な休日が該当します。
休日の具体的な日にちや曜日は企業の裁量にゆだねられており、法定休日を遵守していれば、それ以上の休日を設けても構いません。そのため、年間休日数は企業や事業所によって異なります。
労働基準法で定められている労働時間から算出すると、最低年間休日は105日です。週に2回の休日を設定すれば年間休日は104日となり、祝日や年末年始休暇などの休日を設けていれば、年間休日は110~120日程度になります。
休日が多い職場を探す際のポイントは以下の3つです。
● 規模が大きい会社や休みが多い業界を探す
● 福利厚生や休暇制度も確認する
● 有給の取得率も確認する
年間休日の考え方や設定パターンを理解し、年間休日数から休日の設定方法を予測してみましょう。
- ライター:田仲ダイ
- エンジニアリング会社でマネジメントや人事、採用といった経験を積んだのち、フリーランスのライターとして活動開始。現在はビジネスやメンタルヘルスの分野を中心に、幅広いジャンルで執筆を手掛けている。