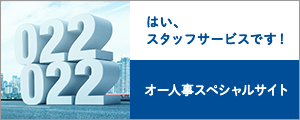無期雇用派遣とは?企業側のメリットと留意点、正社員・有期雇用派遣との違いを解説

無期雇用派遣とは、派遣会社と期間の定めなく雇用契約を結び、派遣先で就業する働き方です。2013年以降の労働契約法改正や2020年の労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)改正により、有期契約の不安定さを解消し、安定雇用の実現を図る手段として注目が高まっています。加えて、慢性的な人手不足に悩む企業にとっても、安定した人材確保を可能にする有効な選択肢です。
本記事では、無期雇用派遣の仕組みや正社員との違い、企業・派遣スタッフそれぞれのメリットと注意点、導入の進め方について詳しく解説します。「優秀な派遣スタッフに、ずっと長く働いていてほしい」と考えている企業の担当者は参考にしてください。
目次
無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、派遣会社と派遣スタッフの間で契約期間の定めがない無期雇用契約を締結し、派遣先企業に派遣する雇用形態です。派遣スタッフは派遣会社の無期雇用社員としての身分を持ちつつ、派遣先での業務に従事できます。
企業にとっては、業務の指揮命令は自社でおこないながら、雇用管理の負担を軽減できる点がメリットです。無期雇用派遣の仕組みや制度上の位置づけを理解したうえで、実際の活用方法や他の雇用形態との違いについて検討していきましょう。
無期雇用派遣の定義・仕組み
無期雇用派遣は、派遣スタッフと派遣会社が無期雇用契約を締結し、継続的に企業へ派遣される制度です。常用型派遣とも呼ばれています。契約期間に定めがなく、派遣先での業務終了後も雇用は継続され、原則一定の給与または休業手当が支払われる仕組みが整っています。
派遣スタッフにとっては安定性が高く、企業にとっても人材の計画的活用がしやすくなります。たとえば急な人員補充や専門性を要する業務にも柔軟に対応でき、欠員リスクを最小限に抑えることが可能です。結果として、労働環境の安定化と業務効率の向上を同時に実現できる制度といえるでしょう。
常用型派遣としての位置づけ
無期雇用派遣は、2015年の労働者派遣法改正によって制度化された常用型派遣に分類されます。無期契約を締結した派遣スタッフを継続的に企業へ派遣することで、一定水準の業務遂行力と組織適応力をもった人材の確保が可能です。
人材の入れ替えが頻繁に起きる有期雇用派遣(登録型派遣)とは異なり、業務知識やノウハウの蓄積が期待できるため、現場の教育コストも軽減されます。特に、専門部署や長期プロジェクトを運営する部門では、戦力の維持が重要です。常用型派遣の活用は組織全体の生産性や安定運営に寄与し、企業文化への順応も図りやすく、人事戦略上の効果も高まります。
関連リンク
スタッフサービスの常用型(無期雇用)サービスの紹介
雇用主と指揮命令権
無期雇用派遣では、派遣スタッフの雇用主は派遣会社であり、給与の支払いや雇用契約の管理はすべて派遣会社が担います。一方、日々の業務指示や評価などの実務的なマネジメントは、派遣先企業の責任によりおこなわれます。このように、雇用と指揮命令の権限が分離されているため、双方の役割を明確に理解したうえで受け入れ体制を整備することが不可欠です。
派遣スタッフにとっても、自身の指示系統と雇用元が明確であることで業務への集中力が高まり、トラブルの未然防止につながります。企業にとっては、管理工数の削減と同時に、即戦力人材を効率的に配置できるのが実務上のポイントです。
有期雇用派遣(登録型派遣)との違い

有期雇用派遣と無期雇用派遣の最大の違いは、雇用契約の「期間」にあります。双方の特徴を正しく理解し、自社の人材戦略に合った雇用形態を選んでいきましょう。
契約期間の有無
無期雇用派遣では、派遣スタッフと派遣会社との間に期間の定めがない雇用契約が締結されます。たとえ派遣先企業での業務が終了しても、派遣企業からの雇用は継続され、待機中にも給与や研修の機会があります。有期雇用派遣の場合は、あらかじめ決まった期間ごとに契約が終了し、派遣先がない期間は収入が発生しません。
また、有期型には「3年ルール」があり、同一部署への派遣は最長3年までと制限されています。無期雇用派遣はこのルールの対象外であるため、長期プロジェクトや継続性の高い業務に適しています。安定性の高さは、従業員の定着や業務効率の維持にもつながる重要な要素です。
派遣料金の違い
厚生労働省の令和5年度労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)によると、派遣料金は無期雇用派遣労働者は26,194円、有期雇用派遣労働者は21,307円です。無期雇用派遣では、一般的に有期雇用派遣よりも高く設定される傾向があります。これは派遣会社が待機期間中も給与を支払う義務を負うことや、昇給・賞与制度、教育訓練の実施などが含まれるためです。一方で、有期雇用派遣は業務がある時のみ人材を確保するため、短期的なコストを抑えることが可能です。
しかし、無期雇用派遣は安定した雇用環境を通じて人材の定着率や業務理解が深まり、結果として生産性の向上や採用・教育にかかる負担軽減につながります。目先のコストだけでなく、長期視点での費用対効果の比較が導入判断の鍵です。
出典:厚生労働省の令和5年労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)
正社員との違い

無期雇用派遣と正社員は、いずれも雇用期間の定めがない点で共通していますが、雇用主が異なります。無期雇用派遣では、派遣会社と雇用契約を結んでいるため、実際に働く派遣先企業が雇用主ではありません。給与体系や就業規則、福利厚生の内容も派遣会社の方針に基づくものとなり、正社員とは異なります。
業務上の役割や責任が似ていても、待遇や制度面に差があります。導入前に雇用管理・人件費の観点から両者の違いをみておきましょう。
コストの違い
無期雇用派遣は、初期費用や固定費の面で正社員採用とは異なるコスト構造を持ちます。採用活動や研修コストが派遣会社側に集約されるため、企業としては初期費用を抑えやすい一方、月給制・賞与・退職金などが派遣料金に反映され、一定の固定費が発生します。
また、無期雇用派遣は派遣期間の制限がないため、安定的に人材を活用したい企業向けの雇用形態です。長期的に見れば、採用リスクの回避や教育コストの削減といったメリットが期待できます。
労働条件の違い
無期雇用派遣の労働条件は、あくまでも派遣会社の就業規則に準じており、派遣先企業の正社員と同等ではありません。賞与や各種手当、福利厚生の内容も派遣会社の制度に依存するため、同じ職場で働いていても待遇に差が生じるケースがあります。
ただし、2020年の労働者派遣法改正により「同一労働同一賃金」の原則が導入され、派遣労働者の待遇改善が義務化されています。これにより、企業側のコスト負担も増加する可能性があるため、制度対応と予算計画の見直しが必要です。
企業から見た無期雇用派遣のメリット

無期雇用派遣は、企業が長期的・安定的にスキル人材を確保できる仕組みです。中長期的に人材投資の効率化を目指す企業が無期雇用派遣を活用するメリットをみていきましょう。
長期安定的な人材確保が可能
無期雇用派遣では、労働者が3年を超えて同じ職場で働くことが可能なため、企業は継続的に人材を確保できます。有期雇用派遣の場合、契約期間の満了ごとに人材の入れ替えが必要となり、一定のスキルを身につけた人材でも再配置せざるを得ません。
無期契約であれば、業務の継続性が求められるプロジェクトや責任あるポジションにも人材を配置できるため、職場内のノウハウ蓄積や業務効率の向上につながります。結果として、人的資源の有効活用が可能となり、安定的な事業運営が見込まれるでしょう。
期間制限(3年ルール)の適用外
無期雇用派遣は、有期雇用派遣に適用される「3年ルール」の対象外であり、個人単位・事業所単位のいずれにも期間制限が設けられていません。企業は同一の派遣スタッフに対して長期的な就業を依頼でき、計画的な人員配置が実現します。
人材の入れ替えによる教育コストや業務引き継ぎの手間が発生しにくく、継続性が重視される業務にも安心して任せることができます。制度の柔軟性を活かすことで、戦略的な人材活用が可能です。
経験やスキルを蓄積した人材の活用による生産性向上
無期雇用派遣では、派遣スタッフが長期間同じ業務を継続することで、企業内での業務理解やスキルの蓄積が進みます。職場環境にも慣れやすく、チームとの連携力も高まるため、生産性の向上が見込まれるでしょう。
また、派遣会社側でも採用時に実績やポテンシャルを確認しており、より業務適性の高い人材を配置しやすいという利点もあります。人材の流動性を抑えつつ、戦力化までのスピードを高めたい企業にとって、効率的な人材戦略の一環として検討すべき制度といえます。
採用・教育コストの削減
無期雇用派遣の活用により、企業は新たな派遣スタッフの採用・教育にかかるコストや工数を削減できます。
有期雇用派遣では、契約満了に伴って人材の入れ替えが生じ、引き継ぎや再教育が繰り返し必要です。無期雇用派遣であれば、同じ人材が長期的に就業することで、教育コストや業務の機会損失を大幅に抑えられます。人事や現場担当者の負担軽減にもつながり、採用難の状況下においても安定した人材運用が可能になります。
企業側の無期雇用派遣の留意点

無期雇用派遣は長期的な人材活用が可能な制度ですが、活用にあたっては留意すべき点も存在します。制度のメリットを十分に活かすために、リスクと義務を事前に理解し、受け入れ体制を整えておきましょう。
派遣スタッフが自社に残り続けるとは限らない
無期雇用派遣は雇用期間に制限がないことがメリットですが、派遣スタッフが自社に長く残るとは限りません。
雇用契約は派遣会社との間で結ばれており、派遣会社の方針や他の派遣先の事情により異動・終了となることがあります。企業がいかに継続的な就業を希望しても、最終的な配置決定権は派遣元にあるため、人材の安定活用が保証されるわけではありません。派遣元担当者とは雇用期間の意向など定期的にコミュニケーションをとると良いでしょう。
正社員募集情報の提供義務
労働者派遣法第40条の5に基づき、1年以上同じ派遣先で就業している無期雇用派遣スタッフがいる場合、企業は正社員の募集情報を該当スタッフに提供する義務があります。これは派遣スタッフのキャリア形成支援を目的としたもので、違反した場合は行政指導や指摘を受ける可能性も少なくありません。
制度への理解不足による法令違反を避けるためにも、受け入れ状況の把握や情報周知体制の整備が重要です。派遣スタッフとの信頼関係にも影響するため、適切な対応が求められるでしょう。
職場環境や業務内容の調整
無期雇用派遣を活用するには、派遣スタッフが職場に早く馴染み、スムーズに業務に従事できる環境整備が不可欠です。派遣先責任者の配置や業務マニュアルの整備、明確な指示系統の構築などにより、業務の効率化と定着率の向上が図れます。
また、企業文化や業務プロセスを理解しやすくする仕組みを整えることも、派遣スタッフのモチベーション維持に欠かせません。受け入れ体制の充実は、派遣労働者のパフォーマンスを最大化するための基本条件です。
労働者から見た無期雇用派遣のメリット・留意点

無期雇用派遣は、企業にとって安定した人材活用の手段である一方、働く側にとってもメリットがあります。企業が制度を活用する際には、労働者側の視点にも配慮し、制度設計や現場での対応に活かすことが、良好な労働環境づくりの鍵です。
雇用と収入の安定
無期雇用派遣では、派遣会社との雇用契約に期間の定めがないため、派遣スタッフにとって雇用の継続性が大きな安心材料です。3年ルールの対象外であるため、同じ職場で長く働くことが可能になり、業務の習熟や職場への定着も進みます。
また、収入が継続して得られる点は生活設計の安定にも寄与し、将来的なキャリア形成にも好影響を与えます。企業としては、こうした安定性が労働者の定着や業務効率向上につながる点を理解しておきましょう。
待機期間中の給与支払い
無期雇用派遣では派遣先での業務が終了した場合でも、次の就業先が決まるまでの待機期間中に給与または休業手当が支払われるのが原則です。労働者にとって収入が断たれるリスクを軽減する大きなメリットであり、安心して働き続けるための保障となります。
企業が制度を活用する際は、派遣社員が長期にわたって安定して働ける背景を理解し、業務指示や教育にもその前提を反映させることが求められます。
スキルアップとキャリア支援制度の利用
同じ職場で長期的に働くことにより、専門知識や業務スキルを深めることができます。また、派遣会社もキャリアビジョンに沿って長期的なアドバイスがしやすくなります。さらに、派遣会社が提供する研修やキャリア支援制度を利用できる点も、労働者にとっては大きな成長機会となるでしょう。
企業側から見ても、制度を通じて育成された人材は即戦力としての価値が高くなり、業務品質の向上や離職率の低下にもつながります。制度を活かすためには、企業と派遣会社の連携が不可欠です。
採用選考がある
無期雇用派遣として働くには、一般的に無期転換権を行使(いわゆる派遣の5年ルール)する場合が一般的です。派遣会社の採用を経て無期雇用契約を締結する場合は、採用選考がおこなわれることがあります。その際には、履歴書・職務経歴書による書類選考や面接が含まれる場合があり、有期派遣のような簡易な登録手続きとは異なります。
この選考プロセスにより、企業は意欲と適性を備えた人材を受け入れられるというメリットがありますが、労働者側には一定のハードルとなることも少なくありません。採用基準の明確化と派遣先とのすり合わせが、ミスマッチ防止に効果的です。
関連記事: 派遣の「5年ルール」とは?制度内容、適用条件、メリットを解説
無期雇用派遣の導入プロセスとポイント

無期雇用派遣をスムーズに導入するには、明確な目的設定と計画的なステップが欠かせません。特に初めて導入を検討する企業では、制度の特性や実務上のポイントを理解し、信頼できる派遣会社との連携体制を整えることが重要です。
導入にあたっては、派遣スタッフとのマッチングだけでなく、自社内での受け入れ準備や社内理解の醸成も不可欠です。ここでは、具体的な導入ステップと派遣会社選定、受け入れ体制整備のポイントを整理します。
導入ステップ
無期雇用派遣を導入するには、まず自社が抱える人材課題を明確化し、その解決手段として本制度を位置付けることが必要です。そのうえで、複数の派遣会社から情報を収集し、自社に合った人材が確保できるかどうかを比較検討します。
選考の際は、職場見学や面談等を通じてミスマッチを防ぎ、派遣スタッフと現場の適応性を確認することが重要です。契約に際しては、労働条件や業務内容について十分にすり合わせたうえで締結し、雇用後のトラブルを防止する体制を構築しましょう。
課題の明確化・目的の設定
自社の人材課題や業務負荷の現状を可視化し、無期雇用派遣を導入する明確な目的を設定します。定型化された業務の委託や専門スキルを有した即戦力人材の確保など、解決したい課題と目指す成果を整理しておくことで、導入効果を測定しやすくなります。
派遣会社への相談・情報収集
無期雇用派遣を提供している派遣会社を複数リストアップし、各社の実績・得意分野・サービス体制を比較します。派遣会社に求める人物像やお任せしたい業務内容を共有しながら相談をおこなうことで、的確な人材提案やマッチングの精度向上が期待できます。
求める人材要件(スキル、経験、人物像)の明確化
自社の業務に必要なスキル・資格・実務経験などを具体的に洗い出すとともに、組織文化や職場風土に合う人物像も明確にしておきましょう。また、業務遂行能力だけでなく、対人能力やチーム適応力といったソフトスキルにも着目しておくと安心です。
派遣会社からの候補者提案・選考
派遣会社から提案された候補者の書類選考・面談・必要に応じた実技評価などを通じて、自社とのマッチ度を見極めます。職場見学の実施も有効です。選考のミスマッチ防止と入社後の定着率向上につながります。
契約条件の確認と労働者派遣契約の締結
業務内容・就業条件・派遣期間・料金体系などの契約条件を事前にすり合わせします。問題がなければ、自社と派遣会社双方が合意したうえで労働者派遣契約を締結します。契約書の法令遵守状況やトラブル時の対応フローも事前に確認しておくと安心です。
派遣会社を選定する際のポイント
無期雇用派遣を成功させるには、適切な派遣会社の選定がカギです。自社の業務内容や職種に合致する人材を安定的に供給できるかどうか、フォローアップ体制が整っているか、法令遵守の姿勢が明確かといった観点が重要です。
派遣スタッフが長期的に定着するためには、派遣元と派遣先の連携も不可欠であり、信頼できるパートナーとしての派遣会社の見極めが欠かせません。
無期雇用派遣の実績とノウハウが豊富か
無期雇用派遣の実績やノウハウが豊富か確認します。実績のある派遣会社を選ぶことで、的確な人材提案や制度対応が期待できます。
希望する職種・スキルを持つ人材の登録者数や得意分野
自社ニーズに合った人材の在籍数やマッチング力を重視して選定していきます。
フォローアップ体制
派遣後も定期的な連絡や課題共有があり、派遣スタッフの就業継続に向けたサポート体制が整っているかを確認します。
コンプライアンス遵守の姿勢
労働法規に対する理解と法令順守の体制が整っている派遣会社を選ぶことが信頼の第一歩です。
受け入れ体制の整備と円滑なコミュニケーション
無期雇用派遣の人材がスムーズに業務へ移行するには、受け入れ準備と社内理解の促進が欠かせません。事前に業務環境を整えるとともに、現場責任者や関連部署との情報共有を徹底することで、受け入れ時の混乱や摩擦を防ぐことができます。
また、派遣スタッフと定期的に面談をおこなうことで、業務上の課題や不安の早期発見にもつながり、長期的な関係構築をサポートできます。
派遣スタッフがスムーズに業務を開始できるための準備
派遣スタッフがスムーズに業務を開始できるよう、PCや業務マニュアルなどの環境整備が不可欠です。また、業務内容や社内ルールを説明するオリエンテーションを実施することで、業務理解を深め、早期戦力化につながります。
社内での情報共有と理解促進
業務の進捗共有や連携を円滑にするため、定期ミーティングや報告の仕組みを整備しましょう。社内での情報共有を通じて、企業の経営方針や文化を伝えることで、派遣スタッフがチームの一員として溶け込みやすくなり、協働体制の強化が期待できます。
定期的な面談やフィードバックによるコミュニケーションの活性化
派遣スタッフとの定期的な面談を通じて業務状況や課題を把握し、必要なサポートを提供する環境をつくりましょう。業務に対するフィードバックを継続的におこなうことで、モチベーション向上とパフォーマンスの安定化が図れます。
無期雇用派遣の活用がおすすめの企業

無期雇用派遣は、単なる人員補充ではなく、長期的に人材を活用したい企業や、専門性の高い業務に即戦力を確保したい企業に特に適しています。3年ルールの制限がない点や、質の高い人材を安定的に確保できる点は、有期雇用派遣では得られない大きなメリットです。
採用や育成のリスクを抑えつつ、業務の継続性と生産性を高めたいと考えている企業へ無期雇用派遣の活用方法を紹介します。
長期的に特定業務を任せたい企業
無期雇用派遣は、3年以上の継続就業が可能なため、長期的な業務を安定的に任せたい企業に適しています。業務の習熟に時間がかかるポジションや、定着性が求められる業務においては、人材の入れ替えによる引き継ぎ負担を軽減できます。
また、無期雇用契約を結ぶ際には、派遣会社が一定の選考基準を設けているため、スキルや適性の高い人材を確保しやすいのも特徴です。業務の質や組織の安定性を重視する企業には、導入のメリットが大きい選択肢となります。
正社員採用が難しい専門分野の人材を探している企業
専門性の高い業務を担う人材の確保が難しい場合、無期雇用派遣は有効な解決策です。派遣会社が保有する即戦力人材を柔軟に活用できるため、育成にかかる時間やコストを削減できます。加えて、急なプロジェクト対応や繁忙期にも迅速な人材投入が可能で、業務の遅延リスクの軽減も可能です。
正社員採用では見極めが難しい場合も、実務を通じて適性を判断できる点で、コストパフォーマンスの高い人材活用ができるでしょう。
まとめ

無期雇用派遣は、派遣スタッフと派遣会社との間で期間の定めなく雇用契約を結ぶ形態です。企業にとっては安定的かつ柔軟な人材確保手段として注目されています。無期雇用派遣は3年ルールの制限を受けず、長期にわたって同一スタッフに業務を任せることができる点が最大の特徴です。
企業が無期雇用派遣を効果的に活用するためには、導入目的の明確化や適切な派遣会社の選定、受け入れ体制の整備が欠かせません。特に、長期的に業務を任せたい場合や、正社員採用が難しい専門人材の確保には、有力な選択肢となり得ます。
無期雇用派遣の特徴と活用ポイントを正しく理解し、自社にとって最適な人材活用の判断材料としていきましょう。
自社の人材戦略に無期雇用派遣が適しているかどうか、まずは現状の課題を整理し、信頼できる派遣会社に相談することが有効です。スタッフサービスでは、無期雇用派遣に関する豊富な実績と専門的なサポート体制を整えております。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
スタッフサービス:常用型派遣(無期雇用派遣)
<ライタープロフィール>
小山真奈
セールスライター兼オンライン事務代行。中小企業での経理9年の実務経験を活かし、現在は「伝わる資料」づくりに特化したスライド制作と事務代行を提供。構成・コピー・進行管理まで一貫対応し、実務に根ざした文章を執筆。